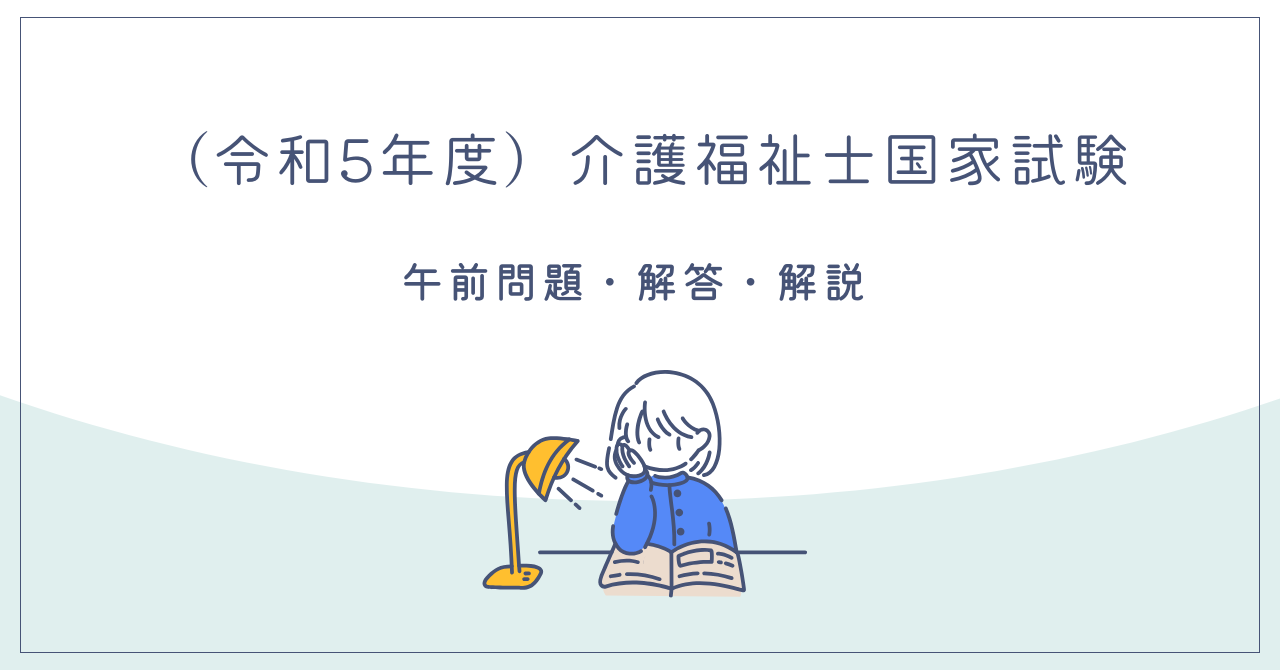人間の尊厳と自立
問題1
Aさん(76歳,女性,要支援1)は,一人暮らしである。週1回介護予防通所リハビリテーションを利用しながら,近所の友人たちとの麻雀を楽しみに生活している。最近,膝に痛みを感じ,変形性膝関節症(knee osteoarthritis)と診断された。同時期に友人が入院し,楽しみにしていた麻雀ができなくなった。Aさんは徐々に今後の生活に不安を感じるようになった。ある日,「自宅で暮らし続けたいけど,心配なの…」と介護福祉職に話した。
Aさんに対する介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 要介護認定の申請を勧める。
- 2 友人のお見舞いを勧める。
- 3 膝の精密検査を勧める。
- 4 別の趣味活動の希望を聞く。
- 5 生活に対する思いを聞く。
答え:5
解説:
Aさんは膝の痛みや楽しみ(生きがい)であった麻雀ができなくなったことが重なり、「今後の生活に不安」を感じています。介護福祉職の最初の対応として最も重要なのは、Aさんが「心配」と表現した漠然とした不安(何が心配なのか、どうなりそうだと感じているのか)を傾聴し、その思い(ニーズ)を具体的に把握することです。選択肢5は、この受容的・共感的な傾聴の姿勢として最も適切です。
1、3、4は、Aさんの不安の背景をアセスメントする前に、具体的な解決策(要介護申請、検査、趣味)を提示しており、時期尚早です。2はAさんの不安の直接的な解決にはなりません。
問題2
次の記述のうち,介護を必要とする人の自立についての考え方として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 自立は,他者の支援を受けないことである。
- 2 精神的自立は,生活の目標をもち,自らが主体となって物事を進めていくことである。
- 3 社会的自立は,社会的な役割から離れて自由になることである。
- 4 身体的自立は,介護者の身体的負担を軽減することである。
- 5 経済的自立は,経済活動や社会活動に参加せずに,生活を営むことである。
答え:2
解説:
介護における「自立」には、身体的自立、精神的自立、社会的自立、経済的自立など、多面的な意味があります。このうち「精神的自立」とは、他者の支援を受けながらでも、自分の生き方や生活の目標を自分で決め、主体的に生きていくこと(自己決定)を指します。選択肢2は、この精神的自立を正しく説明しています。
1は間違いです。他者の支援(サービス利用など)を受けながら主体的に生活することも「自立」と考えます。3は逆で、社会的自立とは社会とのつながりや役割を持つことです。4は介護者の負担軽減という結果であり、本人の自立の定義ではありません。5は経済的自立の定義として不適切です。
人間関係とコミュニケーション
問題3
U介護老人福祉施設では,利用者の介護計画を担当の介護福祉職が作成している。このため,利用者の個別の介護目標を,介護福祉職のチーム全員で共有することが課題になっている。この課題を解決するための取り組みとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 管理職がチーム全体に注意喚起して,集団規範を形成する。
- 2 現場経験の長い介護福祉職の意見を優先して,同調行動を促す。
- 3 チームメンバーの懇談会を実施して,内集団バイアスを強化する。
- 4 チームメンバー間の集団圧力を利用して,多数派の意見に統一する。
- 5 担当以外のチームメンバーもカンファレンス(conference)に参加して,集団凝集性を高める。
答え:5
解説:
課題は「介護目標をチーム全員で共有すること」です。この課題を解決するには、担当者だけが計画を把握するのではなく、担当以外のメンバーもカンファレンス(事例検討会)に参加し、利用者の目標や支援方針について積極的に意見交換する場を設けることが不可欠です。これにより、チームとしての情報共有が促進され、共通の目標に向かう一体感、すなわち「集団凝集性」が高まります。
1、2、4は、注意喚起、同調、集団圧力といった強制的な方法であり、専門職チームの主体的な情報共有にはつながりません。3の内集団バイアスは、自分たちのグループを他より優れていると思い込む偏見を指すため、不適切です。
問題4
Bさん(90歳,女性,要介護3)は,介護老人福祉施設に入所している。入浴日に,担当の介護福祉職が居室を訪問し,「Bさん,今日はお風呂の日です。時間は午後3時からです」と伝えた。しかし,Bさんは言っていることがわからなかったようで,「はい,何ですか」と困った様子で言った。このときの,介護福祉職の準言語を活用した対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 強い口調で伝えた。
- 2 抑揚をつけずに伝えた。
- 3 大きな声でゆっくり伝えた。
- 4 急かすように伝えた。
- 5 早口で伝えた。
答え:3
解説:
準言語(パラ言語)とは、声の大きさ、話す速さ、声のトーン(抑揚)など、言葉そのものの意味以外の情報伝達手段を指します。Bさんは90歳と高齢であり、一度で聞き取れず困った様子です。このような場合、Bさんが情報を処理しやすいように、「ゆっくり」と区切って話し、聞き取りやすいように「大きな(明瞭な)」声で伝えるという準言語の工夫が最も適切です。
1(強い口調)、4(急かす)、5(早口)は、Bさんの不安や混乱を強めてしまいます。2(抑揚をつけない)は、平坦でかえって聞き取りにくくなるため不適切です。
問題5
V介護老人福祉施設では,感染症が流行したために,緊急的な介護体制で事業を継続することになった。さらに労務管理を担当する職員からは,介護福祉職の精神的健康を守ることを目的とした組織的なマネジメントに取り組む必要性について提案があった。
次の記述のうち,このマネジメントに該当するものとして,最も適切なものを1 つ選びなさい。
- 1 感染防止対策を強化する。
- 2 多職種チームでの連携を強化する。
- 3 利用者のストレスをコントロールする。
- 4 介護福祉職の燃え尽き症候群(バーンアウト(burnout))を防止する。
- 5 利用者家族の面会方法を見直す。
答え:4
解説:
設問は、緊急体制という強いストレス下にある「介護福祉職の精神的健康を守る」ための組織的マネジメントは何かを問うています。燃え尽き症候群(バーンアウト)は、持続的な業務上のストレスによって引き起こされる情緒的消耗感や意欲の低下を指す、精神的健康の問題です。したがって、組織として過重な負担を管理し、相談体制を整えるなどして、バーンアウトを防止する取り組みが、まさに求められているマネジメントです。
1と5は感染対策、3は利用者への対応、2は業務プロセスであり、職員の「精神的健康を守る」という目的とは直接異なります。
問題6
次のうち,介護老人福祉施設における全体の指揮命令系統を把握するために必要なものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 組織図
- 2 勤務表
- 3 経営理念
- 4 施設の歴史
- 5 資格保有者数
答え:1
解説:
「指揮命令系統」とは、組織の中で誰が誰に指示を出し、誰が誰に報告するのかという、権限と責任の流れのことです。これを一覧で視覚的に示したものが「組織図」です。組織図を見れば、施設長を頂点として、各部署(介護部、看護部、相談部など)がどのようにつながり、誰が上司・部下にあたるのかが一目でわかります。
2(勤務表)はシフト、3(経営理念)は方針、4(歴史)は沿革、5(資格保有者数)は人員構成を示すものであり、指揮命令系統を示すものではありません。
社会の理解
問題7
次のうち,セルフヘルプグループ(self-help group)の活動に該当するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 断酒会
- 2 施設の社会貢献活動
- 3 子ども食堂の運営
- 4 傾聴ボランティア
- 5 地域の町内会
答え:1
解説:
セルフヘルプグループ(自助グループ)とは、アルコール依存症、難病、障害、ひきこもりなど、同じ課題や悩みを抱える当事者同士が集まり、互いに支え合い、体験を分かち合いながら問題を解決していくグループのことです。「断酒会」は、アルコール依存症の当事者が集まる代表的なセルフヘルプグループです。
2、3、4、5は、ボランティア活動や地域活動であり、当事者同士の相互支援を主目的とするセルフヘルプグループの定義とは異なります。
問題8
特定非営利活動法人(NPO法人)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 社会福祉法に基づいて設置される。
- 2 市町村が認証する。
- 3 保健,医療又は福祉の増進を図る活動が最も多い。
- 4 収益活動は禁じられている。
- 5 宗教活動を主たる目的とする団体もある。
答え:3
解説:
特定非営利活動促進法(NPO法)では20分野の活動が定められていますが、内閣府の調査などにおいて「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」は、NPO法人が最も多く取り組んでいる活動分野となっています。
1は「特定非営利活動促進法」に基づきます。2の認証は「都道府県」または指定都市が行います。4は、収益を非営利活動に充てることを条件に「収益活動」も可能です。5は、宗教活動や政治活動を「主たる目的」とすることはできません。
問題9
地域福祉において,19世紀後半に始まった,貧困地域に住み込んで実態調査を行いながら住民への教育や生活上の援助を行ったものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 世界保健機関(WHO)
- 2 福祉事務所
- 3 地域包括支援センター
- 4 生活協同組合
- 5 セツルメント
答え:5
解説:
セツルメント(Settlement)は、19世紀後半にイギリスのロンドンなどで始まった社会事業活動です。大学の研究者や学生が、貧困地域(スラム)に実際に「住み込み」(Settlement)、住民の実態調査や教育、生活支援を行った活動を指します。
1、2、3はすべて20世紀(主に第二次大戦後や21世紀)に設立された機関・制度であり、19世紀後半の活動ではありません。4も異なる起源を持つ運動です。
問題10
社会福祉基礎構造改革に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 社会福祉法が社会福祉事業法に改正された。
- 2 利用契約制度から措置制度に変更された。
- 3 サービス提供事業者は,社会福祉法人に限定された。
- 4 障害福祉分野での制度改正は見送られた。
- 5 判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された。
答え:5
解説:
2000年の社会福祉法改正を含む社会福祉基礎構造改革において、判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者など)の福祉サービス利用援助や金銭管理を支援するため、「地域福祉権利擁護事業」が創設されました(現在は「日常生活自立支援事業」と呼ばれています)。
1は逆で、「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改正されました。2も逆で、行政がサービスを決める「措置制度」から、利用者が事業者を選んで契約する「利用契約制度」へ移行しました。3は逆で、株式会社やNPO法人なども参入できるようになりました。4も間違いで、障害福祉分野も改革の対象でした。
問題11
Cさん(77歳,男性)は,60歳で公務員を定年退職し,年金生活をしている。持病や障害はなく,退職後も趣味のゴルフを楽しみながら健康に過ごしている。ある日,Cさんはゴルフ中にけがをして医療機関を受診した。このとき,Cさんに適用される公的医療制度として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 国民健康保険
- 2 後期高齢者医療制度
- 3 共済組合保険
- 4 育成医療
- 5 更生医療
答え:2
解説:
公的医療制度において、75歳以上の人は、それまで加入していた医療保険(国民健康保険、被用者保険、共済組合など)から脱退し、原則として全員が「後期高齢者医療制度」に加入します。Cさんは77歳であるため、この制度が適用されます。
1の国民健康保険や3の共済組合保険は、主に74歳までの人が加入する制度です。4と5は障害者総合支援法に基づく特定の医療費助成制度です。
問題12
次のうち,介護保険法に基づき,都道府県・指定都市・中核市が指定(許可),監督を行うサービスとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 地域密着型介護サービス
- 2 居宅介護支援
- 3 施設サービス
- 4 夜間対応型訪問介護
- 5 介護予防支援
答え:3
解説:
介護保険法において、サービスの指定・監督権限はサービスの種類によって異なります。「施設サービス」(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など)の指定・監督は、「都道府県」が行います(指定都市・中核市も都道府県と同様の権限を持ちます)。
1、2、4、5(地域密着型サービス、居宅介護支援、夜間対応型訪問介護、介護予防支援)は、すべて利用者の身近な「市町村」が指定・監督を行います。
問題13
「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 法の対象者は,身体障害者手帳を交付された者に限定されている。
- 2 合理的配慮は,実施するときの負担の大小に関係なく提供する。
- 3 個人による差別行為への罰則規定がある。
- 4 雇用分野での,障害を理由とした使用者による虐待の禁止が目的である。
- 5 障害者基本法の基本的な理念を具体的に実施するために制定された。
(注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
答え:5
解説:
障害者差別解消法は、「障害者基本法」が定める「差別の禁止」という基本的な理念(理想)を、社会のなかで具体的に実現するために制定された法律です。この法律により、「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」が定められました。
1は手帳の有無に関わらず、支援を必要とする全ての障害者が対象です。2は「過重な負担」にならない範囲での提供とされています。3は個人への罰則規定はありません。4は障害者虐待防止法などの内容と近いです。
問題14
「障害者総合支援法」に規定された移動に関する支援の説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 移動支援については,介護給付費が支給される。
- 2 行動援護は,周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。
- 3 同行援護は,危険を回避できない知的障害者が利用する。
- 4 重度訪問介護は,重度障害者の外出支援も行う。
- 5 共同生活援助(グループホーム)は,地域で生活する障害者の外出支援を行う。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
答え:4
解説:
「重度訪問介護」は、重度の肢体不自由や知的・精神障害があり常時介護が必要な人に対して、居宅内での介護(入浴、排泄、食事など)だけでなく、「外出時における移動中の介護」も一体的に提供するサービスです。
1の「移動支援」は、介護給付費(自立支援給付)ではなく「地域生活支援事業」として市町村が実施します。2の「行動援護」は知的障害や精神障害のある人が対象です。3の「同行援護」は視覚障害のある人が対象です。5の共同生活援助(グループホーム)は住まいの場であり、外出支援は移動支援などの別サービスを利用するのが基本です。
問題15
Dさん(80歳,男性,要介護2)は,認知症(dementia)がある。訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用しながら一人暮らしをしている。
ある日,訪問介護員(ホームヘルパー)がDさんの自宅を訪問すると,近所に住むDさんの長女から,「父が,高額な投資信託の電話勧誘を受けて,契約しようかどうか悩んでいるようで心配だ」と相談された。訪問介護員(ホームヘルパー)が長女に助言する相談先として,最も適切なものを 1つ選びなさい。
- 1 公正取引委員会
- 2 都道府県障害者権利擁護センター
- 3 運営適正化委員会
- 4 消費生活センター
- 5 市町村保健センター
答え:4
解説:
高齢者が高額な契約や悪質な勧誘などでトラブルに巻き込まれた(または巻き込まれそうな)場合、専門の相談窓口は「消費生活センター」です。消費者ホットライン(電話番号188)などで相談でき、契約内容の確認、クーリング・オフの方法、事業者との交渉などについて助言・支援を行います。Dさんの認知症(判断能力の低下)が背景にある点も含めて相談すべき機関です。
1は独占禁止法、2は障害者虐待、3は福祉サービスの苦情、5は公衆衛生が専門であり、契約トラブルの相談先ではありません。
問題16
災害時の福祉避難所に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 介護老人福祉施設の入所者は,原則として福祉避難所の対象外である。
- 2 介護保険法に基づいて指定される避難所である。
- 3 医療的ケアを必要とする者は対象にならない。
- 4 訪問介護員(ホームヘルパー)が,災害対策基本法に基づいて派遣される。
- 5 同行援護のヘルパーが,災害救助法に基づいて派遣される。
答え:1
解説:
福祉避難所は、一般の避難所(一次避難所)での生活が困難な、「在宅」で生活している高齢者や障害者など(要配慮者)を受け入れるために市町村が指定する二次的な避難所です。介護老人福祉施設などの入所者は、すでに施設で安全が確保され、ケアを受けられる体制にあるため、原則として福祉避難所の対象とはなりません。
2は「災害対策基本法」に基づき市町村が指定します。3は医療的ケアが必要な人も、福祉避難所の対象に含まれます。4や5のような派遣制度はありません。
問題17
「感染症法」に基づいて,結核(tuberculosis)を発症した在宅の高齢者に,医療費の公費負担の申請業務や家庭訪問指導などを行う機関として,適切なものを 1つ選びなさい。
- 1 基幹相談支援センター
- 2 地域活動支援センター
- 3 保健所
- 4 老人福祉センター
- 5 医療保護施設
(注) 「感染症法」とは,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」のことである。
答え:3
解説:
「保健所」は、地域保健法や感染症法に基づき、結核を含む感染症の予防、まん延防止、公費負担医療の申請受付、患者への家庭訪問指導、服薬支援(DOTS)など、地域の公衆衛生に関する業務を担う中心的な機関です。
1、2は障害福祉の相談・活動拠点、4は高齢者の交流施設、5は生活保護法に基づく医療施設であり、感染症対策の中心機関ではありません。
問題18
Eさん(55歳,女性,障害の有無は不明)は,ひきこもりの状態にあり,就労していない。父親の年金で父親とアパートで暮らしていたが,父親が亡くなり,一人暮らしになった。遠方に住む弟は,姉が家賃を滞納していて,生活に困っているようだと,家主から連絡を受けた。心配した弟が相談する機関として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 地域包括支援センター
- 2 福祉事務所
- 3 精神保健福祉センター
- 4 公共職業安定所(ハローワーク)
- 5 年金事務所
答え:2
解説:
Eさんは55歳であり、父親の死亡によって収入が途絶え、家賃滞納など「生活困窮」状態に陥っています。このような生活困窮者の相談や、生活保護の申請窓口となるのが「福祉事務所」(または市町村の生活支援担当課)です。ひきこもり支援の窓口とも連携しながら、Eさんの生活を立て直すための相談ができます。
1は主に65歳以上の高齢者の相談窓口です。3は精神保健福祉の専門機関、4は職業紹介、5は年金事務の窓口であり、Eさんの現在の生活困窮に関する第一相談窓口としては不適切です。
こころとからだのしくみ
問題19
次のうち,マズロー(Maslow, A.H.)の欲求階層説で成長欲求に該当するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 承認欲求
- 2 安全欲求
- 3 自己実現欲求
- 4 生理的欲求
- 5 所属・愛情欲求
答え:3
解説:
マズローの欲求階層説では、欲求は「欠乏欲求」と「成長欲求」に大別されます。このうち最も高次な欲求である「自己実現欲求」(自分の可能性を最大限に追求したい)が、唯一「成長欲求」に分類されます。
1、2、4、5(承認、安全、生理的、所属・愛情)は、いずれも他者や外部環境から満たされることを求める「欠乏欲求」に分類されます。
問題20
次のうち,交感神経の作用に該当するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 血管収縮
- 2 心拍数減少
- 3 気道収縮
- 4 消化促進
- 5 瞳孔収縮
答え:1
解説:
交感神経は、身体を活動的・緊張状態(闘争か逃走か)にする役割があります。活動に備えて血圧を上げるため、末梢の「血管を収縮」させます。
2の心拍数減少、3の気道収縮、4の消化促進、5の瞳孔収縮は、すべて身体をリラックス・休息状態にする「副交感神経」の作用です。交感神経が優位なときは、心拍数は増加し、気道は拡張し、消化は抑制され、瞳孔は散大します。
問題21
Fさん(82歳,女性)は,健康診断で骨粗鬆症(osteoporosis)と診断され,内服治療が開始された。杖歩行で時々ふらつくが,ゆっくりと自立歩行することができる。昼間は自室にこもり,ベッドで横になっていることが多い。リハビリテーションとして週3日歩行訓練を行い,食事は普通食を毎食8割以上摂取している。
Fさんの骨粗鬆症(osteoporosis)の進行を予防するための支援として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 リハビリテーションを週1日に変更する。
- 2 繊維質の多い食事を勧める。
- 3 日光浴を日課に取り入れる。
- 4 車いすでの移動に変更する。
- 5 ビタミンA(vitamin A)の摂取を勧める。
答え:3
解説:
骨粗鬆症の予防・進行防止には、カルシウムの吸収を助けるビタミンDが必要です。ビタミンDは、食事から摂取するほか、皮膚が紫外線を浴びる(日光浴)ことでも体内で生成されます。Fさんは自室にこもりがちであるため、日光浴を日課に取り入れることは非常に有効な支援です。
1や4は、骨に負荷をかける機会(歩行訓練や自立歩行)を減らしてしまうため、かえって骨を弱くする可能性があります。2(繊維質)は便通、5(ビタミンA)は皮膚や粘膜に関連しますが、骨粗鬆症の直接的な予防支援としては優先度が低いです。
問題22
中耳にある耳小骨として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 ツチ骨
- 2 蝶形骨
- 3 前頭骨
- 4 頬骨
- 5 上顎骨
答え:1
解説:
中耳は、鼓膜から伝わってきた音の振動を増幅させる「ツチ骨」「キヌタ骨」「アブミ骨」という3つの耳小骨から構成されています。よって、1が正解です。
2(蝶形骨)、3(前頭骨)、4(頬骨)、5(上顎骨)は、いずれも頭蓋骨を構成する骨であり、中耳の耳小骨ではありません。
問題23
成人の爪に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 主成分はタンパク質である。
- 2 1 日に1mm程度伸びる。
- 3 爪の外表面には爪床がある。
- 4 正常な爪は全体が白色である。
- 5 爪半月は角質化が進んでいる。
答え:1
解説:
爪は皮膚の一部が変化したもので、髪の毛と同じ「ケラチン」というタンパク質が主成分です。
2は間違いです。1日に伸びる長さは約0.1mm程度(1か月に約3mm)です。3の爪床(そうしょう)は、爪の板(爪甲)の「下」にある皮膚組織を指します。4は間違いです。正常な爪は半透明で、下の爪床にある毛細血管が透けて見えるためピンク色に見えます。5は逆で、爪半月(そうはんげつ)は新しく作られたばかりの角質化が進んでいない(水分を多く含む)部分であるため白く見えます。
問題24
食物が入り誤嚥が生じる部位として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 扁桃
- 2 食道
- 3 耳管
- 4 気管
- 5 咽頭
答え:4
解説:
誤嚥(ごえん)とは、食物や水分、唾液などが、本来の通り道である「食道」ではなく、誤って空気の通り道である「気管」に入ってしまうことを指します。「間違って気管に入る」ため、4が正解です。
5の咽頭は、空気と食物の共通の通り道であり、ここから気管と食道に分岐します。
問題25
Gさん(79歳,男性)は,介護老人保健施設に入所している。Gさんは普段から食べ物をかきこむように食べる様子がみられ,最近はむせることが多くなった。義歯は使用していない。食事は普通食を摂取している。ある日の昼食時,唐揚げを口の中に入れたあと,喉をつかむようなしぐさをし,苦しそうな表情になった。
Gさんに起きていることとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 心筋梗塞(myocardial infarction)
- 2 蕁麻疹(urticaria)
- 3 誤嚥性肺炎(aspiration pneumonia)
- 4 食中毒(foodborne disease)
- 5 窒息(choking)
答え:5
解説:
Gさんは、かきこみ食べやむせが多く、咀嚼(義歯なし)にも問題がある可能性が示唆されています。食事中に「喉をつかむようなしぐさ」(チョークサイン)や「苦しそうな表情」が見られたことから、食べ物が気道に詰まり、呼吸ができなくなる「窒息」の状態に陥っていると判断するのが最も適切です。
1(心筋梗塞)は胸痛、2(蕁麻疹)は皮膚症状、3(誤嚥性肺炎)は誤嚥が原因で起こる肺炎であり、即時の症状ではありません。4(食中毒)は食後の腹痛や嘔吐・下痢が主症状です。
問題26
Hさん(60歳,男性)は,身長170cm,体重120kgである。Hさんは浴槽で入浴しているときに毎回,「お風呂につかると,からだが軽く感じて楽になります」と話す。胸が苦しいなど,ほかの訴えはない。Hさんが話している内容に関連する入浴の作用として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 静水圧作用
- 2 温熱作用
- 3 清潔作用
- 4 浮力作用
- 5 代謝作用
答え:4
解説:
入浴時に「からだが軽く感じる」のは、水がお湯の中で身体を押し上げようとする「浮力作用」によるものです。浮力により、水中では体重が約10分の1程度になり、重力から解放され、筋肉や関節の負担が軽減されます。Hさんは特に体重が多いため、この浮力による負担軽減(楽になる)を強く感じていると考えられます。
1(静水圧作用)は水圧によるマッサージや循環への影響、2(温熱作用)は温かさによるリラックスや血行促進、3(清潔作用)は汚れを落とすことです。
問題27
男性に比べて女性に尿路感染症(urinary tract infection)が起こりやすい要因として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 子宮の圧迫がある。
- 2 尿道が短く直線的である。
- 3 腹部の筋力が弱い。
- 4 女性ホルモンの作用がある。
- 5 尿道括約筋が弛緩している。
答え:2
解説:
女性の尿道は、男性(約15~20cm)に比べて「約3~5cmと短く」、かつ「直線的」な構造をしています。また、肛門と尿道口が近いこともあり、大腸菌などの細菌が膀胱に侵入しやすく、膀胱炎などの尿路感染症を起こしやすい要因となっています。
1、3、4、5は、尿路感染症の直接的な要因としては不適切です。
問題28
次のうち,眠りが浅くなる原因として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 抗不安薬
- 2 就寝前の飲酒
- 3 抗アレルギー薬
- 4 抗うつ薬
- 5 足浴
答え:2
解説:
就寝前の飲酒(寝酒)は、一時的に寝つきを良くする(入眠促進)作用がありますが、アルコールが体内で分解される過程で覚醒作用のあるアセトアルデヒドが発生します。これにより、睡眠の後半(特に明け方)に眠りが浅くなったり、途中で目が覚めたり(中途覚醒)する原因となります。
1、3、4の薬剤は、種類によっては眠気を引き起こすものもありますが、眠りを浅くするとは限りません。5の足浴は、リラックス効果と深部体温の調整を助け、むしろ良質な睡眠を促進します。
問題29
概日リズム睡眠障害(circadian rhythm sleep disorder)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 早朝に目が覚める。
- 2 睡眠中に下肢が勝手にピクピクと動いてしまう。
- 3 睡眠中に呼吸が止まる。
- 4 睡眠中に突然大声を出したり身体を動かしたりする。
- 5 夕方に強い眠気を感じて就寝し,深夜に覚醒してしまう。
答え:5
解説:
概日リズム(サーカディアンリズム)睡眠障害とは、体内時計と実際の生活時間との間にズレが生じ、望ましい時間に眠れない状態を指します。選択肢5は、体内時計が前倒しになる「睡眠相前進型」(または睡眠・覚醒相前進障害)の特徴であり、高齢者によくみられます。夕方(極端に早い時間)に眠くなり、その分、深夜や早朝に目が覚めてしまう状態です。
2は周期性四肢運動障害、3は睡眠時無呼吸症候群、4はレム睡眠行動障害の説明です。1は加齢による変化や、5の結果として起こる症状です。
問題30
鎮痛薬としてモルヒネを使用している利用者に,医療職と連携した介護を実践するときに留意すべき観察点として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 不眠
- 2 下痢
- 3 脈拍
- 4 呼吸
- 5 体温
答え:4
解説:
モルヒネ(医療用麻薬)は、がんの痛みなどを緩和する強力な鎮痛薬ですが、副作用の一つに「呼吸抑制」(呼吸の回数が減る、呼吸が浅くなる)があります。これは生命に直結する重篤な副作用であるため、介護福祉職は医療職と連携し、利用者の呼吸状態(回数、深さ、リズム)に変化がないかを観察することが最も重要です。
1(不眠)よりは「傾眠」(眠気)が、2(下痢)よりは「便秘」や「嘔気」が、モルヒネの一般的な副作用としてよく知られています。
発達と老化の理解
問題31
スキャモン(Scammon, R.E.)の発達曲線に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 神経系の組織は,4歳ごろから急速に発達する。
- 2 筋骨格系の組織は,4歳ごろから急速に発達する。
- 3 生殖器系の組織は,12歳ごろから急速に発達する。
- 4 循環器系の組織は,20歳ごろから急速に発達する。
- 5 リンパ系の組織は,20歳ごろから急速に発達する。
答え:3
解説:
スキャモンの発達曲線は、体の組織を4つの型(一般型、神経型、生殖器型、リンパ型)に分けて発達のパターンを示したものです。このうち「生殖器型」(生殖器系の組織)は、思春期になる12歳ごろまでほとんど発達せず、その後20歳に向けて急速に発達するのが特徴です。
1の「神経型」は、出生直後から急速に発達し、4~6歳ごろまでに成人の約90%に達します。2と4の「一般型」(筋骨格系や循環器系)は、乳幼児期と思春期の2回、急速な発達(成長スパート)が見られます。5の「リンパ型」は、思春期(12歳ごろ)に成人の約200%とピークに達し、その後は低下します。
問題32
幼稚園児のJさん(6歳,男性)には,広汎性発達障害(pervasive developmental disorder)がある。砂場で砂だんごを作り,きれいに並べることが好きで,毎日,一人で砂だんごを作り続けている。
ある日,園児が帰宅した後に,担任が台風に備えて砂場に青いシートをかけておいた。翌朝,登園したJさんが,いつものように砂場に行くと,青いシートがかかっていた。Jさんはパニックになり,その場で泣き続け,なかなか落ち着くことができなかった。
担任は,Jさんにどのように対応すればよかったのか,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 前日に,「あしたは,台風が来るよ」と伝える。
- 2 前日に,「あしたは,台風が来るので砂場は使えないよ」と伝える。
- 3 前日に,「あしたは,おだんご屋さんは閉店です」と伝える。
- 4 その場で,「今日は,砂場は使えないよ」と伝える。
- 5 その場で,「今日は,おだんご屋さんは閉店です」と伝える。
答え:2
解説:
広汎性発達障害のあるJさんは、毎日の習慣(砂場での砂だんご作り)が予期せず変更されたこと(青いシート)でパニックを起こしています。このような場合、変更が起きる「前日」に、「なぜ(台風が来るので)」「何が変わるのか(砂場は使えない)」を具体的に予告(事前告知)することが最も重要です。これにより、Jさんは心の準備ができ、パニックを防げる可能性が高まります。
1と3は抽象的・比喩的であり、Jさんが「砂場が使えない」ことを具体的に理解するのは困難です。4と5は、パニックが起きた「その場」での対応であり、予防的な対応(事前告知)としては遅すぎます。
問題33
生理的老化に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 環境によって起こる現象である。
- 2 訓練によって回復できる現象である。
- 3 個体の生命活動に有利にはたらく現象である。
- 4 人間固有の現象である。
- 5 遺伝的にプログラムされた現象である。
答え:5
解説:
老化には、病気や環境要因による「病的老化(二次的老化)」と、誰にでも起こる「生理的老化(一次的老化)」があります。生理的老化は、生物が生まれながらにして持っている遺伝的なプログラム(設計図)に基づいて、避けられない形で起こる変化であると考えられています。
1は病的老化の説明です。2は、訓練で機能低下の速度を遅らせることはできますが、老化現象そのものを「回復」させることはできません。3は、老化は機能低下をもたらすため、生命活動に有利とは言えません。4は、人間だけでなく全ての生物に共通する現象です。
問題34
エイジズム(ageism)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 高齢を理由にして,偏見をもったり差別したりすることである。
- 2 高齢になっても生産的な活動を行うことである。
- 3 高齢になることを嫌悪する心理のことである。
- 4 加齢に抵抗して,健康的に生きようとすることである。
- 5 加齢を受容して,活動的に生きようとすることである。
答え:1
解説:
エイジズム(Ageism)とは、バトラー(Butler, R.)が提唱した概念で、「年齢」を理由にした偏見や固定観念、あるいはそれに基づく差別的な(不利益な)扱いを指します。特に高齢者に対する否定的な見方(例:「高齢者は頑固だ」「生産性がない」など)を指す場合が多いです。
2は「プロダクティブ・エイジング(生産的老化)」、5は「サクセスフル・エイジング(幸運な老化)」や「アクティブ・エイジング(活動的老化)」、4は「アンチ・エイジング(抗加齢)」の考え方に近いもので、エイジズムの定義ではありません。
問題35
Kさん(80歳,男性)は,40歳ごろから職場の健康診査で高血圧と高コレステロール血症(hypercholesterolemia)を指摘されていた。最近,階段を上るときに胸の痛みを感じていたが,しばらく休むと軽快していた。喉の違和感や嚥下痛はない。今朝,朝食後から冷や汗を伴う激しい胸痛が起こり,30分しても軽快しないので,救急車を呼んだ。
Kさんに考えられる状況として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 喘息(bronchial asthma)
- 2 肺炎(pneumonia)
- 3 脳梗塞(cerebral infarction)
- 4 心筋梗塞(myocardial infarction)
- 5 逆流性食道炎(reflux esophagitis)
答え:4
解説:
Kさんには高血圧、高コレステロール血症という動脈硬化のリスク因子があります。「階段を上ると胸が痛む(労作性狭心症)」という前兆があり、今朝の「30分以上続く激しい胸痛」「冷や汗」という症状は、狭心症が進行し、心臓の血管が完全に詰まってしまった急性心筋梗塞の典型的な症状です。
1(喘息)は呼吸困難や喘鳴(ゼーゼー音)、3(脳梗塞)は麻痺や言語障害、5(逆流性食道炎)は胸やけが主症状であり、Kさんの症状とは異なります。
問題36
次のうち,健康寿命の説明として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 0 歳児の平均余命
- 2 65 歳時の平均余命
- 3 65 歳時の平均余命から介護期間を差し引いたもの
- 4 介護状態に至らずに死亡する人の平均寿命
- 5 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間
答え:5
解説:
健康寿命(WHOが提唱)とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」の平均を指します。介護や支援を必要とせず、自立して生活できる期間のことです。
1の「0歳児の平均余命」は、「平均寿命」の定義です。平均寿命と健康寿命の差(日本では男性約9年、女性約12年)が、いわゆる介護や支援が必要となる期間にあたります。
問題37
次のうち,前立腺肥大症(prostatic hypertrophy)に関する記述として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 抗利尿ホルモンが関与している。
- 2 症状が進むと無尿になる。
- 3 初期には頻尿が出現する。
- 4 進行すると透析の対象になる。
- 5 骨盤底筋訓練で回復が期待できる。
答え:3
解説:
前立腺肥大症は、男性の尿道の周りにある前立腺が加齢とともに大きくなり、尿道を圧迫する疾患です。初期には、圧迫により膀胱が刺激され、尿意が近くなる「頻尿」(特に夜間頻尿)や、尿が出にくくなる「排尿困難」といった症状が出現します。
1(抗利尿ホルモン)は尿崩症など、2(無尿:尿が生成されない)は腎不全、4(透析)も腎不全、5(骨盤底筋訓練)は主に女性の尿失禁の対策であり、前立腺肥大症の直接的な原因や治療法ではありません。
問題38
次のうち,高齢期に多い筋骨格系の疾患に関する記述として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 骨粗鬆症(osteoporosis)は男性に多い。
- 2 変形性膝関節症(knee osteoarthritis)ではX脚に変形する。
- 3 関節リウマチ(rheumatoid arthritis)は軟骨の老化によって起こる。
- 4 腰部脊柱管狭窄症(lumbar spinal canal stenosis)では下肢のしびれがみられる。
- 5 サルコペニア(sarcopenia)は骨量の低下が特徴である。
答え:4
解説:
腰部脊柱管狭窄症は、加齢により背骨(腰椎)の中にある神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、中の神経が圧迫される疾患です。圧迫された神経に関連する部位、特に下肢(お尻から足先)に痛みやしびれが生じたり、歩行により症状が悪化したりします(間欠性跛行)。
1の骨粗鬆症は、閉経後の女性ホルモンの減少により、女性に圧倒的に多いです。2の変形性膝関節症は、多くの場合O脚(内反変形)となります。3の関節リウマチは自己免疫疾患であり、軟骨の老化が主な原因なのは変形性関節症です。5のサルコペニアは「骨量」ではなく「筋肉量」が低下する状態を指します(骨量の低下は骨粗鬆症)。
認知症の理解
問題39
高齢者の自動車運転免許に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 75 歳から免許更新時の認知機能検査が義務づけられている。
- 2 80 歳から免許更新時の運転技能検査が義務づけられている。
- 3 軽度認知障害(mild cognitive impairment)と診断された人は運転免許取消しになる。
- 4 認知症(dementia)の人はサポートカー限定免許であれば運転が可能である。
- 5 認知症(dementia)による運転免許取消しの後,運転経歴証明書が交付される。
(注) 「サポートカー限定免許」とは,道路交通法第91条の2の規定に基づく条件が付された免許のことである。
答え:1
解説:
道路交通法に基づき、75歳以上のドライバーは、免許更新時に全員が「認知機能検査」を受けることが義務付けられています。この検査結果に基づき、認知症の疑い(第1分類)や認知機能低下の疑い(第2分類)などが判定されます。
2の運転技能検査は、75歳以上で、かつ過去3年間に一定の違反(信号無視や速度超過など)歴がある人が対象となります。3は、認知症(第1分類)と判定された場合は免許取消し(または停止)となりますが、軽度認知障害(MCI)の段階では、取消しの対象とはなりません。4は、認知症と診断された場合はサポートカー限定であっても運転は許可されません。5の運転経歴証明書は、免許取消し(違反による)の後ではなく、免許の「自主返納」や「更新せず失効」した場合に交付されるのが基本です。
問題40
認知症(dementia)の行動・心理症状(BPSD)であるアパシー(apathy)に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 感情の起伏がみられない。
- 2 将来に希望がもてない。
- 3 気持ちが落ち込む。
- 4 理想どおりにいかず悩む。
- 5 自分を責める。
答え:1
解説:
アパシー(Apathy)は「無関心」「無気力」「意欲低下」と訳され、認知症の症状(BPSD)の一つです。周囲の出来事や以前は好きだった趣味などに対して無関心になり、喜んだり怒ったりといった「感情の起伏(表出)がみられない」状態を指します。
2(絶望)、3(抑うつ)、5(自責感)は、アパシーよりも「うつ状態」によくみられる症状です。
問題41
認知症(dementia)の人にみられる,せん妄に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 ゆっくりと発症する。
- 2 意識は清明である。
- 3 注意機能は保たれる。
- 4 体調の変化が誘因になる。
- 5 日中に多くみられる。
答え:4
解説:
せん妄は、意識混濁に幻覚や興奮などを伴う状態です。認知症の人は、感染症(発熱)、脱水、便秘、薬剤の影響、環境の変化(入院)といった「体調の変化」や環境のストレスが誘因(引き金)となって、せん妄を発症しやすいです。
1は間違いです。せん妄は「急性(急に)」発症します。2は間違いです。意識レベルが低下(意識混濁)するのが特徴です。3は間違いです。注意機能の低下(ぼんやりする、集中できない)が中核的な症状です。5は間違いです。夕方から夜間(夜間せん妄)に症状が悪化しやすい特徴があります。
問題42
レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)にみられる歩行障害として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 しばらく歩くと足に痛みを感じて,休みながら歩く。
- 2 最初の一歩が踏み出しにくく,小刻みに歩く。
- 3 動きがぎこちなく,酔っぱらったように歩く。
- 4 下肢は伸展し,つま先を引きずるように歩く。
- 5 歩くごとに骨盤が傾き,腰を左右に振って歩く。
答え:2
解説:
レビー小体型認知症は、パーキンソン病と似た症状(パーキンソニズム)が出現するのが特徴です。歩行障害としては、パーキンソン病と同様に、「最初の一歩が踏み出しにくい(すくみ足)」、歩幅が狭くなる「小刻み歩行」、止まれなくなる「突進歩行」などがみられます。
1は腰部脊柱管狭窄症などの間欠性跛行、3は小脳失調による失調性歩行、4は脳梗塞後遺症などの痙性歩行、5は筋力低下などによる動揺性歩行(アヒル歩行)の説明です。
問題43
次の記述のうち,若年性認知症(dementia with early onset)の特徴として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 高齢の認知症(dementia)に比べて,症状の進行速度は緩やかなことが多い。
- 2 男性よりも女性の発症者が多い。
- 3 50 歳代よりも30歳代の有病率が高い。
- 4 特定健康診査で発見されることが多い。
- 5 高齢の認知症(dementia)に比べて,就労支援が必要になることが多い。
答え:5
解説:
若年性認知症は、65歳未満(現役世代)で発症するため、本人の就労(仕事を続けられるか、休職・退職の手続き)や、それに伴う経済的な問題(収入減、住宅ローンなど)への支援が、高齢の認知症の方と比べて、より重要かつ差し迫った課題となることが多いです。
1は逆で、進行速度が速い場合が多いとされています。2は逆で、やや男性に多いと報告されています。3は逆で、有病率は年齢が上がるほど高くなります。4は特定健康診査(メタボ健診)で発見されることはまれです。
問題44
Lさん(78歳,女性,要介護1)は,3年前にアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)と診断された。訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用し,夫の介護を受けながら二人で暮らしている。ある日,訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問すると夫から,「用事で外出しようとすると『外で女性に会っている』と言って興奮することが増えて困っている」と相談を受けた。
Lさんの症状に該当するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 誤認
- 2 観念失行
- 3 嫉妬妄想
- 4 視覚失認
- 5 幻視
答え:3
解説:
Lさんの「『外で女性に会っている』と言って興奮する」という症状は、夫が浮気をしているという事実に基づかない確信を持つ「嫉妬妄想」の典型例です。これは認知症のBPSD(行動・心理症状)の一つであり、記憶障害や不安感などを背景に生じることがあります。
1(誤認:人を間違えるなど)よりも、3(嫉妬妄想)の方がより具体的な症状を指しており適切です。2(道具が使えない)、4(物が認識できない)、5(ないものが見える)は、事例の内容とは異なります。
問題45
認知機能障害による生活への影響に関する記述として,最も適切なものを 1つ選びなさい。
- 1 遂行機能障害により,自宅がわからない。
- 2 記憶障害により,出された食事を食べない。
- 3 相貌失認により,目の前の家族がわからない。
- 4 視空間認知障害により,今日の日付がわからない。
- 5 病識低下により,うつ状態になりやすい。
答え:3
解説:
相貌失認(そうぼうしつにん)は、失認(視覚失認)の一種で、目や鼻などのパーツは認識できても、顔全体を「知っている人の顔」として認識できなくなる症状です。重度になると、毎日会っている家族の顔がわからなくなることがあります。
1の「自宅がわからない」は、見当識障害(場所)です。2の「食事を食べない」は、食物失認(食べ物と認識できない)やアパシー(意欲低下)などが考えられます。4の「日付がわからない」は、見当識障害(時間)です。5は逆で、病識(病気の自覚)がないことで、不安や抑うつが軽減されている場合もあります。
問題46
バリデーション(validation)に基づく,認知症(dementia)の人の動きや感情に合わせるコミュニケーション技法として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 センタリング(centering)
- 2 リフレージング(rephrasing)
- 3 レミニシング(reminiscing)
- 4 ミラーリング(mirroring)
- 5 カリブレーション(calibration)
答え:4.5
解説:
バリデーションは、認知症の人の言動を(たとえ非現実的でも)否定せず、その背景にある感情に寄り添う技法です。「ミラーリング」は、その技法の一つで、相手の姿勢、表情、声のトーン、呼吸リズムなどを鏡(ミラー)のように合わせることを指します。これにより、非言語的に「あなたに寄り添っています」というメッセージを伝え、安心感やラポール(信頼関係)を築きます。
認知症の人の動きや感情に合わせると技法と言う記載から、共感の意味である選択肢5も正解です。
1(センタリング)は介護者自身が心を落ち着かせる技法。2(リフレージング)は相手の言葉を繰り返す技法。3(レミニシング)は回想法のこと。
問題47
Mさん(80歳,女性,要介護1)は,アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)であり, 3 日前に認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居した。主治医から向精神薬が処方されている。居室では穏やかに過ごしていた。夕食後,表情が険しくなり,「こんなところにはいられません。私は家に帰ります」と大声を上げ,ほかの利用者にも,「あなたも一緒に帰りましょう」と声をかけて皆が落ち着かなくなることがあった。
Mさんの介護を検討するときに優先することとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 Mさんが訴えている内容
- 2 Mさんの日中の過ごし方
- 3 ほかの利用者が落ち着かなくなったこと
- 4 対応に困ったこと
- 5 薬が効かなかったこと
答え:1
解説:
Mさんは入居直後であり、夕方(夕暮れ症候群)に強い不安を感じています。このBPSDに対応する際、最も優先すべきは、Mさんが発した「家に帰ります」という「訴えている内容(言葉)」の背景にある感情(不安、混乱、居場所のなさ)を理解しようとすることです。「なぜ家に帰りたいのか」「Mさんにとっての家とは何か」をアセスメントすることが、ケアの第一歩となります。
2(日中の過ごし方)もアセスメントに重要ですが、まずは本人の訴えの分析が優先です。3(他の利用者)や4(スタッフの困惑)は、MさんのBPSDの結果生じたことであり、Mさん本人のケアを検討する上での優先事項ではありません。5は薬効の判断より、まず環境要因や心理的要因を検討すべきです。
問題48
Aさん(80歳,男性,要介護1)は,認知症(dementia)で,妻の介護を受けながら二人で暮らしている。「夫は昼夜逆転がある。在宅介護を続けたいが,私が体調を崩し数日間の入院が必要になった」と言う妻に提案する,Aさんへの介護サービスとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)
- 2 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 3 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 4 特定施設入居者生活介護
- 5 介護老人福祉施設
答え:2
解説:
妻が「数日間の入院」が必要となり、その間の介護者が不在になるため、Aさんに一時的に宿泊(24時間体制)で介護サービスを提供する必要があります。このニーズに合致するのが「短期入所生活介護(ショートステイ)」です。これは、介護者の疾病や休養(レスパイト)のために利用されます。
1は「通所(日帰り)」サービスのため、入院中の夜間対応ができません。3、4、5は、恒久的に「入所(入居)」する居住系サービスであり、一時的な利用を目的とするショートステイとは異なります。
障害の理解
問題49
次のうち,ノーマライゼーション(normalization)の原理を盛り込んだ法律(いわいわゆる「1959年法」)を制定した最初の国として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 デンマーク
- 2 イギリス
- 3 アメリカ
- 4 スウェーデン
- 5 ノルウェー
答え:1
解説:
ノーマライゼーションは、障害のある人が障害のない人と同様の生活を送ることができる社会を目指す理念です。この理念を世界で初めて法律(1959年の知的障害者福祉法、通称「1959年法」)に盛り込んだのはデンマークです。この法律の制定には、ノーマライゼーションの父と呼ばれるバンク-ミケルセンが深く関わりました。
他の国々もノーマライゼーションの理念を取り入れていますが、1959年法を制定したのはデンマークです。
問題50
法定後見制度において,成年後見人等を選任する機関等として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 法務局
- 2 家庭裁判所
- 3 都道府県知事
- 4 市町村長
- 5 福祉事務所
答え:2
解説:
法定後見制度(後見、保佐、補助)は、判断能力が不十分な人を法律的に保護・支援する制度です。この制度の開始(後見開始の審判)や、成年後見人・保佐人・補助人を誰にするかを選任する権限は、本人や家族からの申立てに基づき、「家庭裁判所」が行います。
1の法務局は登記、3(都道府県知事)や4(市町村長)は介護保険や障害福祉サービスの行政機関、5(福祉事務所)は生活保護などの窓口であり、成年後見人等を選任する機関ではありません。
問題51
次の記述のうち,障害を受容した心理的段階にみられる言動として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 障害があるという自覚がない。
- 2 周囲に不満をぶつける。
- 3 自分が悪いと悲観する。
- 4 価値観が転換し始める。
- 5 できることに目を向けて行動する。
答え:5
解説:
障害の受容とは、障害をありのままに受け入れ、その障害とともに生きていこうとする心理状態です。この段階に至ると、利用者は失われた機能(できないこと)にとらわれるのではなく、残された機能(できること)に目を向け、それらを活用して新たな生活を再構築しようと主体的に行動し始めます。
1は「否認」、2は「怒り」、3は「抑うつ」の段階にあたります。4の「価値観の転換」は、受容に至る重要なプロセスですが、5の「実際に行動する」という言動は、受容が成立した後の、より具体的で積極的な段階を示しています。
問題52
統合失調症(schizophrenia)の特徴的な症状として,最も適切なものを1 つ選びなさい。
- 1 振戦せん妄
- 2 妄想
- 3 強迫性障害
- 4 抑うつ気分
- 5 健忘
答え:2
解説:
統合失調症の症状は、幻覚や「妄想」といった陽性症状(本来ないものがあるように感じる)と、意欲の低下や感情の平板化といった陰性症状(本来あるべきものが失われる)などに大別されます。特に「自分は誰かに狙われている」(被害妄想)や「電波で操られている」(作為妄想)といった妄想は、特徴的な症状の一つです。
1(振戦せん妄)はアルコール離脱症状、3(強迫性障害)は不安障害の一種、4(抑うつ気分)はうつ病、5(健忘)は記憶障害であり、それぞれ統合失調症の主症状とは異なります。
問題53
Bさん(60歳,男性)は,一人暮らしをしている。糖尿病性網膜症(diabetic retinopathy)による視覚障害(身体障害者手帳1級)があり,末梢神経障害の症状がでている。Bさんの日常生活において,介護福祉職が留意すべき点として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 水晶体の白濁
- 2 口腔粘膜や外陰部の潰瘍
- 3 振戦や筋固縮
- 4 足先の傷や壊疽などの病変
- 5 感音性の難聴
答え:4
解説:
Bさんは糖尿病の合併症として、網膜症(視覚障害)に加えて「末梢神経障害」があります。末梢神経障害が進行すると、足先の感覚(痛み、熱さ・冷たさ)が鈍くなります。そのため、靴擦れ、やけど、小さな傷などに気づかないまま放置してしまい、そこから細菌が感染して潰瘍や「壊疽」に進行するリスクが非常に高くなります。介護福祉職は、Bさんの足先を日常的に観察し、傷や皮膚の変化の有無に留意する必要があります。
1(水晶体の白濁)は白内障、3(振戦や筋固縮)はパーキンソン病、2(潰瘍)はベーチェット病、5(感音性難聴)は加齢性難聴などの特徴であり、Bさんの病状とは直接関係ありません。
問題54
Cさん(55歳,男性)は,5年前に筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)と診断された。現在は症状が進行して,日常生活動作に介護が必要で,自宅では電動車いすと特殊寝台を使用している。次の記述のうち,Cさんの現在の状態として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 誤嚥せずに食事することが可能である。
- 2 明瞭に話すことができる。
- 3 身体の痛みがわかる。
- 4 自力で痰を排出できる。
- 5 箸を上手に使える。
答え:3
解説:
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、身体を動かす運動神経が障害されますが、感覚神経(痛み、熱さ、触覚など)や知覚、意識は、進行しても末期まで保たれることが一般的です。したがって、Cさんは手足が動きにくくても、「身体の痛み」を感じることはできます。
1、2、4、5はすべて運動機能に関連する動作(嚥下、発語、呼吸筋、手指動作)であり、症状が進行したCさんの状態としては、困難になっている可能性が非常に高いです。
問題55
Dさん(36歳,女性,療育手帳所持)は,一人暮らしをしながら地域の作業所に通っている。身の回りのことはほとんど自分でできるが,お金の計算,特に計画的にお金を使うのが苦手だった。そこで,社会福祉協議会の生活支援員と一緒に銀行へ行って,1週間ごとにお金をおろして生活するようになった。小遣い帳に記録をするようにアドバイスを受けて,お金を計画的に使うことができるようになった。
次のうち,Dさんが活用した支援を実施する事業として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 障害者相談支援事業
- 2 自立生活援助事業
- 3 日常生活自立支援事業
- 4 成年後見制度利用支援事業
- 5 日常生活用具給付等事業
答え:3
解説:
「日常生活自立支援事業」(旧:地域福祉権利擁護事業)は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用援助や、日常的な「金銭管理」(銀行での払い戻し、公共料金の支払いなど)を支援する事業です。主に「社会福祉協議会」が実施しています。Dさんが生活支援員と行った支援は、まさにこの事業の内容です。
1は計画相談、2は一人暮らしの定着支援、4は成年後見制度の利用促進、5は用具の給付であり、Dさんが受けた金銭管理の支援とは異なります。
問題56
次のうち,障害の特性に応じた休憩時間の調整など,柔軟に対応することで障害者の権利を確保する考え方を示すものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 全人間的復権
- 2 合理的配慮
- 3 自立生活運動
- 4 意思決定支援
- 5 共同生活援助
答え:2
解説:
「合理的配慮」とは、障害者差別解消法に定められた考え方で、障害のある人から何らかの支援(社会的障壁の除去)の申し出があった場合に、事業所や行政などが、過度な負担にならない範囲で、柔軟な対応(例:休憩時間の調整、筆談での対応、段差の解消など)を行うことを指します。これにより、障害者の権利(機会の平等)を確保します。
1はリハビリテーションの理念、3は障害者自身の主体性を重視する運動、4は本人の自己決定を支えるプロセス、5はグループホームのことであり、「合理的配慮」の定義とは異なります。
問題57
「障害者総合支援法」において,障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所に置かなければならない専門職として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 2 社会福祉士
- 3 介護福祉士
- 4 民生委員
- 5 相談支援専門員
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
答え:5
解説:
障害者総合支援法において、障害福祉サービスを利用するための「サービス等利用計画」の作成やモニタリングを担う専門職は、「相談支援専門員」です。相談支援専門員は、利用者の意向や状況をアセスメントし、どのようなサービスが必要かを計画にまとめます。
1の介護支援専門員は、介護保険法に基づくケアプランを作成する専門職です。2、3、4は、サービス等利用計画案を作成する事業所への必置専門職ではありません。
問題58
家族の介護力をアセスメントするときの視点に関する記述として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 障害者個人のニーズを重視する。
- 2 家族のニーズを重視する。
- 3 家族構成員の主観の共通部分を重視する。
- 4 家族を構成する個人と家族全体の生活を見る。
- 5 支援者の視点や価値観を基準にする。
答え:4
解説:
家族の介護力(アセスメント)を評価する際は、介護を担う特定の家族員(例えば妻や長女)個人の健康状態、介護技術、心理的負担など(構成する個人)を見るだけでなく、家族全体の経済状況、他の家族員との関係性、協力体制、生活リズムなど(家族全体)を総合的に見ることが重要です。家族を一つのシステムとして捉え、個人と全体の双方の視点を持つ必要があります。
1や2のように、どちらか一方のニーズだけを重視したり、5のように支援者の価値観を基準にしたりするのは、適切なアセスメントとは言えません。
医療的ケア
問題59
次の記述のうち,喀痰吸引等を実施する訪問介護事業所として登録するときに,事業所が行うべき事項として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 登録研修機関になる。
- 2 医師が設置する安全委員会に参加する。
- 3 喀痰吸引等計画書の作成を看護師に依頼する。
- 4 介護支援専門員(ケアマネジャー)の文書による指示を受ける。
- 5 医療関係者との連携体制を確保する。
答え:5
解説:
介護福祉士等が喀痰吸引等を行うためには、事業所は「登録特定行為事業者」として都道府県に登録する必要があります。その登録要件として、医師、看護師等の医療関係者との緊密な「連携体制を確保」し、安全を担保することが定められています。
1の「登録研修機関」は、吸引等の研修を実施する機関であり、サービス提供事業所とは別の登録です。3の計画書は、看護師等が作成しますが、医師の「指示書」に基づいて作成されます。4の指示書は、介護支援専門員ではなく「医師」から受ける必要があります。
問題60
次のうち,呼吸器官の部位の説明に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 鼻腔は,上葉・中葉・下葉に分かれている。
- 2 咽頭は,左右に分岐している。
- 3 喉頭は,食べ物の通り道である。
- 4 気管は,空気の通り道である。
- 5 肺は,腹腔内にある。
答え:4
解説:
気管は、喉頭(のど)と肺(気管支)をつなぐ管状の器官であり、空気が肺へと送られるための主要な「通り道」です。
1は「肺」(右肺)の説明です(鼻腔は鼻甲介で分かれています)。2は「気管」が左右の気管支に分岐する説明です(咽頭は鼻・口と食道・喉頭をつなぐ部分です)。3は「食道」の説明です(喉頭は空気の通り道であり、発声の役割も担います)。5は間違いで、肺は肋骨に囲まれた「胸腔内」にあります。
問題61
次のうち,痰の吸引の準備に関する記述として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 吸引器は,陰圧になることを確認する。
- 2 吸引びんは,滅菌したものを用意する。
- 3 吸引チューブのサイズは,痰の量に応じたものにする。
- 4 洗浄水は,決められた消毒薬を入れておく。
- 5 清浄綿は,次亜塩素酸ナトリウムに浸しておく。
答え:1
解説:
吸引を実施する前には、必ず吸引器の電源を入れ、チューブの先端を指でふさぐなどして、圧力計が医師の指示に基づいた設定値(陰圧)まで上がるかを点検します。正しく陰圧がかからなければ、痰を吸引することはできません。
2の吸引びんは、滅菌までは不要ですが、清潔に洗浄・乾燥させたものを使用します。3のチューブサイズは、痰の量ではなく、利用者の身体(鼻腔の大きさや気管カニューレの内径など)に合わせて選びます。4の洗浄水は、チューブ内を洗浄するためのもので、通常、滅菌水や水道水を使い、消毒薬は入れません。5の次亜塩素酸ナトリウムは、主に環境消毒用であり、皮膚の清拭などには使用しません。
問題62
次のうち,経管栄養で起こるトラブルに関する記述として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 チューブの誤挿入は,下痢を起こす可能性がある。
- 2 注入速度が速いときは,嘔吐を起こす可能性がある。
- 3 注入物の温度の調整不良は,脱水を起こす可能性がある。
- 4 注入物の濃度の間違いは,感染を起こす可能性がある。
- 5 注入中の姿勢の不良は,便秘を起こす可能性がある。
答え:2
解説:
栄養剤の注入速度が速すぎると、胃が急激に引き伸ばされたり、消化が追いつかなかったりするため、胃から食道への逆流が起こりやすくなります。これが「嘔吐」や吐き気の原因となります。
1のチューブの誤挿入(特に肺への挿入)は、下痢ではなく、誤嚥性肺炎という重大な事故につながります。3の温度の調整不良(冷たすぎるなど)は、腹痛や下痢の原因となります。4の濃度の間違い(濃すぎるなど)は、下痢や脱水の原因となります。5の姿勢の不良(仰臥位など)は、逆流や誤嚥の原因となります。
問題63
Eさん(75歳,女性)は,介護老人福祉施設に入所している。脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症があり,介護福祉士が胃ろうによる経管栄養を行っている。ある日,半座位で栄養剤の注入を開始し,半分程度を順調に注入したところで,体調に変わりがないかを聞くと,「少しお腹が張ってきたような気がする」とEさんは答えた。意識レベルや顔色に変化はなく,腹痛や嘔気はない。
次のうち,介護福祉士が看護職員に相談する前に行う対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 嘔吐していないので,そのまま様子をみる。
- 2 仰臥位(背臥位)にする。
- 3 腹部が圧迫されていないかを確認する。
- 4 注入速度を速める。
- 5 栄養剤の注入を終了する。
答え:3
解説:
Eさんの訴えは「少しお腹が張ってきた」という軽度なもので、他に異常はありません。このような場合、注入速度や栄養剤が原因である可能性のほかに、衣服(ズボンのゴムなど)や姿勢によって腹部が圧迫(圧迫)され、膨満感を感じている可能性が考えられます。看護職員に相談する前に、まずは介護福祉士が確認できる外的な要因(衣服のずれや身体のねじれなど)をチェックし、調整するのが適切な最初の対応です。
1は利用者の訴えを無視することになり不適切です。2は仰臥位(平らな)姿勢にすると、栄養剤が逆流しやすくなり危険です。4は症状を悪化させます。5は、明らかな異常がない段階で即座に中止するより、まずは原因の確認が優先されます。
過去の問題はこちら
(令和5年度午前)介護福祉士国家試験 問題・解答・解説 (当ページ)