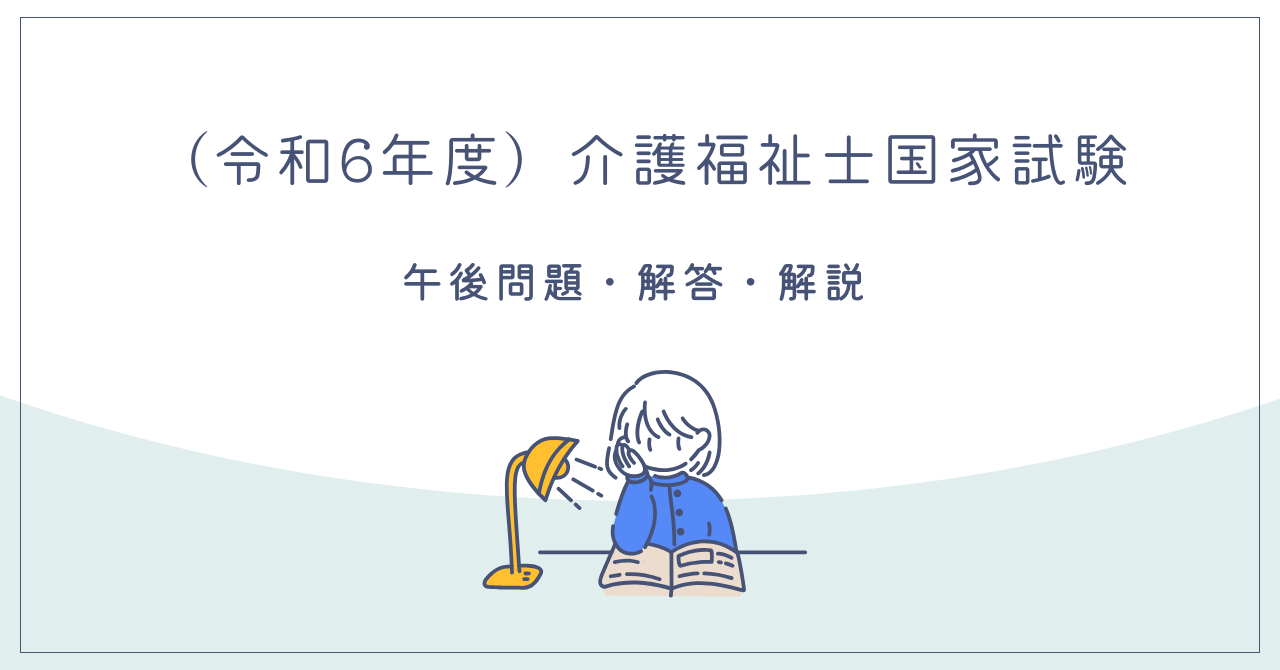介護の基本
問題64
介護福祉に関連する法律に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 「高齢者虐待防止法」は,福祉六法の1つである。
- 2 「障害者総合支援法」は,障害者基本計画の策定を義務づけている。
- 3 社会福祉法によって,社会福祉士の定義が規定されている。
- 4 介護保険法は,国民の共同連帯の理念に基づいて介護保険制度を設けている。
- 5 医師法によって,介護福祉の業務の一部として医行為が認められている。
(注)1 「高齢者虐待防止法」とは,「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
(注)2 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
答え:4
解説:
介護保険法の第1条(目的)には、加齢に伴う心身の変化による要介護状態等となっても、国民の「共同連帯の理念」に基づき介護保険制度を設け、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることが明記されています。
1の福祉六法は、一般に「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「老人福祉法」「母子及び父子並びに寡婦福祉法」を指し、高齢者虐待防止法は含まれません。2の障害者基本計画の策定を定めているのは「障害者基本法」です。3の社会福祉士および介護福祉士の定義は「社会福祉士及び介護福祉士法」に規定されています。5の医師法により、原則として医師以外の医行為は禁止されています(介護福祉士は特定の研修を受けた喀痰吸引等を除く)。
【受験生の皆さんへ】「国民の共同連帯」というフレーズ、暗記だけで済ませていませんか?
なぜこの法律が必要だったのか。それは、かつての「嫁が看るのが当たり前」という過酷な現実を終わらせるためでした。
「家族を救うための法律」という視点で条文を読むと、無機質な言葉に体温が宿ります。
👉 家族の視点で「介護保険法の理念」を読む
問題65
社会福祉士及び介護福祉士法に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 資質向上のために,5年に1回,資格更新研修を受けなければならない。
- 2 社会福祉士の業務を介護福祉士が行うことは禁じられている。
- 3 介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない。
- 4 介護福祉士は,その業を辞した後は秘密保持義務が解除される。
- 5 介護福祉士国家試験に合格した日から,介護福祉士を名乗ることができる。
答え:3
解説:
社会福祉士及び介護福祉士法(第45条)には「信用失墜行為の禁止」が定められており、介護福祉士は専門職としての信用を傷つけるような行為をしてはならないと規定されています。
1の資格更新制度は、介護福祉士には導入されていません(努力義務としての研修はありますが、義務の更新研修はありません)。4の秘密保持義務(第46条)は、業務を辞した後も継続して課されます。5は、国家試験合格後、指定登録機関に「登録」して初めて介護福祉士を名乗ることができます。2は、業務独占資格ではないため、このような禁止規定はありません。
【受験生の皆さんへ】「信用失墜行為」の禁止、イメージできていますか?
なぜ仕事外の行動まで制限されるのか。それは、介護福祉士が利用者の生活の最も深い部分に関わる、高い倫理観が必要な仕事だからです。
「家族が安心して命を預けられる理由」として法律を理解すると、条文の意味がスッと頭に入ります。
👉 家族の視点で「資格の重み」を読む
問題66
Aさん(75歳,女性)は,3か月前に,血管性認知症(vascular dementia)を発症し,軽度の左片麻痺で杖歩行となり,要介護3と認定された。Aさんは,料理が大好きで,娘と一緒に食事を作ることを楽しみに生活していた。1か月前から認知症(dementia)が進行し,ユニット型介護老人福祉施設に入所した。Aさんは夕方になると,「ご飯の支度をしないといけないから帰ります」と言いながら,興奮して歩き回る様子がみられるようになった。
Aさんへの介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 居室に鍵をかけて,自室で過ごしてもらう。
- 2 介護福祉職と一緒に,夕食の準備をしてもらう。
- 3 杖を預かり,低めの丸椅子に座ってもらう。
- 4 介護福祉職の判断で,向精神薬を服用してもらう。
- 5 ここがAさんの自宅であることを,理解してもらう。
答え:2
解説:
Aさんの興奮や帰宅願望は、大好きだった「料理(夕食の支度)」という役割が失われたことによる不安や混乱(BPSD:行動・心理症状)と考えられます。Aさんの「ご飯の支度をしないと」という言葉を否定せず、ユニットのキッチンで「一緒に夕食の準備をしましょう」と誘い、できること(野菜を洗う、食器を並べるなど)をしてもらうことで、Aさんの役割を回復し、不安を和らげることができます。
1と3は身体拘束にあたり不適切です。4は介護福祉職の判断で薬の服用を決めることはできません。5のように「ここが自宅だ」と説得(現実の修正)を試みると、Aさんの混乱や興奮をさらに強めてしまう可能性が高く、不適切です。
【受験生の皆さんへ】「帰宅願望への対応」をパターン暗記していませんか?
正解が「料理」になる理由は、Aさんが「料理が好きだったから」です。
もしAさんが元大工さんだったら?元教師だったら?
マニュアルではなく「その人らしさ(個別性)」に焦点を当てることの重要性を、この事例から学び取りましょう。
👉 家族の視点で「役割ケア」の効果を読む
問題67
ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health: 国際生活機能分類)における「参加」と「活動」の2つが関連した,認知症の人の支援に関する記述として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 若年性アルツheimer型認知症(dementia of the Alzheimer’s type with early onset)があり,治療している。
- 2 認知症カフェに通い,体操をしている。
- 3 近所に住む長男が,買物を代行している。
- 4 自宅にある広い庭を,バリアフリー化している。
- 5 見当識障害があり,GPS装置を身に着けている。
答え:2
解説:
ICFにおいて、「活動」は個人が行う特定の課題や行為(例:「体操をする」)を指し、「参加」は地域社会や生活場面への関わり(例:「認知症カフェに通う」)を指します。選択肢2は、体操という「活動」と、カフェに通うという社会的な「参加」の両方を含んでいます。
1は「健康状態」です。3は「環境因子」(家族の支援)です。4(バリアフリー化)と5(GPS)も「環境因子」(物的・技術的環境)に分類されます。
【受験生の皆さんへ】「活動」と「参加」の違い、説明できますか?
「買い物ができる(活動)」と「主婦として買い物に行く(参加)」。
似ているようで違うこの2つの概念を、認知症の人の「生きがい」や「役割」という視点から整理することで、ICFの全体像がスッキリと理解できます。
👉 家族の視点で「活動と参加」の違いを読む
問題68
次の記述のうち,介護保険制度における訪問介護員(ホームヘルパー)が行うサービス内容として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 利用者が大切にしている庭の植木に,水やりをする。
- 2 利用者が長年飼っている猫のペットフードを,購入してくる。
- 3 掃き掃除をする習慣のある利用者と一緒に,寝室をほうきで掃除する。
- 4 利用者と一緒に,近所のラーメン屋に行く。
- 5 利用者のクレジットカードを預かって,買物を代行する。
答え:3
解説:
訪問介護の「生活援助」として寝室の掃除を行うことは適切です。さらに、利用者の習慣(掃き掃除)を尊重し、残存能力を活用して「一緒に行う」ことは、自立支援の観点からも望ましい対応です。
1(園芸)や2(ペットの世話)、4(外食)は、利用者の日常生活に直接必要な援助とはみなされず、介護保険の算定対象外となります。5は、金銭トラブル防止のため、訪問介護員が利用者のクレジットカードや預金通帳、印鑑などを預かることは原則禁止されています。
【受験生の皆さんへ】「生活援助」の範囲、迷っていませんか?
判断基準は「本人」かつ「日常的」であること。
「ペットの世話」や「来客対応」がなぜ対象外になるのか。制度の目的である「国民の保険料で賄われている」という視点を持つと、ルールの意味がスッキリ理解できます。
👉 家族の視点で「ヘルパー業務の境界線」を読む
問題69
次の記述のうち,介護従事者を守る法制度として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 労働安全衛生法では,年に1回以上の健康診断を行うことを義務づけている。
- 2 労働者災害補償保険法では,労働時間,賃金,休暇などの労働条件を定めている。
- 3 環境基本法では,快適な職場環境の形成の促進を定めている。
- 4 介護休業は,対象家族1名につき,毎年93日間を取得できる。
- 5 出生時育児休業は,子の出生後から8週間取得できる。
答え:1
解説:
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。この法律に基づき、事業者は労働者に対し、年に1回以上(特定業務従事者は6か月に1回)の定期健康診断を実施する義務があります。
2の労働条件(労働時間、賃金など)を定めているのは「労働基準法」です。3の快適な職場環境の形成は「労働安全衛生法」の目的の一つです(環境基本法は公害対策など)。4の介護休業は、対象家族1人につき「通算」93日までであり、毎年ではありません。5の出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に「4週間」まで取得できます。
【受験生の皆さんへ】法律問題を「暗記」だけで乗り切ろうとしていませんか?
なぜ国は健康診断を義務付けたのか。それは、介護現場で働く皆さんが倒れてしまっては、日本の福祉が崩壊するからです。
「自分自身を守るための盾」として法律を捉え直すと、無機質な条文が頼もしい味方に見えてきます。
👉 家族の視点で「働く人を守る法律」を読む
問題70
Bさん(68歳,女性,要介護1)は,ヨーロッパで生まれ育ち,50歳のときに日本人と結婚した。65歳で夫と共に日本で暮らすようになったが,日本語は十分に理解できない。半年前に,脳梗塞(cerebral infarction)を起こし,利き手に麻痺があり,立ち上がりも不安定である。現在は,介護老人保健施設に入所し,在宅復帰へ向けたリハビリテーションを行っている。Bさんはこれまでの生活様式を守り,自宅で自分のペースで食事ができるようになりたいと希望している。
次の記述のうち,Bさんへの介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 入所中は母語を使わずに,日本語を話すように伝える。
- 2 居室の床に布団を敷いて,寝起きができるようにする。
- 3 自分で食事ができるように,自助具の使用状況を確認する。
- 4 ほかの利用者と同じ時間に食べ終えるように伝える。
- 5 日本の生活に合わせるように,余暇活動の内容は介護福祉職が判断する。
答え:3
解説:
Bさんは「利き手麻痺」がありながらも「自宅で自分で食事をしたい」という明確な希望を持っています。この在宅復帰と自立支援の目標を達成するため、利き手が不自由でも食事がしやすくなる自助具(スプーン、フォーク、皿など)の活用を検討し、その使用状況を確認・支援することが最も適切です。
1、2、4、5は、Bさんの文化(母語、ベッド生活)や個別のニーズ(自分のペース)、自己決定権(余暇活動)を無視し、日本の生活様式や施設のペースを一方的に押し付ける不適切な対応です。
【受験生の皆さんへ】「日本語を話すように伝える」がなぜ間違いなのか?
それは、利用者のこれまでの人生(生活歴)やアイデンティティを否定することになるからです。
「個別性(その人らしさ)」を尊重することが、なぜ自立支援につながるのか。具体的なエピソードを通して、ケアの本質を理解しましょう。
👉 家族の視点で「個別ケアの重要性」を読む
問題71
次の記述のうち,チームアプローチに関するものとして,適切なものを1 つ選びなさい。
- 1 介護福祉職が利用者のところに行って,相談,支援を行う。
- 2 障害者が,地域の資源を活用して,共生社会の実現を目指す。
- 3 複数の専門職が共通の目標に向かって協働し,課題解決に取り組む。
- 4 利用者に代わって,専門職がサービスを決定する。
- 5 当事者が集まって体験談を話し,共に支えあう。
答え:3
解説:
チームアプローチ(多職種連携)とは、利用者の複雑なニーズに応えるため、医師、看護師、介護福祉士、リハビリ専門職、ケアマネジャーなど、複数の異なる専門職が、互いの専門性を尊重し、情報を共有しながら「共通の目標」の達成に向かって「協働(連携)」することを指します。
1は個人の業務、2はインクルージョンの理念、4は専門職主導(パターナリズム)、5はセルフヘルプグループ(自助グループ)の説明であり、チームアプローチの定義とは異なります。
【受験生の皆さんへ】「多職種協働」をただの単語として覚えていませんか?
なぜ一人ではなくチームで取り組む必要があるのか。
それは、利用者の生活課題が複雑化しており、一つの専門性だけでは解決できないからです。「家族もチームの一員である」という視点を持つことで、連携の重要性がより深く理解できます。
👉 家族の視点で「チームケアの意義」を読む
問題72
介護保険施設における防災対策に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 介護福祉士は,災害派遣福祉チームで活動することが義務づけられている。
- 2 介護福祉士は,防災スキル向上のために,防災士の資格取得が義務づけられている。
- 3 災害対策基本法に基づき,個別避難計画の作成が施設長に義務づけられている。
- 4 一般的に,飲料水と非常食は1日分の備蓄が義務づけられている。
- 5 災害時等に備えて,業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定が義務づけられている。
答え:5
解説:
2021年度(令和3年度)の介護報酬改定に伴う運営基準の改正により、全ての介護サービス事業者は、感染症や災害が発生した場合でも必要なサービスを継続的に提供できるよう、「業務継続計画(BCP)」を策定することが義務化されました(2024年度から完全義務化)。
1や2は義務ではありません。3の個別避難計画の作成義務は、施設長ではなく「市町村」にあります(施設は協力義務)。4の備蓄は、最低でも「3日分」(可能であれば1週間分)が推奨されており、1日分では不十分です。
【受験生の皆さんへ】「BCP」と「避難計画」の違い、説明できますか?
避難は「逃げること」、BCPは「事業(介護)を続けること」。
なぜ国がこれを義務化したのか。震災やパンデミックの教訓から、「利用者の生活を崩壊させないための最後の砦」としてBCPを理解しましょう。
👉 家族の視点で「BCPの必要性」を読む
問題73
次のうち,結核(tuberculosis)の予防対策に該当するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 便座のアルコール消毒
- 2 肺炎球菌ワクチンの接種
- 3 紫外線を避けた生活
- 4 年に1回の胸部X線検査
- 5 50℃以上の温水によるリネン類の洗濯
答え:4
解説:
結核は、初期症状が風邪と似ており自覚しにくいため、集団感染のリスクがあります。特に介護施設職員など高齢者と接する機会が多い人は、定期的な(年に1回など)胸部X線検査(レントゲン検査)を受けることが、結核の早期発見(二次予防)と感染拡大防止のために重要です。
1の便座消毒は接触感染対策であり、結核(空気感染・飛沫感染)対策にはなりません。2は肺炎球菌の予防ワクチンです(結核のワクチンはBCG)。3の紫外線は結核菌を殺菌する効果があります。5は、結核菌はリネン類を介して感染することはまれです(リネン類の消毒が必要なのは疥癬など)。
【受験生の皆さんへ】「結核=レントゲン」と反射的に選べますか?
なぜ消毒ではなく検査が正解なのか。それは結核が「空気感染」であり、かつ「進行がゆっくり」だからです。
「高齢者の既感染発病」というリスク背景を知ることで、定期検診の重要性がより深く理解できます。
👉 家族の視点で「結核検診」の必要性を読む
コミュニケーション技術
問題74
次の記述のうち,利用者とのコミュニケーションの場面で用いる要約の技法として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 開かれた質問をして,利用者の気持ちを明らかにした。
- 2 共感しながら話を聞き,利用者の気持ちを受け止めた。
- 3 話の途中でうなずき,利用者の気持ちに同意した。
- 4 話の内容を総合的にまとめて返し,利用者の気持ちを整理した。
- 5 自己覚知を図り,利用者との人間関係の形成に努めた。
答え:4
解説:
要約(サマライジング)とは、利用者が話した内容(事実や感情)の要点を、支援者が「総合的にまとめて」整理し、利用者に「返す(伝える)」技法です。これにより、利用者は自分の話が正しく理解されたことを確認でき、自分自身の気持ちや考えを整理することにもつながります。選択肢4は、この要約の定義と目的を正しく説明しています。
1は「開かれた質問」、2は「共感」や「受容」、3は「うなずき」であり、いずれも傾聴の重要な技法ですが「要約」そのものではありません。5の「自己覚知」は、支援者自身が自分を理解することで、専門職としての姿勢の基本です。
【受験生の皆さんへ】「要約」と「受容・共感」の使い分け、できていますか?
ただ聞くだけでなく、あえて「まとめて返す」ことがなぜ必要なのか。
それは、利用者が混乱している時、思考を整理してあげることも支援の一つだからです。家族の会話の悩みをヒントに、技法の目的を深く理解しましょう。
👉 家族の視点で「要約テクニック」の効果を読む
問題75
次の記述のうち,利用者と家族の意向が異なるとき,家族とのコミュニケーションにおいて介護福祉職が留意すべき点として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 家族に支援方針を決めてもらう。
- 2 家族を通して利用者の意向を聴き取る。
- 3 家族と話す機会を別に設ける。
- 4 家族にカウンセリングを行うことを意識する。
- 5 家族を説得する。
答え:3
解説:
利用者と家族の意向が対立する場合、介護福祉職はまず利用者の自己決定を尊重する義務があります。その一方で、家族がなぜ利用者の意向と異なる考えを持つのか、その背景にある心配や思いを傾聴することも極めて重要です。利用者の前では話しにくい本音もあるため、「家族と話す機会を別に設ける」(3)ことで、家族の思いをじっくりと聴き、信頼関係を築きながら、双方にとってより良い支援を模索する基盤を作ることができます。
1や2は、利用者の自己決定権を侵害する不適切な対応です。5のように一方的に説得したり、4のように専門外のカウンセリングを行ったりすることも適切ではありません。
【受験生の皆さんへ】「家族を説得する」がなぜ間違いなのか?
私たちの仕事は、どちらか一方の味方をすることではありません。
板挟みになった時こそ、双方の言い分を「別々に、丁寧に聞く」ことでしか見えてこない解決策があります。現場のリアルな葛藤を想像して、選択肢を選びましょう。
👉 家族の視点で「意見対立時の対応」を読む
問題76
Aさん(80歳,男性,要介護3)は,介護老人福祉施設に入所している。アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)が進行している。ある日の昼食時,介護福祉職がAさんに配膳すると,「お金はこれしかありません。足りますか」と小さくたたまれたティッシュペーパーを渡してきた。
このときのAさんに対する介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 ティッシュペーパーは,口の周りが汚れたら拭くものだと伝える。
- 2 ティッシュペーパーが不足しているサインとして受け止める。
- 3 飲食店での会計の場面であると認識して対応する。
- 4 食事に集中するように促す。
- 5 小遣いの増額を家族に相談する。
答え:3
解説:
Aさんは認知症の症状により、現在いる場所が施設であることを認識できず、過去の経験(外食など)と混同して「飲食店で会計をしている」場面として行動していると考えられます。ティッシュペーパーはAさんにとって「お金」の象徴です。このような場合、否定や訂正(1や4)をするとAさんの混乱や不安を強めてしまいます。Aさんの主観的な現実(飲食店での会計)を受け入れ、その世界観に合わせて対応する「バリデーション(妥当性の確認)」の技法が適切です。「ありがとうございます。ちょうどいただきます」などと、3のように会計の場面として対応するのが正解です。
2や5は、Aさんの行動の背景にある認識を誤って解釈しています。
【受験生の皆さんへ】「ティッシュ=汚れたら拭くもの」と正論を言っていませんか?
選択肢1を選んでしまうと、利用者のプライドを傷つけ、関係悪化を招きます。
なぜAさんはティッシュを渡したのか?その背景にある「社会性」や「義理堅さ」を読み解く力が、適切なケア(選択肢3)を選ぶ鍵になります。
👉 家族の視点で「世界観に合わせるケア」を読む
問題77
構音障害のあるBさんは,現在発語訓練を実施中である。ある日,介護福祉職に対して,「おあんで,あつがおごれた」と訴えた。介護福祉職は,Bさんの発語をうまく聞き取れず,「もう一度,言ってください」と伝えた。Bさんは,自身の発語で会話を続けようとしているが,介護福祉職には,その内容を十分に理解することができなかった。
このときの,Bさんに対する介護福祉職の判断として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 Bさんは言葉の意味の理解に支障があるため,会話の継続は困難である。
- 2 発音が苦手なため,短い言葉でゆっくり話してもらう必要がある。
- 3 話す意欲があるため,開かれた質問が有効である。
- 4 発語訓練の効果がみられないため,訓練を中止する必要がある。
- 5 Bさんの言葉が聞き取れないため,会話を中断する必要がある。
答え:2
解説:
構音障害は、言葉の意味を理解したり言葉を組み立てたりする能力(言語機能)は保たれていますが、ろれつが回らないなど「発音」が不明瞭になる状態です。Bさんは「会話を続けようとしている」ことから、意欲もあり、言語機能にも問題はないと推測されます。したがって、介護福祉職は「Bさんは発音が苦手な状態である」と判断し、Bさんが伝えやすく、介護福祉職が聞き取りやすくなる工夫(例:「短い言葉でゆっくり話してもらう」)が必要であると考えるのが適切です。
1は失語症との混同であり間違いです。3の「開かれた質問」は長い返答が必要になるため、構音障害のある方にはかえって負担になります。4や5はBさんの意欲を著しく損なう不適切な判断です。
【受験生の皆さんへ】「構音障害」と「失語症」の対応、混同していませんか?
構音障害は「発声の運動障害」であり、言語理解や構成能力は保たれています。
だからこそ、「聞き取れないから会話を中断する(選択肢5)」のではなく、「話しやすい方法を提案する(選択肢2)」ことが正解になるのです。
👉 家族の視点で「伝わる会話のコツ」を読む
問題78
Cさん(55歳,男性)は,知的障害がある。3か月前に,施設から居宅での一人暮らしに移行し,現在は,居宅介護(ホームヘルプサービス)を利用しながら生活している。ある日,Cさんが,「ゴミ,分けて捨てるの,難しいよ」と言うので,室内に分別収集の説明書を貼って,カレンダーに収集日を書くことにした。そして,介護福祉職は,「この説明書とカレンダーを見て,捨てるといいですよ」とCさんに伝えた。その後,Cさんは努力していたが,分別できなかったゴミが少しずつ増えていった。
次のうち,Cさんにかける介護福祉職の最初の言葉として,最も適切なものを1 つ選びなさい。
- 1 「ゴミでいっぱいになる前に,適切に捨てられるようになりましょう」
- 2 「説明書とカレンダーをよく見てください」
- 3 「ゴミが増えてきて,気持ち悪いですね」
- 4 「がんばっていれば,上手にできるようになりますよ」
- 5 「ゴミ捨ては難しいですよね。できることをいっしょに考えましょう」
答え:5
解説:
Cさんは「努力していた」にもかかわらず、現在の支援方法(説明書とカレンダー)ではうまく分別できていません。この状況でまず行うべきは、Cさんの「難しい」という気持ちに共感し(ゴミ捨ては難しいですよね)、Cさんの努力を否定せず、Cさんの主体性を尊重しながら、次の解決策を「一緒に考える」という協働的な姿勢を示すことです。5の言葉かけは、この共感と協働の姿勢(エンパワメント)を最もよく表しています。
1や2は、Cさんの努力を無視した指示・命令であり、Cさんを追い詰めてしまいます。3は介護福祉職の主観的な不快感を伝えており不適切です。4は具体的な解決策を示さない単なる励ましであり、問題の解決にはなりません。
【受験生の皆さんへ】「受容」とは、ただ甘やかすことではありません。
Cさんは努力したけれど失敗してしまいました。その挫折感を受け止め、「一人じゃないよ」と伝えることが、次の意欲を引き出します。
「なぜ『頑張ればできる』という励ましが不正解なのか?」その心理的な理由を、家族介護の視点から深く理解しましょう。
👉 家族の視点で「失敗した人への声かけ」を読む
問題79
介護保険サービスにおける記録に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 記録に含まれないものとして食事チェック表がある。
- 2 介護記録は介護福祉職の意見を中心に記録する。
- 3 調査・研究目的で記録を利用することは避ける。
- 4 主観的情報と客観的事実は区別しないで記録する。
- 5 利用者は記録の閲覧を請求することができる。
答え:5
解説:
介護記録は、個人情報保護法の対象となる個人情報です。利用者は、サービス事業者に対し、自身の個人情報(介護記録)について開示(閲覧)を請求する権利を有しています。
1の食事チェック表は、利用者の健康状態を把握する上で非常に重要な記録の一部です。2の介護記録は、介護福祉職の意見(主観)ではなく、利用者の状態や言動、提供したケアといった「客観的事実」を中心に記録します。3は、個人が特定できないよう匿名化するなどの倫理的配慮を行えば、調査・研究目的で利用することは可能です。4は、利用者の訴えなどの「主観的情報(S)」と、観察・測定した「客観的事実(O)」は、明確に区別して記録するのが原則です。
【受験生の皆さんへ】なぜ記録に「主観」を混ぜてはいけないのか?
それは、記録が将来的に「家族に開示される公的な文書」だからです。
家族が読んだ時に「わがままと書かれている」と不快にならないよう、事実を客観的に書く技術が求められます。「誰のために書くのか」を意識して、記録の意義を学びましょう。
👉 家族の視点で「記録開示の重要性」を読む
生活支援技術
問題80
高齢者に配慮した居室環境に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
- 1 夏は高齢者が発汗してから冷房を使用する。
- 2 暖房を使用するときは除湿機を併用する。
- 3 冷房を使用するときは換気を控える。
- 4 温度は介護福祉職の感覚で調整する。
- 5 冬はトイレの温度を居室の温度に近づける。
答え:5
解説:
高齢者は急激な温度変化による血圧変動(ヒートショック)を起こしやすく、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まります。特に冬場は、暖かい居室と寒いトイレとの温度差が大きくなりがちです。そのため、トイレにも小型の暖房器具を置くなどして、温度差を少なくする環境整備は事故予防の観点から非常に重要です。
1は熱中症予防の観点から不適切です。高齢者は体温調節機能が低下しており、「暑さ」を感じにくく、発汗しにくいため、室温や湿度を管理し、発汗する前に冷房を使用します。2は暖房使用時は空気が乾燥するため、除湿機ではなく加湿器を併用します。3は冷房中でも二酸化炭素濃度の上昇などを防ぐため、適度な換気は必要です。4は介護福祉職の感覚ではなく、温度計・湿度計の客観的な数値や、利用者の体感・訴えに基づいて調整します。
【受験生の皆さんへ】「高齢者の感覚で調整する」がなぜ間違いなのか?
高齢者は感覚機能が低下しているため、本人の「暑い・寒い」という感覚だけに頼ると、熱中症や低体温症を見逃すリスクがあるからです。
「客観的な数値(室温)やリスク管理」に基づいた環境整備の重要性を、生活の場面から理解しましょう。
👉 家族の視点で「温度管理の鉄則」を読む
問題81
次の記述のうち,介護の現場において,レクリエーション活動で実施するアイスブレーキングの効果として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 参加者の緊張感を軽減することができる。
- 2 活動内容を毎回固定して実施することができる。
- 3 介護福祉職の負担を軽減することができる。
- 4 利用者の参加を義務づけることができる。
- 5 勝敗を楽しむことができる。
答え:1
解説:
アイスブレーキングは、活動の導入(最初)に行う簡単なゲームや自己紹介などを指します。文字通り「氷(アイス)を壊す(ブレイク)」という意味で、初対面の人や集団の中での参加者の緊張感を軽減し、リラックスした雰囲気を作り、コミュニケーションを促進する効果があります。
2は毎回固定するとマンネリ化します。3は介護福祉職の負担軽減が主目的ではありません。4はレクリエーションは任意参加が原則であり、義務づけるのは不適切です。5は勝敗を競うものではなく、参加しやすくすることが目的です。
【受験生の皆さんへ】レクの目的は「勝敗」ではありません。
なぜアイスブレイクが必要なのか。それは、利用者に「安心して参加してもらうため」です。
「義務付ける(選択肢4)」や「勝敗重視(選択肢5)」がなぜ不適切なのか。「参加者の心の安全」という視点を持つと、正解が自然と浮かび上がります。
👉 家族の視点で「緊張をほぐす技術」を読む
問題82
次の記述のうち,介護福祉職が行う身じたく・整容の介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 ベッド上で行う口腔ケアは,ガーグルベースンを用いる。
- 2 総義歯の洗浄は,歯みがき剤を用いる。
- 3 耳垢の除去は,ピンセットを用いる。
- 4 ベッド上で行う洗顔は,冷水に浸して絞ったタオルを用いる。
- 5 浴室で行う洗髪は,ドライシャンプーを用いる。
答え:1
解説:
ガーグルベースン(腎盂型・そら豆型の容器)は、ベッド上でうがいをする際に、利用者が吐き出した水や痰、洗浄液などを受け止めるために使用するものです。ベッド上での口腔ケアにおいて適切に用いられます。
2の歯みがき剤には研磨剤が含まれているため、総義歯に使用すると表面に傷がつき、細菌が繁殖しやすくなります。義歯専用の洗浄剤やブラシを使用します。3の耳垢除去(特にピンセットなど器具を使う場合)は、耳の内部を傷つける医療行為にあたるため、介護福祉職は原則行いません(耳介の清拭までが範囲です)。4は利用者に不快感を与えるため、温かいタオル(温清拭)を用います。5のドライシャンプーは水を使わない洗髪方法であり、浴室ではなく入浴できない時にベッド上などで使用します。
【受験生の皆さんへ】「義歯洗浄に歯磨き剤」で×を選べましたか?
なぜダメなのか。「研磨剤で傷がつき、細菌が繁殖するから」という根拠までセットで覚えてこそ、現場で使える知識になります。
「利用者の健康を守るためのケア」という視点で、一つ一つの手順の意味を理解しましょう。
👉 家族の視点で「整容ケアのコツ」を読む
問題83
次の記述のうち,障害のある人への事故防止の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 パーキンソン病(Parkinson disease)の人には,低めのベッドを用意する。
- 2 認知症(dementia)の人には,ガスコンロを用意する。
- 3 在宅酸素療法中の人のそばでは,喫煙しない。
- 4 視覚障害のある人には,洗体用に頭受け台を用意する。
- 5 聴覚障害のある人には,補高便座を用意する。
答え:3
解説:
在宅酸素療法で使用する酸素は、それ自体が燃えるわけではありませんが、物が燃えるのを助ける「支燃性」が非常に高いガスです。そのため、たばこやストーブなどの小さな火気でも、引火して火災を引き起こす重大な事故につながります。酸素療法中の利用者のそばでは絶対に喫煙してはいけません。
1のパーキンソン病の人は、すくみ足や立ち上がりの困難さがあるため、低すぎるベッドは逆に立ち上がりが難しくなります。2の認知症の人は、火の消し忘れのリスクが高いため、ガスコンロではなくIHクッキングヒーターなどへの変更が望ましいです。4の頭受け台は洗髪用です。5の補高便座は、膝関節の疾患などで深くかがめない人が使用します。
【受験生の皆さんへ】「パーキンソン病に低床ベッド」がなぜ×なのか説明できますか?
病気の特徴と、それに適した環境整備(福祉用具)の組み合わせは、試験の頻出ポイントです。
すくみ足や立ち上がり困難がある場合、どんなベッドが良いのか?「利用者の動きやすさ」を想像しながら、誤答の理由も深掘りしましょう。
👉 家族の視点で「在宅酸素の事故防止」を読む
問題84
次のうち,右片麻痺の利用者が多点杖を使用して3動作歩行を開始するときに,介護福祉職が行う説明として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 「杖,右足,左足の順で歩きましょう」
- 2 「杖,左足,右足の順で歩きましょう」
- 3 「右足,左足,杖の順で歩きましょう」
- 4 「左足,杖,右足の順で歩きましょう」
- 5 「左足,右足,杖の順で歩きましょう」
答え:1
解説:
片麻痺の利用者が杖を使う場合、杖は麻痺のない「健側」の手(この場合は左手)で持ちます。3動作歩行は、最も安定性が高い歩行方法で、(1)杖(健側で支える)、(2)患側(麻痺のある右足)、(3)健側(麻痺のない左足)の順で一歩ずつ進みます。したがって、1が正しい順序です。
【受験生の皆さんへ】「右麻痺だから…えっと…」と頭の中でシミュレーションしていませんか?
右麻痺なら杖は左手。だから「杖(左)→患側(右)→健側(左)」となる。
丸暗記ではなく、「重心をどこで支えるか」という身体力学の視点でイメージすれば、どんなひっかけ問題も怖くありません。
👉 家族の視点で「安全な歩行手順」を読む
問題85
ノーリフティングケアに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 仰臥位(背臥位)の利用者を抱え上げて,端座位にする。
- 2 仰臥位(背臥位)の利用者を手前に引きよせて,ストレッチャーに移乗する。
- 3 端座位の利用者の体幹を抱きかかえて,車いすに移乗する。
- 4 端座位の利用者にスライディングボードを使用して,車いすに移乗する。
- 5 立位が困難な端座位の利用者に回転移動盤を使用して,車いすに移乗する。
答え:4
解説:
ノーリフティングケアとは、介護者の腰痛予防などのために、利用者を「持ち上げない(リフトしない)」「抱え上げない」介護技術のことです。スライディングボードは、ベッドと車いすの間に渡し、利用者を「滑らせて」移乗させるための福祉用具であり、持ち上げない介護(ノーリフティングケア)の代表的な例です。
1、2、3はすべて、介護者が利用者を「抱え上げ」たり「引きよせ」たりする動作であり、ノーリフティングケアに反します。5の回転移動盤は、足が床につき、立位(またはそれに近い状態)が保持できる人が方向転換のために使用するもので、立位が困難な人には使用できません。
【受験生の皆さんへ】「抱え上げる」という言葉に違和感を持てましたか?
選択肢1や3にある「抱え上げて」は、現代の介護技術としては不適切(NGワード)です。
なぜなら、それが腰痛の元凶だからです。「利用者と介護者、双方を守るケア」という視点を持てば、自然と「スライディングボード(選択肢4)」が選べるようになります。
👉 家族の視点で「ノーリフティング」のメリットを読む
問題86
次の記述のうち,左片麻痺の利用者を右側臥位から端座位にするときの介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 利用者に左手でベッド柵をつかむように伝える。
- 2 利用者に右肘を支点にして上体を起こしてもらう。
- 3 利用者の右脚をベッドから下ろす。
- 4 利用者の頸部を支えて上体を起こす。
- 5 端座位の利用者の右側に立って上体を支える。
答え:2
解説:
左片麻痺の利用者にとって、右側は「健側」です。右側臥位(健側が上)から起き上がる際は、動かすことができる右腕(健側)の肘をベッドにつき、そこを支点にしてベッド面を押しながら上体を起こしてもらうのが、本人の残存能力を最も活かした自然な起き上がり方(体幹の回旋運動)となります。
1の左手(患側)ではベッド柵を掴めません。3の右脚(健側)は、上体を起こす力として使うため、先にベッドから下ろしません(先に下ろすのは患側の左脚です)。4は頸部だけを支えて起こすのは危険であり、肩甲骨と膝窩(膝の裏)などを支えます。5は端座位になった後は、不安定な「患側」(左側)に立って上体を支えます。
【受験生の皆さんへ】「頸部を支えて起こす」がなぜ間違いか、説明できますか?
首を支点にすると、頚椎に負担がかかり危険だからです。
なぜ「肘」なのか。それは、利用者が自分の力を使える唯一の支点だからです。「自立支援」と「安全」の両面から、介助方法の根拠を理解しましょう。
👉 家族の視点で「起き上がり介助のコツ」を読む
問題87
口腔ケアに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 うがいは,顔貌を整える。
- 2 歯みがきは,感染予防になる。
- 3 口腔内の乾燥は,口臭を予防する。
- 4 唾液腺マッサージは,唾液の分泌を抑える。
- 5 咀嚼機能の向上のために,タッピングを行う。
答え:2
解説:
口腔内を歯みがきで清潔に保つことは、虫歯や歯周病の予防だけでなく、口腔内の細菌が唾液や食物と共に気管に入って引き起こされる「誤嚥性肺炎」という重大な感染症の予防に直結します。
1のうがいは、口腔内の洗浄や湿潤が目的です。3の口腔内の乾燥は、唾液の自浄作用を低下させ、細菌が繁殖しやすくなるため、口臭の「原因」となります。4の唾液腺マッサージは、唾液の分泌を「促進」するために行います。5のタッピング(筋肉を軽く叩く刺激)は、主に嚥下機能(嚥下反射の誘発など)の向上や麻痺の改善のために行われます。
【受験生の皆さんへ】「口腔ケアの効果」を丸暗記していませんか?
なぜ歯磨きが感染予防になるのか。それは「誤嚥性肺炎」や「ウイルス感染」のリスクを下げるからです。
現場で「命を守るケア」として口腔ケアを実践するために、その根拠を生活者の視点から深く理解しておきましょう。
👉 家族の視点で「口腔ケアの重要性」を読む
問題88
次の記述のうち,口腔ケアを実施するときの留意点として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 実施中は,利用者に顎を上げた姿勢をとってもらう。
- 2 総義歯は,上顎から下顎の順に外してもらう。
- 3 歯みがきの前に,うがいを行ってもらう。
- 4 歯ブラシは,大きく動かして磨いてもらう。
- 5 舌ブラシは,舌先から咽頭に向かって動かしてもらう。
答え:3
解説:
歯みがき(ブラッシング)を開始する前に、まずうがいをしてもらうことで、口腔内に残っている大きな食べかすなどを洗い流すことができます。これにより、その後のブラッシングが効率的かつ効果的に行え、汚れを奥に押し込むことも防げます。
1は間違いです。顎を上げた姿勢(上を向く)は、水分や唾液が気管に流れ込みやすく、誤嚥のリスクが最も高くなります。必ず顎を引いた姿勢(やや下を向く)をとってもらいます。2は逆で、一般的に外しにくい「下顎」から先に外し、入れる時は安定しやすい「上顎」から入れます。4は歯茎を傷つけたり、磨き残しが出たりするため、小刻みに動かします。5は逆で、「奥(咽頭側)から手前(舌先)」に向かって動かし、汚れをかき出します。
【受験生の皆さんへ】「顎を上げた姿勢」がなぜ×なのか、即答できますか?
「見やすいから」という介護者都合の視点ではなく、「利用者が誤嚥しない安全な姿勢(頸部前屈)」という身体構造の視点を持てば、迷うことはありません。
一つ一つの動作の根拠を、現場のリスク管理と結びつけて覚えましょう。
👉 家族の視点で「安全な口腔ケア」の手順を読む
問題89
次の記述のうち,介護が必要な人への熱中症対策のために,介護福祉職が行う水分補給の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 のどが渇いてから,水分を取るように伝える。
- 2 水でむせるときは,ゼリーの提供を控える。
- 3 起床時は,水分摂取を控えるように伝える。
- 4 食事のときの水分は,一日の水分摂取量から除く。
- 5 汗の量が多いときは,塩分を含んだ飲み物を勧める。
答え:5
解説:
熱中症対策において、大量に汗をかいた場合は、水分だけでなく体内の塩分(ナトリウム)も同時に失われています。この状態で水だけを飲むと、かえって体液が薄まり、低ナトリウム血症(水中毒)を引き起こす危険があります。そのため、汗が多い時は、塩分やミネラルも補給できる経口補水液やスポーツドリンクなどを勧めるのが適切です。
1は不適切です。高齢者は「のどの渇き」を感じにくくなっているため、渇きを感じる前に、時間を決めてこまめに水分補給を促す必要があります。2は逆で、水でむせる(誤嚥の兆候)場合は、ゼリー状の水分やとろみをつけた水分が誤嚥予防に有効です。3は不適切です。起床時は睡眠中の発汗で水分が失われているため、コップ1杯程度の水分摂取を勧めるべきです。4は食事中の水分(汁物、お茶など)も一日の摂取量に含めて計算します。
【受験生の皆さんへ】「のどが渇いてから」がなぜ×なのか、説明できますか?
「高齢者は口渇中枢の機能が低下しているため、自覚症状が出にくい」という生理学的な理由を知っているかどうかが、プロと素人の分かれ目です。
「隠れ脱水」のリスクを理解し、予防的なケアの視点を持ちましょう。
👉 家族の視点で「水分補給の難しさ」を読む
問題90
Aさん(75歳,男性)は,1年前に前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)と診断され,現在は,認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居している。若い頃から食べることが好きである。現在,咀嚼や嚥下機能の低下はなく,スプーンを使い,自分で食べている。最近,飲み込む前に次々と食べ物を口に入れることが増えた。
次の記述のうち,Aさんの現在の状態に合わせた食事の介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 取っ手つきのコップを準備する。
- 2 食器に少量ずつ盛りつけて提供する。
- 3 すべての料理をテーブルの上に並べる。
- 4 大きなスプーンに変更する。
- 5 手で持って食べられる物を準備する。
答え:2
解説:
Aさんの「飲み込む前に次々と食べ物を口に入れる」行動(早食い・詰め込み食べ)は、前頭側頭型認知症の特徴的な症状である脱抑制や常同行動と考えられます。嚥下機能自体に問題はなくても、詰め込みによる窒息のリスクが非常に高い状態です。この対策として、一度に口に入れられる量を物理的に制限する(例:小皿に少量ずつ盛りつけて提供し、食べ終わったら次を出す)のが最も適切で安全な対応です。
1はコップの問題ではありません。3は、すべての料理を並べると、かえって詰め込み食べを助長します。4の大きなスプーンは、一度に口に入れる量を増やしてしまい、さらに危険です。5は手づかみ食べを誘発する可能性があり、詰め込みの解決にはなりません。
【受験生の皆さんへ】「前頭側頭型認知症」の特徴、イメージできていますか?
アルツハイマー型とは違い、記憶障害よりも「人格変化」や「脱抑制(本能のまま動く)」が目立つのが特徴です。
Aさんの「次々と口に入れる」行動の原因を理解すれば、なぜ「少量ずつ提供」が正解なのか、論理的に導き出せます。
👉 家族の視点で「詰め込み食べの対策」を読む
問題91
次の記述のうち,パーキンソン病(Parkinson disease)で上肢の震えはあるが,自力摂取が可能な利用者の食事の介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 食事後に口腔内のアイスマッサージを行う。
- 2 片側の縁が高くなっている皿を準備する。
- 3 上半身を後ろに20度程度倒すように伝える。
- 4 食器の置いてある位置を説明する。
- 5 踵を床から浮かすように伝える。
答え:2
解説:
パーキンソン病による上肢の震え(安静時振戦)があると、スプーンなどで食べ物をうまくすくう動作が困難になります。片側の縁が高くなっている皿(自助食器)を使用すると、食べ物が皿の縁に引っかかるため、スプーンですくいやすくなり、自力摂取を支援できます。
1のアイスマッサージは、嚥下反射を誘発するために食事「前」に行います。3は誤嚥予防のため、上半身は前傾姿勢(顎を引く)が基本です。4は視覚障害のある人への対応です。5は踵を床にしっかりつけ、安定した姿勢をとってもらいます。
【受験生の皆さんへ】「パーキンソン病=安静時振戦」だけで終わっていませんか?
重要なのは、その症状が「生活(食事)」にどう影響し、どうすれば解決できるか(自助具の活用)をつなげて考えることです。
「こぼしてしまう利用者の困りごと」を想像しながら、具体的な支援方法を学びましょう。
👉 家族の視点で「自助具の選び方」を読む
問題92
次の記述のうち,入浴の作用を生かした,高齢者への入浴の介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 食事は,入浴直前に摂取する。
- 2 高血圧の人には,42℃以上の湯につかってもらう。
- 3 浴槽の中では,関節運動を促す。
- 4 心疾患(heart disease)のある人には,肩まで湯につかってもらう。
- 5 個浴の浴槽内では,足を浮かせてもらう。
答え:3
解説:
浴槽の中では「浮力」が働き、体重の負担が軽減され、関節にかかる重力が少なくなります。また、水の「抵抗」が適度な負荷となります。この作用(浮力・抵抗作用)を利用して、膝や股関節などの関節運動(リハビリ)を促すことは、入浴の機会を生かした適切な介護です。
1は不適切です。食事直後は消化のために胃腸に血液が集まるため、入浴は避けます(食後1~2時間はあける)。2は不適切です。42℃以上の高温浴は交感神経を刺激し、血圧を急上昇させるため、高血圧の人には危険です(38~40℃の微温浴が適します)。4は不適切です。心疾患のある人は、水圧による心臓への負担を避けるため、肩までつかる全身浴ではなく、半身浴が推奨されます。5は浮力で体が不安定になり危険です。
【受験生の皆さんへ】「心疾患の人は肩まで浸かる」がなぜ×なのか?
それは「静水圧作用」によって心臓への還流血流量が増え、負担がかかりすぎるからです。
「浮力」「静水圧」「温熱」の3つの作用が体にどう影響するか。生活場面に置き換えて理解すれば、丸暗記する必要はありません。
👉 家族の視点で「入浴の効能とリスク」を読む
問題93
次の記述のうち,下肢筋力が低下して介護を必要とする人の入浴に適した環境として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 浴室の入口は開き戸にする。
- 2 床から浴槽の縁までの高さは20cmにする。
- 3 縦に長く,浅めの洋式の浴槽にする。
- 4 浴槽の縁の幅は20cmにする。
- 5 浴槽への出入りのために,水平および垂直の手すりを設置する。
答え:5
解説:
下肢筋力が低下した人にとって、浴槽をまたぐ動作(出入り)は、最も転倒リスクが高い動作の一つです。浴槽の縁をまたぐ際に体を支えるための「水平の手すり」と、浴槽内で立ち座りをするための「垂直の手すり」を適切に組み合わせることで、安全性が大きく向上します。
1は開き戸ではなく、車いすでの出入りや介助スペースの確保がしやすい「引き戸」が望ましいです。2は低すぎます。床からの高さは40~45cm程度が、またぎやすく、浴槽の縁にいったん腰掛ける動作にも適しています。3は洋式(浅く長い)より、肩までつかりやすく立ち座りもしやすい和洋折衷式(深さ・長さが中間)が望ましいです。4は広すぎます。縁に腰掛ける場合、10~15cm程度が適切です。
【受験生の皆さんへ】「浴槽の高さ20cm」がなぜ不適切か、わかりますか?
「またぎやすい」メリットよりも、「立ち上がれない」デメリットの方が大きいからです。
単に数字を覚えるのではなく、「実際の入浴動作でどこに負担がかかるか」をイメージすれば、適切な環境が論理的に選べます。
👉 家族の視点で「お風呂場の安全対策」を読む
問題94
次の記述のうち,体調不良で入浴できない片麻痺の利用者に対して,ベッド上で行う全身清拭の方法として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 清拭時は,窓を開けて行う。
- 2 洗面器には,40℃程度のお湯を準備する。
- 3 最初に,腹部から清拭する。
- 4 背部は,患側を下にした側臥位にして拭く。
- 5 蒸しタオルで拭いた後は,乾いたタオルで水分を拭き取る。
答え:5
解説:
蒸しタオル(温清拭)で拭いた後、皮膚に水分が残っていると、それが蒸発する際(気化熱)に体温を奪い、湯冷め(不快感や寒気)の原因となります。そのため、拭いた箇所はすぐに乾いたタオルで水分を拭き取り、保温することが重要です。
1は不適切です。湯冷め防止のため、窓は閉め、室温を22~24℃程度に保ちます。2は不適切です。タオルを絞る際に火傷のリスクがあり、タオルもすぐに冷めてしまいます。一般的に50~60℃程度のお湯でタオルを濡らし、固く絞ります。3は不適切です。清拭は、原則として末梢(手足の先)から中枢(心臓)に向かって拭きます(静脈血の還流を促すため)。4は不適切です。片麻痺の利用者の場合、体位が安定しやすい「健側」を下にした側臥位をとってもらいます。
【受験生の皆さんへ】「窓を開けて換気」がなぜ間違いなのか?
普段の掃除なら正解ですが、清拭の場面では「保温」が最優先されるからです。
「気化熱のリスク」を理解していれば、室温管理やお湯の温度設定など、清拭に関するあらゆる問題に対応できるようになります。
👉 家族の視点で「清拭のポイント」を読む
問題95
次のうち,同居の高齢者におむつを使用する家族介護者に対する,介護福祉職の説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 「使用する本人の羞恥心に気を配りましょう」
- 2 「尿失禁を防ぐことができます」
- 3 「尿量を気にせずに,1日中同じおむつを使うことができます」
- 4 「おむつを着けると,安心して排泄ができます」
- 5 「家族の都合に合わせて,おむつを使いましょう」
答え:1
解説:
おむつの使用は、本人にとって「排泄が自立できなくなった」という認識につながり、羞恥心や自尊心の低下を招く可能性があります。介護者は、その気持ちに最大限配慮し、尊厳を守る(人前で交換しない、おむつと呼ばない、「あてもの」と呼ぶなど)ことが最も重要であると説明すべきです。
2はおむつは失禁を「受ける」ものであり、「防ぐ」ものではありません。3は濡れたまま長時間放置すると、皮膚トラブル(おむつかぶれ)や不快感、感染の原因になります。4は「おむつを着ければ安心」ではなく、できるだけトイレでの排泄を目指し、おむつは最終手段(または夜間のみなど限定的)と考えるのが基本です。5は家族の都合(介護者の都合)ではなく、本人の排泄リズムや皮膚の状態に合わせて交換するのが原則です。
【受験生の皆さんへ】「家族の都合に合わせて」がなぜ×なのか?
介護は効率も大切ですが、それ以上に「尊厳の保持」が優先されます。
おむつを勧められた時の高齢者のショックや葛藤を想像すれば、選択肢1以外は選べないはずです。現場で求められる「心のケア」の視点を養いましょう。
👉 家族の視点で「おむつ導入の心理」を読む
問題96
次の記述のうち,ポータブルトイレを使用するときの排泄の介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 ポータブルトイレの下に新聞紙を敷く。
- 2 ベッドで臥床している状態で,ズボンや下着をおろす。
- 3 ポータブルトイレには,前かがみになって座ってもらう。
- 4 排泄が終わるまで,ポータブルトイレの後ろに立って待つ。
- 5 排泄後の陰部の清拭は,ベッドの上で行う。
答え:3
解説:
ポータブルトイレに座る際、足が床にしっかりとつき、やや前かがみ(前傾姿勢)になることは、排便を促すために最も適した姿勢です。この姿勢は、直腸と肛門の角度を緩やかにし、腹圧をかけやすくするため、生理的に排便しやすい状態を作ります。介護福祉職は、利用者の安全(バランス)に配慮しながら、この姿勢がとれるように支援します。
1の新聞紙を敷くことも汚染防止のために適切な「準備」ですが、排泄「そのもの」を支援する介護としては、3の姿勢の工夫がより適切です。2や4は利用者の羞恥心への配慮に欠けるため不適切です。5はベッドを汚染するリスクがあり、ポータブルトイレに座ったまま安定した状態で行う方が適切です。
【受験生の皆さんへ】「後ろに立って待つ」がなぜ不適切か、わかりますか?
排泄ケアで大切なのは、身体的な介助だけでなく「心理的な安全性(羞恥心への配慮)」です。
「見られていたら出ない」という当たり前の感覚を大切にすることで、正しいケアの選択肢が見えてきます。
👉 家族の視点で「排泄しやすい環境」を読む
問題97
次の記述のうち,介護福祉職が行うことのできる,坐薬(座薬)を用いた介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 膣から挿入する坐薬(座薬)が扱える。
- 2 坐薬(座薬)は,あたたかな場所で保管する。
- 3 坐薬(座薬)は,とがっていない方から挿入する。
- 4 腹部に力を入れるよう促しながら,坐薬(座薬)を挿入する。
- 5 下剤以外の坐薬挿入は,先に排泄を済ませてから行う。
答え:5
解説:
下剤(便を出すため)以外の坐薬(解熱剤、鎮痛剤、吐き気止めなど)は、挿入後に排便してしまうと、薬剤が効果を発揮する前に便と一緒に排出されてしまいます。そのため、薬剤の効果を確実に得るために、先にトイレを済ませて(排泄後)から挿入するのが原則です。
1は間違いです。介護福祉職が扱えるのは、医行為に該当しない「肛門」から挿入する坐薬(緩下剤など)の介助のみです。膣坐薬の挿入は医療行為です。2は間違いです。坐薬は体温で溶けるよう作られているため、冷所(冷蔵庫など)で保管します。3は間違いです。とがっている方(先端)から挿入します。4は間違いです。腹部に力を入れる(いきむ)と坐薬が出てきてしまうため、リラックスして腹部の力を抜いてもらいます。
【受験生の皆さんへ】「腹部に力を入れる」がなぜ間違いか、わかりますか?
お腹に力が入ると(腹圧がかかると)、肛門が締まり、座薬が入りにくくなるだけでなく、飛び出しやすくなるからです。
「どうすれば利用者が苦痛なく挿入できるか」という身体の仕組みに基づいたケアを理解しましょう。
👉 家族の視点で「座薬挿入のコツ」を読む
問題98
次の記述のうち,調理における基本調味料の効果や使い方として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 砂糖は,塩より先に入れると,食物に甘みが浸透しやすくなる。
- 2 塩は,食物のうま味を増し,照りを出す。
- 3 酢は,食物の水分を引き出し,保存性を高める。
- 4 しょうゆは,食物のくさみを抜き,肉を柔らかくする。
- 5 みそは,味付けの最初に入れると,特有の香りが逃げない。
答え:1
解説:
調味料を入れる順序「さしすせそ」(砂糖、塩、酢、醤油、味噌)は、味の浸透しやすさに基づいています。砂糖(分子量が大きい)は、塩(分子量が小さい)より先に入れないと、塩の脱水作用・浸透圧によって食材が締まってしまい、甘みが浸透しにくくなります。よって、砂糖を先に入れるのが基本です。
2の照りを出すのは、砂糖やみりんです。3の水分を引き出し保存性を高めるのは、塩や砂糖です(浸透圧)。4のくさみを抜き肉を柔らかくするのは、酒や酢、生姜などの効果です。5のみそは、風味が飛びやすいため、火を止める直前など、調理の最後に入れるのが基本です。
【受験生の皆さんへ】「さしすせそ」を単なる順序として暗記していませんか?
「なぜ砂糖が先なのか(浸透圧・分子量)」「なぜ味噌は最後なのか(風味)」。
その理由を理解することは、高齢者の「減塩対策」や「食欲増進」の支援を考える上で、現場で必ず役立つ知識になります。
👉 家族の視点で「調味料の効果」を読む
問題99
食品の保存に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 賞味期限の切れた未開封の缶詰は,すぐに廃棄する。
- 2 ウインナーには,消費期限が記載されている。
- 3 前日調理して常温保存した肉入りカレーは,再加熱する。
- 4 りんごを冷蔵庫で保存するときは,ビニール袋に入れて密封する。
- 5 冷凍食品は,一度解凍しても再冷凍すれば長期間の保存が可能である。
答え:4
解説:
りんごは、冷蔵庫内でそのまま保存すると水分が蒸発して鮮度が落ちやすくなります。また、熟成を促すエチレンガスを発生させるため、他の野菜や果物の熟成を早めてしまう可能性があります。そのため、ビニール袋に入れて密封(または軽く口を閉じる)ことは、水分の蒸発を防いで鮮度を保ち、かつエチレンガスの影響を他の食品に及ぼさないための適切な保存方法です。
1の「賞味期限」は「美味しく食べられる期限」であり、期限が切れてもすぐに食べられなくなるわけではないため、廃棄は必須ではありません。2のウインナーは、冷蔵品など急速に劣化しやすいものは「消費期限」ですが、常温保存可能な製品などでは「賞味期限」が記載される場合もあり、必ずしも消費期限とは限りません。3は危険です。常温保存した肉入りカレーは、ウェルシュ菌などの食中毒菌が増殖している危険性が高く、廃棄すべきです。5は不適切です。一度解凍した食品は、品質が著しく低下し、細菌も増殖しやすいため、再冷凍してはいけません。
【受験生の皆さんへ】「カレーの常温保存」がなぜ×なのか説明できますか?
再加熱すればOKと思いがちですが、「ウェルシュ菌」のリスクを知っていれば、それが不適切な対応だとわかります。
ただの暗記ではなく、「なぜその保存方法が危険なのか?」という衛生管理の視点を持つことが、現場での事故防止につながります。
👉 家族の視点で「食品保存の落とし穴」を読む
問題100
次の記述のうち,衣類の保管方法として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 衣装ケースで保管するときは,たたんだ衣類の下に防虫剤を入れる。
- 2 ドライクリーニング後の衣類は,ビニールを外さずに保管する。
- 3 汚れのひどい衣類は,介護福祉職の判断で廃棄する。
- 4 湿気を含んだ衣類は,たたんで引き出しに保管する。
- 5 絹製品は,タンスの上部に保管する。
答え:5
解説:
絹(シルク)製品は、シワになりやすく、デリケートな素材です。タンスに保管する際は、重い衣類(綿やウールなど)の下に置くと、シワや型崩れの原因になります。そのため、タンスの上部(一番上)にふんわりと保管するのが適切です。
1は間違いです。防虫剤の成分は空気より重いため、衣類の「上」に置かないと効果が全体に行き渡りません。2は間違いです。クリーニングのビニールは通気性が悪く、湿気がこもりカビの原因になるため、必ず外してから保管します。3は不適切です。介護福祉職が利用者の所有物を勝手に判断して廃棄してはいけません。4は不適切です。湿気を含んだまま保管すると、カビや虫食いの原因になります。
【受験生の皆さんへ】「防虫剤は下に置く」がなぜ×なのか説明できますか?
「防虫成分のガスは空気より重い」。この物理法則を知っていれば、迷うことなく「上」を選べます。
丸暗記ではなく、「なぜそうするのか(根拠)」を生活の場面とリンクさせて覚えることで、確実な知識として定着します。
👉 家族の視点で「衣類保管のルール」を読む
問題101
次の記述のうち,介護の現場で行うベッドメイキングとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 居室の窓は,閉めて行う。
- 2 キャスターのあるベッドは,ストッパーを外す。
- 3 シーツの中心線を,マットレスの端に合わせる。
- 4 シーツをマットレスの下に入れるときは,手掌を下にする。
- 5 シーツ交換は,両膝を伸ばしたままで行う。
答え:4
解説:
ベッドメイキングにおいて、シーツをマットレスの下に差し込む際、手掌(手のひら)を下に向け、手の甲を上にした状態で滑り込ませるのが正しい技術です。この方法は、指をマットレスとベッドフレームの間に挟んで怪我をすることを防ぐための、安全なボディメカニクスに基づいています。
1は、埃の飛散防止や室温維持のために窓を閉めることもありますが、清掃時の「換気」のために窓を開けることも重要であり、状況によります。4の安全技術の方がより優先されます。2はベッドが動くと危険なため、ストッパーは「かけて」固定します。3はシーツの中心線をマットレスの「中心線」に合わせます。5は腰痛の原因となるため、膝を曲げて腰を落として作業します。
【受験生の皆さんへ】「膝を伸ばしたまま」がなぜ×なのか、身体感覚でわかりますか?
それは腰痛の元凶だからです。
ベッドメイキングの問題は、単なる手順の暗記ではなく「ボディメカニクス(身体の使い方の技術)」と「安全管理」の視点で解くことが重要です。
👉 家族の視点で「シーツ交換のコツ」を読む
問題102
Bさん(90歳,女性,要介護3)は,アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)があり,介護老人福祉施設に入所している。テレビを見ることが好きで,日中はお茶を飲みながら,テレビを見て過ごすことが日課である。 1 週間前からBさんは,夜中に目が覚めたり,3時ごろに起きたりと,不眠が続いている。2時間ほどしか寝ていない日もある。ある日,Bさんは,「昼間,眠くてしかたがない。からだがだるい」と介護福祉職に話した。
次の記述のうち,Bさんに安眠を促すための介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 午前中,太陽の光を浴びることを勧める。
- 2 昼間眠いときは,1時間以上の昼寝を勧める。
- 3 夕食後,すぐに寝ることを勧める。
- 4 寝る前に,介護福祉職の判断で睡眠薬を勧める。
- 5 夜眠れないときは,居室でテレビを見ることを勧める。
答え:1
解説:
Bさんの不眠(中途覚醒、早朝覚醒)と日中の眠気は、日中の活動不足や体内リズム(サーカディアンリズム)の乱れが原因と考えられます。午前中に太陽の光を浴びる(日光浴)ことは、体内時計をリセットし、夜間の良質な睡眠を促すホルモン(メラトニン)の分泌を整えるのに非常に効果的です。日中のテレビ視聴(座位)だけでなく、散歩などで光を浴びる活動を勧めるのが最も適切です。
2は不適切です。1時間以上の長い昼寝は、夜間の睡眠をさらに妨げるため逆効果です(昼寝は15~30分以内が望ましい)。3は食後すぐの就寝は消化に悪く、逆流性食道炎などの原因にもなります。4は介護福祉職の判断で薬を勧めることはできません(医師の指示が必要です)。5はテレビの光(ブルーライト)が脳を覚醒させるため、夜眠れない時の対応として不適切です。
【受験生の皆さんへ】「不眠=睡眠薬」と安易に考えていませんか?
介護の基本は「薬を使わないケア」の検討から始まります。
Bさんの生活リズム(日中の過ごし方)に着目し、「体内時計をどうリセットするか」という生理学的な視点を持てば、選択肢1が輝いて見えるはずです。
👉 家族の視点で「光と睡眠」の関係を読む
問題103
終末期の介護に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 決まった時間に食事を提供する。
- 2 部屋の換気は控えるようにする。
- 3 無反応のときは無言で静かに介護を行う。
- 4 呼吸困難時は,顎を下げて頭部を前屈させた仰臥位(背臥位)にする。
- 5 せん妄によって話のつじつまが合わないときは,否定せずに受け止める。
答え:5
解説:
終末期には、身体的な苦痛や環境の変化、薬剤の影響などで、せん妄(意識混濁による混乱や幻覚・妄想)が起こりやすくなります。このとき、本人の話のつじつまが合わなくても、それを否定したり訂正したりすると、本人の不安や混乱を強めてしまいます。まずは否定せずに受け止め、安心感を持ってもらえるように寄り添うことが重要です。
1は不適切です。決まった時間ではなく、本人が望むとき(食べられるとき)に、望むもの(食べられるもの)を少量ずつ提供します。2は不適切です。息苦しさを感じることが多いため、新鮮な空気を取り入れる適度な換気は必要です。3は不適切です。無反応に見えても聴覚は最後まで残ると言われているため、無言ではなく、穏やかに声かけ(「お体を拭きますね」など)をしながら介護を行います。4は不適切です。呼吸困難時は、上体を起こした姿勢(ファウラー位やセミファウラー位)が最も楽です。顎を下げて前屈させると気道が狭くなります。
【受験生の皆さんへ】「無反応のときは無言で」がなぜ間違いなのか?
「どうせ聞こえていない」というのは介護者側の勝手な思い込みです。
聴覚は最期まで残る機能です。「返事がなくても、心には届いている」という信条を持ってケアにあたることが、終末期介護の基本姿勢です。
👉 家族の視点で「終末期せん妄への対応」を読む
問題104
次のうち,キューブラー・ロス(Kubler-Ross, E.)が提唱した終末期にある人の死の受容過程のうち,「死は避けられないと知り,さまざまな喪失感を抱く段階」に該当するものとして,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 否認
- 2 怒り
- 3 取り引き
- 4 抑うつ
- 5 受容
答え:4
解説:
キューブラー・ロスが提唱した死の受容過程は、一般に「否認」→「怒り」→「取り引き」→「抑うつ」→「受容」の5段階とされています。このうち「抑うつ」の段階は、死が避けられないことを現実として理解し、それによって失うものの大きさ(家族、人生、健康、仕事など)に直面し、深い悲しみや絶望感、無力感(喪失感)に沈む時期とされています。
1の「否認」は「自分は死なない」と死の事実を認めない段階。2の「怒り」は「なぜ自分が死ななければならないのか」と周囲や運命に怒りを向ける段階。3の「取り引き」は「何かにすがる」(神仏、医療、善行)ことで死を先延ばしにしようとする段階。5の「受容」は、死を静かに受け入れる段階です。
【受験生の皆さんへ】「抑うつ」をただの単語として覚えていませんか?
なぜ「死は避けられないと知る」ことが「抑うつ」につながるのか。
それは、希望的観測(否認や取り引き)が打ち砕かれ、現実の喪失感(家族との別れなど)に直面する時期だからです。「人の心の動き」として流れを理解しましょう。
👉 家族の視点で「死の受容プロセス」を読む
問題105
Cさん(58歳,男性)は,アテトーゼ型(athetosis)の脳性麻痺(cerebral palsy)がある。腕,脚,体幹の筋肉は不随意的にゆっくりと動くことが多く,手指を細かく動かすことは難しい。言葉をはっきり発音することが困難であるが,音の聞き取りはできる。次のうち,Cさんが使用している情報・意思疎通支援用具として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 福祉電話
- 2 携帯用会話補助装置
- 3 人工喉頭
- 4 助聴器
- 5 点字器
答え:2
解説:
Cさんは、アテトーゼ型(不随意運動)により「手指を細かく動かすこと」と「はっきり発音すること(構音障害)」が困難ですが、「音の聞き取りはできる」状態です。携帯用会話補助装置(VOCA:Voice Output Communication Aid)は、大きなスイッチやボタン(不随意運動があっても操作しやすい)を押すことで、あらかじめ録音された音声や合成音声を発声させ、会話を補助する装置です。Cさんの状態に最も適していると考えられます。
1の福祉電話(聴覚障害者や発話困難者がファクスなどで通信)や5の点字器は視覚障害者用です。3の人工喉頭は喉頭を摘出した人用です。4の助聴器は聴覚障害者用ですが、Cさんは「音の聞き取りはできる」ため不要です。
【受験生の皆さんへ】Cさんの障害特性、正しく把握できましたか?
「アテトーゼ型脳性麻痺=不随意運動」という特徴から、細かい手指の動きが苦手であることを読み取るのがポイントです。
「身体機能に合わせて、どの道具を選べばコミュニケーションが可能になるか?」というマッチングの視点を養いましょう。
👉 家族の視点で「会話補助装置の選び方」を読む
介護過程
問題106
次の記述のうち,介護過程を展開する目的として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 家族が抱える生活課題の解決
- 2 個別ケアに基づく利用者の自立支援
- 3 介護福祉職の職業倫理の向上
- 4 利用者と家族の信頼関係の構築
- 5 介護福祉職と他職種の連携の促進
答え:2
解説:
介護過程は、アセスメント、計画立案、実施、評価という一連のプロセスです。これは画一的なケアではなく、利用者一人ひとりの状態やニーズに基づいた「個別ケア」を科学的根拠を持って実践するための枠組みです。その最大の目的は、利用者のQOL(生活の質)の向上と「自立支援」にあります。
1(家族)、3(倫理)、4(信頼関係)、5(連携)は、介護過程を展開する上で重要な要素であったり、結果として得られるものであったりしますが、介護過程そのものの「目的」として最も中核となるのは2です。
【受験生の皆さんへ】「介護過程」をただの作業フローだと思っていませんか?
アセスメントから評価までの流れは、すべて「その人らしい生活(個別ケア)」を実現するためにあります。
「家族の課題解決」や「信頼関係」も大切ですが、最大の目的はあくまで「利用者の自立」にあることを、しっかりと区別しましょう。
👉 家族の視点で「計画作成の意義」を読む
問題107
生活課題に関する記述として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 家族の立場から検討する。
- 2 利用者のニーズを判断の基盤にする。
- 3 利用者の要望を1つに集約する。
- 4 介護福祉職の主観を尊重する。
- 5 生命の危機よりも利用者の意向を優先する。
答え:2
解説:
介護過程における「生活課題」(解決すべき課題)は、利用者が望む生活(ニーズ)と、現在の生活状況とのギャップから導き出されます。したがって、利用者の「ニーズ」が何かを正確に把握し、それを判断の基盤(ベース)として課題を特定することが基本です。
1は家族の立場ではなく、利用者の立場が優先されます。4は主観ではなく、客観的な情報収集とアセスメントが必要です。5は安全の確保や生命の維持が最優先であり、利用者の意向と対立する場合は安全を優先します。
【受験生の皆さんへ】「デマンド(要望)」と「ニーズ(課題)」の違い、区別できていますか?
「お菓子が食べたい」はデマンドですが、その裏にあるニーズは「空腹を満たしたい」かもしれないし、「寂しさを紛らわせたい」かもしれません。
「本質的な課題は何か」を見抜く視点を持つことが、適切なケアプラン作成の第一歩です。
👉 家族の視点で「ニーズの深掘り」を読む
問題108
次の記述のうち,介護過程の展開における評価の説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 他の利用者と比較して評価する。
- 2 短期目標の評価によって,介護過程の展開を終了する。
- 3 目標の達成状況を評価する。
- 4 介護計画の実施後に評価日を検討する。
- 5 介護計画を修正した場合は,評価を省略する。
答え:3
解説:
介護過程における「評価」とは、立案した介護計画(長期目標・短期目標)に対して、ケアを実施した結果、「目標がどの程度達成されたか」を客観的に判断することです。そして、達成できていない場合は、その原因を分析し、計画の修正(アセスメントの再実施)につなげます。
1は他者比較ではなく、本人の過去の状態との比較(個人内評価)です。2は短期目標を評価しても、介護過程(アセスメント→計画→実施→評価のサイクル)は終了せず、継続されます。4の評価日は、計画を実施した後ではなく、計画を「立案する段階」であらかじめ設定します。5は計画を修正した場合こそ、その修正が適切であったかどうかの「評価」が必要です。
【受験生の皆さんへ】「評価」をただの書類作成だと思っていませんか?
評価は、ケアの終了ではなく「次のアセスメント(始まり)」です。
なぜ「他人との比較」がダメなのか。それは介護過程の目的が「個別ケアの実現」だからです。「その人にとってどうだったか」を追求する姿勢を学びましょう。
👉 家族の視点で「計画見直しの重要性」を読む
問題109
次のうち,介護保険制度のサービス担当者会議におけるサービス提供責任者の役割として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 会議の主催
- 2 居宅サービス計画の原案の説明
- 3 他職種が実施したサービス内容の評価
- 4 訪問介護計画の作成に要した時間の報告
- 5 訪問介護計画の作成に必要な情報の確認
答え:5
解説:
サービス担当者会議は、主に介護支援専門員(ケアマネジャー)が主催し、居宅サービス計画の原案を説明します。訪問介護のサービス提供責任者は、その会議に参加するメンバーの一員として、居宅サービス計画に基づいた具体的な「訪問介護計画」を作成するために必要な情報(利用者の意向、他サービスとの連携内容など)を確認・収集する役割を担います。
1(主催)と2(原案の説明)は、主に介護支援専門員の役割です。3(他職種の評価)や4(時間の報告)は、サービス担当者会議の主要な目的ではありません。
【受験生の皆さんへ】「会議の主催」は誰の役割か、区別できていますか?
主催はケアマネ、サ責は参加者。この違いを明確にしましょう。
なぜサ責が参加するのか?それは「具体的な訪問介護計画を作るため」です。現場での動きをイメージすれば、選択肢に迷うことはありません。
👉 家族の視点で「サ責の役割」を読む
次の事例を読んで,問題110,問題111について答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(78歳,男性,要介護1)は,一人暮らしで,脳梗塞(cerebral infarction)を発症し入院した。その後,リハビリテーションを経て,自宅に戻った。利き手の右手に麻痺が残ったため,左手を使った調理の自立を目的に,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用することになった。サービス利用時は,訪問介護員(ホームヘルパー)の協力を得ながら,孫からプレゼントされた包丁を使って,調理に取り組んでいた。
ある日,好物の牛肉をうまく押さえることができず,切ることができなかった。すると,Aさんは包丁を置き,部屋で横になってしまった。心配した訪問介護員(ホームヘルパー)が声をかけ,バイタルサインを確認したところ変化はなかった。Aさんは,「右手が思うように動いてくれない。悔しい。でも,もう一度ひとりで作れるようになりたい」と話した。
次の日,Aさんは,「今日も手伝って」と訪問介護員(ホームヘルパー)に話した。
問題110
調理中にAさんが包丁を置き,部屋で横になってしまった行動に対する解釈として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 体調不良による休憩
- 2 食材に対する不満
- 3 調理に対する興味の喪失
- 4 包丁に対する不満
- 5 調理がうまくできないことに対する苛立ち
答え:5
解説:
Aさんは利き手の麻痺が残りながらも「調理の自立」という明確な目標を持っていました。しかし、好物の牛肉がうまく切れなかった(失敗した)直後に、包丁を置いて横になっています。その後の「右手が思うように動いてくれない。悔しい」というAさん自身の言葉から、この行動は、目標(自立)と現実(失敗)のギャップから生じた「苛立ち」や「悔しさ」の表れであると解釈するのが最も適切です。
1はバイタルサインに変化がないことから否定されます。3は「もう一度作れるようになりたい」という言葉と矛盾します。2や4についての記述はありません。
【受験生の皆さんへ】「包丁に対する不満」を選びませんでしたか?
確かに切れなかったのは事実ですが、それは「孫からもらった大切な包丁」です。
道具への不満ではなく、「それを使ってもできない自分への無力感」に着目するのが正解への鍵です。事例の背景にあるストーリーを想像しましょう。
👉 家族の視点で「リハビリ中の葛藤」を読む
問題111
訪問介護計画の修正を目的としたカンファレンスで,訪問介護員(ホームヘルパー)が提案する内容として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 訪問介護員(ホームヘルパー)による調理の代行
- 2 担当する訪問介護員(ホームヘルパー)の交代
- 3 配食サービスの利用
- 4 調理に関する福祉用具の活用
- 5 訪問回数の削減
答え:4
解説:
Aさんの目標は「調理の自立」であり、その意欲も「もう一度作れるようになりたい」と確認できています。課題は「(利き手でないため)牛肉を押さえることができない」という具体的な動作(活動)です。この場合、自立の目標を諦める1(代行)や3(配食)を提案するのではなく、Aさんの残存能力(左手)を活かしつつ、課題を解決できるような「福祉用具の活用」(例:食材を固定できるまな板、握りやすい包丁など)を提案することが、自立支援の観点から最も適切です。
2(担当交代)や5(回数削減)は、問題の本質的な解決になりません。
【受験生の皆さんへ】事例問題の鍵は「利用者の願い(ニーズ)」にあります。
Aさんは「もう一度ひとりで作れるようになりたい」と言っています。この言葉を見逃さなければ、選択肢1(代行)や3(配食)が不適切であることは明白です。
「その人の願いを叶えるための手段は何か?」という視点で、選択肢を吟味しましょう。
👉 家族の視点で「自助具活用のメリット」を読む
次の事例を読んで,問題112,問題113について答えなさい。
〔事 例〕
Bさん(42歳,女性,障害支援区分3)は,知的障害があり,母親と二人暮らしである。日中は生活介護事業所に通っている。日常生活動作の一部に見守りが必要である。個別支援計画の短期目標を,「見守りのもと,トイレで排泄ができる」としている。
しかし,最近,排泄のときに下着やズボンを汚してしまい,それをほかの利用者にからかわれ,しばらく一人でいる様子があったと生活支援員から申し送りがあった。
ある日,事業所長が話しかけると,Bさんは,「トイレで失敗したら恥ずかしい」と元気なく話した。母親からも電話で,「これからは紙おむつを使うように勧めているのだけど,使いたくないとBは話している」とサービス管理責任者に連絡があった。
問題112
次のうち,Bさんがしばらく一人でいた様子を理解するために必要な情報として,最も優先すべきものを1つ選びなさい。
- 1 サービス管理責任者との関係
- 2 生活支援員との関係
- 3 事業所長との関係
- 4 ほかの利用者との関係
- 5 母親との関係
答え:4
解説:
Bさんが一人でいた直接的なきっかけは、排泄を失敗したことを「ほかの利用者にからかわれ」たことです。それによりBさんは「恥ずかしい」と感じ、一人でいる様子がみられました。この一連の出来事の中心には、Bさんと「ほかの利用者」との対人関係(からかいというネガティブなやり取り)があります。したがって、Bさんの行動を理解するためには、普段のほかの利用者との関係性を把握することが最も優先されます。
1、2、3(職員)や5(母親)との関係も重要ですが、今回の行動の直接的な引き金とはなっていません。
【受験生の皆さんへ】母親の「おむつを勧めた」という情報に惑わされていませんか?
母親の提案は、Bさんの「恥ずかしい」という気持ちを解決するどころか、逆撫でしている可能性があります。
優先すべきは「Bさんが孤立している原因(他の利用者との関係)」を把握すること。問題文のヒントから、ご本人の一番の苦しみを汲み取りましょう。
👉 家族の視点で「排泄と自尊心」の関係を読む
問題113
Bさんについて,個別支援会議が開催され,短期目標を,「排泄の自立(下着を汚さずに排泄する)(3か月)」とした。次の記述のうち,Bさんの短期目標を実現するために生活支援員がとる対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 定期的に,手順を理解できているか一緒に確認する。
- 2 自宅で排泄を済ませ,事業所で排泄しないように助言する。
- 3 母親の要望であると伝え,紙おむつを使うように助言する。
- 4 ポータブルトイレを設置し,そこで排泄をするように誘導する。
- 5 排泄に関する行為を,全介助にする。
答え:1
解説:
Bさんは排泄の失敗で「恥ずかしい」と感じており、紙おむつは「使いたくない」という意向を持っています。目標は「排泄の自立」です。この状況で必要な支援は、Bさんの尊厳を守りつつ、失敗の原因を探り、自立を促すことです。失敗の原因が、トイレに行くタイミング、衣服の着脱、拭き方などの「手順」の混乱である可能性を考え、「定期的に、手順を理解できているか一緒に確認する」ことは、Bさんを尊重しながら自立を支援する最も適切な対応です。
2(事業所でさせない)や5(全介助)は、「自立」という目標に反します。3(紙おむつ)は、Bさん本人の意向(自己決定)を無視した対応であり不適切です。4は、事業所のトイレで排泄できることが目標であり、ポータブルトイレの設置は適切ではありません。
【受験生の皆さんへ】「母親の要望」を優先していませんか?
介護の主役はあくまで「利用者本人」です。母親がオムツを勧めていても、本人が拒否しているなら、専門職としては本人の意思を尊重し、自立に向けた支援(選択肢1)を提案すべきです。
「誰のためのケアか」を見失わないようにしましょう。
👉 家族の視点で「失敗への寄り添い方」を読む
総合問題
次の事例を読んで,問題114から問題116までについて答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(70歳,男性)は,妻と二人で暮らしている。旅行や釣りが趣味で,会社員として勤務していたころは,活動的な生活を送っていた。66歳のときにパーキンソン病(Parkinson disease)と診断されたが,内服治療が開始され,症状はあまり気にならなかった。1年前から顔の表情が乏しくなり,歩行開始時に,はじめの一歩が出にくくなった。3か月前からは,歩き始めると方向転換が難しく,急に止まることができないことがある。
Aさんは,今後の生活について相談するために,地域包括支援センターに行った。センターで対応してくれたB主任介護支援専門員は,介護福祉士としての実務経験が豊富だった。Aさんは信頼して,気になっていたことをすべて話すことができた。Aさんは,要介護認定を申請することを勧められ,後日,市役所に行き,要介護認定の申請を行った。
問題114
現在のAさんの症状に該当するホーエン・ヤール重症度分類として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 ステージⅠ
- 2 ステージⅡ
- 3 ステージⅢ
- 4 ステージⅣ
- 5 ステージⅤ
答え:3
解説:
ホーエン・ヤール重症度分類において、ステージⅢは、両側性の症状(表情が乏しい、すくみ足など)に加えて、姿勢反射障害(バランスが崩れやすく、転びやすい)が出現し始める段階を指します。Aさんの「方向転換が難しく」「急に止まることができない」(突進現象)という症状は、この姿勢反射障害に該当するため、ステージⅢが最も適切です。
ステージⅠは片側のみの症状、ステージⅡは両側性の症状のみ(姿勢反射障害なし)の状態です。ステージⅣは日常生活に介助が必要な状態、ステージⅤは車いすや寝たきりの状態を指します。
【受験生の皆さんへ】「すくみ足・小刻み歩行」からステージ3を選べましたか?
ステージ1・2(軽症)とステージ3(中等度)の決定的な違いは、「姿勢反射障害(バランスがとれない)」の有無です。
「転びやすくなる」という生活リスクと結びつけて覚えれば、もう迷うことはありません。
👉 家族の視点で「パーキンソン病の歩行」を読む
問題115
要介護認定を申請してから2週間が経過した。Aさんは要介護認定の認定結果が届かないことが気になった。そこで,以前に対応してくれたB主任介護支援専門員に電話で相談した。
次のうち,B主任介護支援専門員の応答として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 「次の受診時に主治医に相談しましょう」
- 2 「通常1か月程度かかるので,あと2週間くらい待ってみましょう」
- 3 「以前に自宅に来てくれた認定調査員に相談しましょう」
- 4 「念のためにもう一度要介護認定を申請してください」
- 5 「通常であれば認定結果は出ていると思います」
答え:2
解説:
要介護認定の申請から認定結果の通知までの期間は、介護保険法により、原則として申請日から30日以内と定められています。Aさんは申請からまだ2週間しか経過していないため、B主任介護支援専門員としては、この目安(「通常1か月程度」)を伝え、Aさんの不安を軽減する対応が最も適切です。
1(主治医)や3(調査員)に相談するのは適切ではありません。4(再申請)は不要です。5はAさんの不安を煽る不適切な説明です。
【受験生の皆さんへ】「原則30日」という数字、ただ暗記していませんか?
その30日の間に、申請者は「まだか、まだか」と不安な日々を過ごしています。
待機期間中の心理や、その間の生活を支える「暫定プラン」の運用まで想像を広げることで、制度の数字が生きた知識として定着します。
👉 家族の視点で「認定待ち期間」の不安を読む
問題116
最近,Aさんは急に体の動きが悪くなる時間帯があり,不安を感じた。そこでAさんは,週に2回利用している訪問介護員(ホームヘルパー)に相談した。相談を受けた訪問介護員(ホームヘルパー)はAさんに,日々の症状の変化とその時間,さらにもう一点をメモして,医師に伝えるようにと助言した。
日々の症状の変化とその時間に加えて,Aさんが医師に伝える内容として,最も優先度の高いものを1つ選びなさい。
- 1 服薬の時間
- 2 起床の時間
- 3 食事の時間
- 4 排便の時間
- 5 入浴の時間
答え:1
解説:
パーキンソン病のAさんにみられる「急に体の動きが悪くなる時間帯」は、内服薬(L-ドパなど)の効果が切れる時間帯に起こる「ウェアリング・オフ現象」である可能性が非常に高いです。医師が薬の量や種類、内服回数を適切に調整するためには、症状が出た時間と「服薬の時間」との関連性を把握することが最も重要となります。
起床、食事、排便、入浴の時間も生活を知る上で重要ですが、薬の効果との関連性を確認するためには、服薬時間の優先度が最も高いです。
【受験生の皆さんへ】「日々の変化」に何をプラスすべきか、即答できますか?
食事や入浴の時間も大切ですが、パーキンソン病においては「薬」との関連性が最優先事項です。
「ウェアリング・オフ現象」という病態生理と、それを把握するための「情報収集(モニタリング)」の視点をリンクさせましょう。
👉 家族の視点で「症状日誌の書き方」を読む
次の事例を読んで,問題117から問題119までについて答えなさい。
〔事 例〕
Cさん(90歳,女性)は,動物好きで長年ペットのオウムを飼っている。5年前に夫が亡くなったときも,ペットが大きな心の支えになった。2年前,身体の衰えから買物や調理などの家事が難しくなり,一人暮らしが困難になったので,ペットと入所できる健康型有料老人ホームに入所した。
最近Cさんは,毎週楽しみにしていたレクリエーションがある曜日や時間を忘れてしまう,トイレの場所がわからず失禁するなどの症状が繰り返し生じるようになってきた。心配した娘がCさんと病院を受診したところ,アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)と診断を受けた。
健康型有料老人ホームでは対応が困難になってきたため,心配した娘はCさんが入所できる施設に移ることを検討し始めた。
問題117
次のうち,最近のCさんの症状に該当するものとして,最も適切なものを 1つ選びなさい。
- 1 妄想
- 2 見当識障害
- 3 失語
- 4 遂行機能障害
- 5 観念失行
答え:2
解説:
見当識障害とは、現在の時間、場所、人物などが正しく認識できなくなる症状です。Cさんの「曜日や時間を忘れてしまう」(時間の見当識障害)や、「トイレの場所がわからない」(場所の見当識障害)という症状は、まさに見当識障害の典型的な例です。
1(妄想:事実でないことを信じ込む)、3(失語:言葉の理解や表出が困難)、4(遂行機能障害:段取りができない)、5(観念失行:道具を使えない)は、事例の症状とは異なります。
【受験生の皆さんへ】「レクの日時を忘れる=記憶障害」だけで片付けていませんか?
確かに記憶の問題もありますが、日時や場所が特定できなくなるのは「見当識」の崩れです。
Cさんの「トイレの場所がわからない」という行動から、「空間認識(場所の見当識)の低下」を読み取る力が、現場での適切な環境整備につながります。
👉 家族の視点で「見当識障害の不安」を読む
問題118
娘はCさんの病状を心配して,「お父さんが残してくれた貯金があるから,もっとお母さんのお世話をしてくれる施設に移ろう」と提案した。Cさんは,「ペットと一緒に暮らせなくなるのは嫌だ」とつぶやき,うつむいた。困った娘は健康型有料老人ホームの介護福祉士に相談した。
次のうち,娘への介護福祉士の応答として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 「Cさんがペットを大事にしている意思を尊重してはいかがですか」
- 2 「Cさんが新しい施設に行くことが最優先です」
- 3 「あなたの意向を優先してはいかがですか」
- 4 「Cさんがペットを飼うことは優先度の高いニーズとは言えません」
- 5 「Cさんが新しい施設に行くことを受け入れるように説得してください」
答え:1
解説:
Cさんは「ペットと一緒に暮らせなくなるのは嫌だ」という、長年の心の支えであるペットに関する明確な意思を示しています。介護福祉職は、たとえ認知症があっても本人の意思決定を支援し、その思いを尊重する(アドボカシー)立場にあります。したがって、娘に対してCさんのその意思を尊重することを提案する1が最も適切です。
2、3、4、5は、Cさんの自己決定権を無視し、家族や支援者の都合を優先する不適切な対応です。
【受験生の皆さんへ】「説得する(選択肢5)」を選びそうになりませんでしたか?
娘さんの心配ももっともですが、専門職の役割は家族の味方をすることではなく、「ご本人の最善の利益(QOL)」を守ることです。
Cさんにとってオウムがどれほど大きな存在か。事例の背景にある「生活史」を読み解く力が試されます。
👉 家族の視点で「ペットと生きがい」の関係を読む
問題119
Cさんと娘は介護福祉士と相談し,希望に沿った施設を見つけることができた。
次のうち,Cさんが入所する施設として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 経過的軽費老人ホーム(B型)
- 2 介護医療院
- 3 介護老人保健施設
- 4 養護老人ホーム
- 5 介護付有料老人ホーム
答え:5
解説:
Cさんはアルツハイマー型認知症の介護が必要であり、かつ「ペットと入所できる」という強い希望を持っています。「介護付有料老人ホーム」は、介護サービスが提供される居住施設であり、施設によっては「ペット可」としているなど、多様な選択肢が存在します。Cさんと娘が希望に沿った施設(認知症ケアとペット飼育が両立できる)を見つけた場合、この形態である可能性が最も高いです。
1、2、3、4は、公的な性格が強い施設であり、ペットとの入所は原則として認められていません。また、2(医療院)や3(老健)は医療やリハビリが中心、4(養護)は経済的・環境的理由による措置入所が基本であり、Cさんの状況とは異なります。
【受験生の皆さんへ】消去法ではなく「積極法」で選べましたか?
単に「他が違うから」ではなく、「CさんのQOL(ペットとの生活)を守りつつ、必要なケア(認知症対応)を提供できるのはここしかない」という理由で選ぶことが大切です。
「利用者の生活の継続性」という視点から、各施設の機能を再確認しましょう。
👉 家族の視点で「施設選びの基準」を読む
次の事例を読んで,問題120から問題122までについて答えなさい。
〔事 例〕
Dさん(男性,障害支援区分4)は,ベッカー型筋ジストロフィー(Becker muscular dystrophy)である。自宅で家族と生活をしている。Dさんは,食事は自立しているが,排泄,入浴に介護が必要である。歩行はできず,移動は電動車いすを使用している。絵を描くことが趣味であり,日中は創作活動に取り組んでいる。
これまでDさんは自宅で家族の介護を受けながら生活してきたが,Dさんの身体機能の低下に伴い,家族の介護負担が増えたため,居宅介護を利用することになった。
問題120
Dさんの疾患で生じる病態として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 筋線維の変性
- 2 運動神経の変性
- 3 網膜の変性
- 4 自己免疫の低下
- 5 脳細胞の変性
答え:1
解説:
筋ジストロフィー(ベッカー型やデュシェンヌ型など)は、筋肉の細胞(筋線維)を構成・維持するタンパク質が遺伝子の変異によって正常に作られないため、筋線維が徐々に壊れていく(変性・壊死)疾患です。
2(運動神経の変性)は筋萎縮性側索硬化症(ALS)など、3(網膜の変性)は網膜色素変性症など、5(脳細胞の変性)は認知症やパーキンソン病などの病態です。
【受験生の皆さんへ】「病態」と「生活」を結びつけていますか?
「筋線維の変性」という医学的な正解を選ぶだけでなく、その病態がDさんの生活(電動車椅子、創作活動、家族の介護負担)にどう影響しているかを読み取ることが大切です。
事例を通して、病気と生活支援の関係を深く理解しましょう。
👉 家族の視点で「難病との暮らし」を読む
問題121
E居宅介護事業所に勤務するF介護福祉職は,Dさん宅を初回訪問するにあたりフェイスシートのジェノグラムを確認した。以下のジェノグラムからF介護福祉職が把握した内容として,適切なものを1つ選びなさい。

- 1 Dさんは,Dさんの母親と同居している。
- 2 Dさんには息子がいる。
- 3 Dさんの兄は結婚している。
- 4 Dさんの父親は生存している。
- 5 Dさんの妻には兄弟姉妹がいる。
答え:2
解説:
このジェノグラム(家族図)において、Dさん(ご本人)は48歳の男性(四角)と解釈するのが最も適切です。Dさん(48)は、妻(47)との間に実線で結ばれた21歳の男性(四角)がいます。これはDさんの「息子」を意味します。したがって、選択肢2が正解です。
1:Dさん(48)の母親(77)は、Dさんの兄(51)と同じ点線(別世帯)で囲まれており、Dさんとは同居していません。
3:Dさん(48)の兄(51)は未婚です。
4:Dさん(48)の父親(左上の黒塗りの四角)は、塗りつぶされているため故人であると読み取れます。
5:Dさん(48)の妻(47)に兄弟姉妹は描かれていません。
【受験生の皆さんへ】「図を見て答える問題」に焦っていませんか?
ジェノグラムの問題は、ルールさえ知っていれば確実に点数が取れるサービス問題です。
Dさんの事例のように、「なぜ今、家族構成の確認が必要なのか(介護負担の増加)」という背景とセットで理解することで、アセスメント能力が磨かれます。
👉 家族の視点で「ジェノグラムの役割」を読む
問題122
Dさんが居宅介護を利用してから数年が経過し,Dさんの身体機能は徐々に低下して,着替えに時間がかかるようになった。Dさんは自分のことはできるだけ自分で行いたいという思いがあり,時間がかかっても自分で着替えをしていた。
ある日,DさんはF介護福祉職に,「着替えをすると疲れてしまい,絵を描くことができない」とつぶやいた。F介護福祉職は,「着替えは私たちや家族の介護を利用して,Dさんは好きな絵を描いたらいいのではないですか」と伝えた。その後,Dさんは介護福祉職と家族の介護を利用して,短時間で着替えを済ませ,絵を描くことに専念できるようになった。
F介護福祉職が発言した自立観を示した人物として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 ヴィクトール・フランクル(Frankl, V.)
- 2 バンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen, N.)
- 3 エド・ロバーツ(Roberts, E.)
- 4 フェリックス・バイステック(Biestek, F.)
- 5 ミルトン・メイヤロフ(Mayeroff, M.)
答え:3
解説:
エド・ロバーツは、自立生活運動(IL運動)の父と呼ばれる人物です。彼は、障害者自身の「自己決定」に基づき、介護サービス(人の手)を使いながらでも、地域で主体的に生活すること(QOLの追求)こそが「自立」であると提唱しました。F介護福祉職の助言は、ADL(着替え)の動作的自立にこだわるより、介護を利用してQOL(絵を描くこと)を優先する、まさにこの自立観に基づいています。
1(フランクル)は実存分析、2(バンク-ミケルセン)はノーマライゼーション、4(バイステック)はケースワークの7原則、5(メイヤロフ)はケアリング論の提唱者です。
【受験生の皆さんへ】人名問題、ただの暗記だと思っていませんか?
なぜDさんの事例で「エド・ロバーツ」が正解になるのか。
それは、彼が提唱した「自立生活運動(IL運動)」の精神が、まさにDさんの「ケアを受けて自己実現する姿」と重なるからです。エピソードと人物をセットで覚えれば、記憶は定着します。
👉 家族の視点で「新しい自立観」を読む
次の事例を読んで,問題123から問題125までについて答えなさい。
〔事 例〕
Gさん(38歳,女性)は,母親(65歳)と暮らしていた。両側性感音難聴(sensorineural hearing loss)があり,雑音がある場所では話を聞き取りにくい。相手の口の動きや表情から会話の内容を理解することはできる。Gさんは,脳梗塞(cerebral infarction)を発症し,左片麻痺で車いすの生活となり,障害支援区分4と認定された。母親による介護が難しくなったため,障害者支援施設に入所することになった。
Gさんは,写真を撮ることが好きで,施設で近くの公園に出かけたときに,介護福祉職に手伝ってもらいながら好きな風景を撮影している。Gさんは,その写真をアルバムにして,母親にプレゼントしたいと考えている。
ある日,Gさんから,「アルバムを作りたい。飾りの付け方やメッセージの書き方を教えてほしい」と相談があった。介護福祉職は,Gさんとアルバムを作ることにした。
問題123
次のうち,Gさんが施設入所支援と同時に利用している障害福祉サービスとして,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 自立生活援助
- 2 療養介護
- 3 短期入所
- 4 生活介護
- 5 居宅介護
答え:4
解説:
障害者支援施設では、利用者は夜間の「施設入所支援」と、日中の「生活介護」(創作活動、機能訓練、入浴・排泄・食事等の介護)を組み合わせて利用することが一般的です。Gさんが日中に公園で写真を撮ったり、アルバム作りを行ったりする活動は、この「生活介護」の一環として提供されていると考えられます。
1(自立生活援助)は一人暮らしの支援、2(療養介護)は医療的ケアが常時必要な人、3(短期入所)は一時的な宿泊、5(居宅介護)は在宅でのサービスです。
【受験生の皆さんへ】「施設入所支援」と「生活介護」のセット利用、理解できていますか?
Gさんは施設に入所していますが、日中の活動として利用しているのは「生活介護」です。
なぜ「居宅介護」や「療養介護」ではないのか。「日中活動の場」という視点でサービス体系を整理し、Gさんの生活(写真撮影やアルバム作り)と結びつけて覚えましょう。
👉 家族の視点で「施設での日中活動」を読む
問題124
次のうち,Gさんの難聴の原因となっている損傷部位に該当するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 内耳から聴神経
- 2 外耳道から中耳
- 3 耳介から中耳
- 4 耳介から外耳道
- 5 耳介
答え:1
解説:
難聴は、障害部位によって「伝音難聴」(外耳〜中耳)と「感音難聴」(内耳〜聴神経)に大別されます。Gさんは「感音難聴」と診断されているため、障害の原因部位は音を感じ取る「内耳」(蝸牛)や、その信号を脳に送る「聴神経」にあります。
2、3、4、5はすべて、外耳や中耳の部位であり、これらが原因となるのは「伝音難聴」です。
【受験生の皆さんへ】「内耳・聴神経=感音性」と丸暗記していませんか?
重要なのは、損傷部位によって「どんな聞こえにくさ(生活課題)」が生じるかです。
Gさんがなぜ口の動きを見ているのか。その理由を「音の歪み・弁別困難」という症状と結びつけることで、深い病態理解につながります。
👉 家族の視点で「聞こえにくさの正体」を読む
問題125
次の記述のうち,Gさんに介護福祉職がアルバムの作り方を説明するときに配慮することとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 Gさんの左側に座る。
- 2 閉じられた質問を用いる。
- 3 小さな声で話す。
- 4 Gさんの好きな音楽を流す。
- 5 1対1で向かい合って話す。
答え:5
解説:
Gさんは、雑音があると聞き取りにくい一方、「相手の口の動きや表情から会話の内容を理解できる」(読話)という特徴があります。したがって、Gさんが口元や表情を読み取りやすいように、雑音のない静かな環境で、「1対1で向かい合って」視線を合わせて話すことが最も適切な配慮です。
1(左側)は片麻痺への配慮であり、両側性難聴のGさんには不適切です。2(閉じられた質問)はコミュニケーションの幅を狭めます。3(小さな声)は聞き取れません(明瞭な発音が重要)。4(音楽)はGさんにとって「雑音」となり、聞き取りを妨げます。
【受験生の皆さんへ】「健側から話しかける」というセオリーに固執していませんか?
通常、片麻痺の方へは健側介助が基本ですが、この事例では「読唇(口の動きを見る)」が必要な難聴があるため、「正面」が正解になります。
「複数の障害がある場合、どちらを優先すべきか」という応用力が問われる良問です。
👉 家族の視点で「伝わる位置取り」を読む
過去の問題はこちら
(令和6年度午後)介護福祉士国家試験 問題・解答・解説 (当ページ)