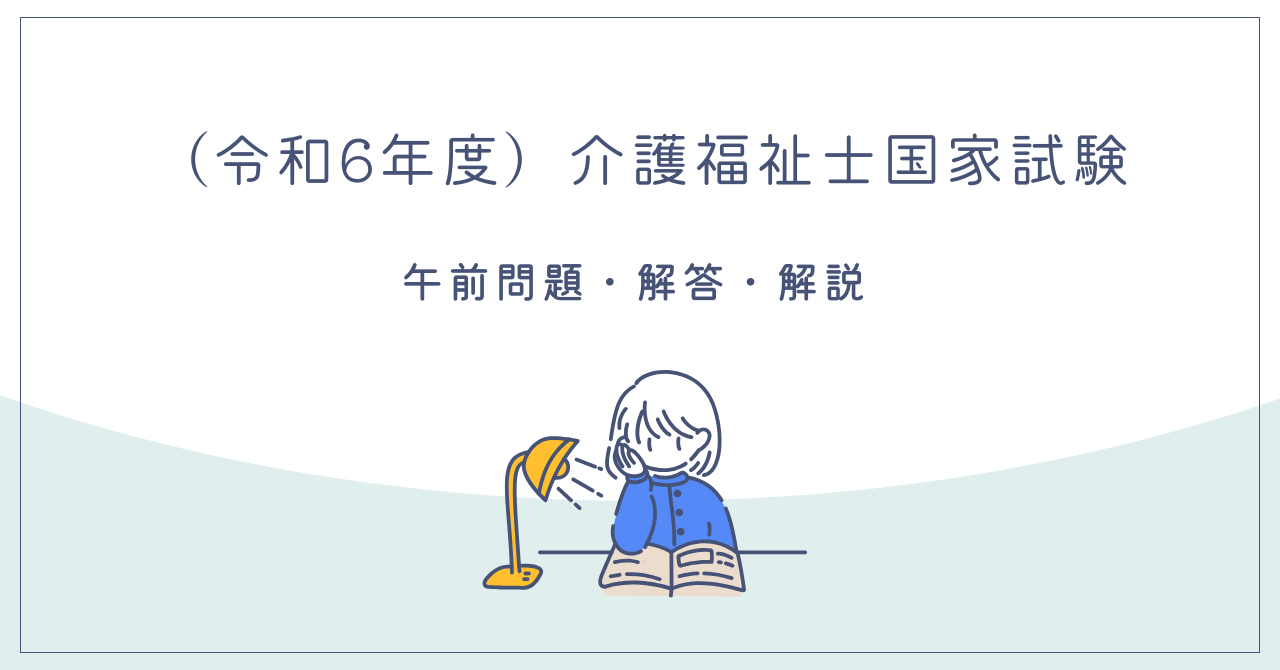人間の尊厳と自立
問題1
次の記述のうち,介護福祉職がアドボカシー(advocacy)の視点から行う対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 介護を行う前には,利用者に十分な説明をして同意を得る。
- 2 利用者の介護計画を作成するときに,他職種に専門的な助言を求める。
- 3 利用者個人の趣味を生かして,レクリエーション活動を行う。
- 4 希望を言い出しにくい利用者の意思をくみ取り,その実現に向けて働きかける。
- 5 視覚障害者が必要とする情報を,利用しやすいようにする。
答え:4
解説:
アドボカシーとは、利用者の権利を擁護すること、特に自分では意思を表明しにくい利用者の代わりにその意向をくみ取り、代弁・主張することを指します。選択肢4は、まさにこのアドボカシー(権利擁護・代弁機能)の実践例であり、正解です。
他の選択肢については、1はインフォームド・コンセント(説明と同意)、2は多職種連携、3はレクリエーション活動、5は情報提供や環境整備(アクセシビリティの確保)に関する記述であり、いずれも重要な支援ですが、アドボカシーの核心的な意味とは異なります。
【受験生の皆さんへ】用語の暗記に疲れていませんか?
「アドボカシー」=「権利擁護・代弁」。言葉で覚えると難しく感じますが、現場のリアルな悩みを通すと一発でイメージできます。
「なぜ利用者は本音を言えないのか?」という視点を持つことで、正解を選ぶ力がグッと深まります。息抜きがてら、現場視点のコラムを読んでみませんか?
👉 現場のエピソードで「アドボカシー」を深く理解する
問題2
Aさん(83歳,女性,要介護3)は,脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症で左ひだりかたまひ片麻痺があり,介護老人福祉施設で生活している。家族から,「できることは自分で行ってほしい」と希望があり,Aさんは自室から食堂まで車いすで自走することを日課としている。
1 週間前から,介護福祉士養成施設の学生がAさんのフロアで実習を開始した。数日前からAさんは実習生に,「今日は腕が痛いので,食堂まで車いすを押してください」と依頼するようになった。悩んだ実習生は,実習指導者に相談をした。
実習生に対する実習指導者の最初の助言として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 「Aさんの腕は痛くないので,気にしないでください」
- 2 「どのようなときも,Aさん自身で行ってもらうことが必要です」
- 3 「ご家族から自分で行うように,言われています」
- 4 「それは自立につながらないので,車いすを押さないでください」
- 5 「Aさんが依頼する理由を,まず考えてみることが大切です」
答え:5
解説:
利用者の行動や発言には、必ず何らかの理由や背景があります。Aさんが「腕が痛いので押してほしい」と依頼するようになった理由(本当に腕が痛いのか、実習生との関係性を築きたいのか、あるいは他の要因か)を利用者の視点に立って考えることが、適切な支援の第一歩となります。選択肢5は、実習生自身にその理由のアセスメント(把握・分析)を促す、最も適切な指導・助言です。
1のように利用者の訴えを否定したり、2や4のように「自立」という側面だけを捉えて一律に拒否したり、3のように家族の意向だけを伝えたりすることは、Aさんの現在の状態や思いを尊重していない不適切な対応です。
【受験生の皆さんへ】「自立支援=突き放す」ではありません。
正解の選択肢を選ぶのは簡単ですが、現場で実践するのは難しいものです。
家族の心理や、高齢者の「甘え」の背景にあるものを理解することで、「なぜ他の選択肢がダメなのか」が深く理解できるようになります。暗記を「知恵」に変えるコラムを読んでみませんか?
👉 現場視点で「利用者の本音」を深く理解する
人間関係とコミュニケーション
問題3
人間関係と心理に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 自己愛とは,自分という存在を,他人と区別して意識することである。
- 2 自己同一性の確立とは,自分とは何かという認識をもつことである。
- 3 自我とは,日常行動に影響を与える,表面化していない意識のことである。
- 4 自己覚知とは,コミュニケーションにおいて自分について話すことである。
- 5 自己中心性とは,自分の意思で自分の行動をコントロールすることである。
答え:2
解説:
自己同一性(アイデンティティ)の確立とは、エリクソン(Erikson, E.H.)が提唱した青年期の課題で、「自分とは何者か」「社会で何をすべきか」といった問いに対し、自分なりの答えを見いだし、連続性のある確固たる自分を持つことです。選択肢2は、この定義を正しく説明しています。
1の「他人と区別して意識すること」は自我意識や自己意識の説明に近く、3の「表面化していない意識」は潜在意識の説明です。4の「自分について話すこと」は自己開示、5の「自分の行動をコントロールすること」は自己統制(セルフコントロール)の説明です。
【受験生の皆さんへ】用語の定義、丸暗記になっていませんか?
「自己同一性=アイデンティティ」。そう覚えるのは簡単ですが、現場で高齢者が抱える「定年後の喪失感」と結びつけられていますか?
「なぜ高齢者は元気をなくすのか?」という視点を持つと、無機質な心理学用語が生きた知識に変わります。
👉 高齢者の「心の喪失」とアイデンティティの関係を読む
問題4
Aさん(80歳,男性)は,有料老人ホームに入所することになった。一人暮らしが長かったAさんは,入所当日,担当の介護福祉職と話すことに戸惑っている様子で,なかなか自分のことを話そうとはしなかった。介護福祉職は,一方的な働きかけにならないように,Aさんとコミュニケーションをとるとき,あいづちを打ちながらAさんの発話を引き出すように心がけた。
このときの,介護福祉職の対応の意図に当てはまるものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 互いの自己開示
- 2 コミュニケーション能力の評価
- 3 感覚機能の低下への配慮
- 4 認知機能の改善
- 5 双方向のやり取り
答え:5
解説:
コミュニケーションは、送り手と受け手が互いに情報をやり取りし、影響を与え合う「双方向」のプロセスが基本です。介護福祉職が一方的にならず、あいづち(受容・傾聴のサイン)を打ちながらAさんの発話(反応)を引き出そうとする対応は、まさにこの双方向のやり取りを成立させ、信頼関係を築こうとする意図の表れです。
1の自己開示は、関係性ができてから徐々に行われるものです。2の評価が目的ではなく、3や4の機能低下への対応であるとは本文からは読み取れません。
【受験生の皆さんへ】「一方的」と「双方向」の違い、説明できますか?
言葉の定義は知っていても、現場で具体的にどう振る舞うことなのか、イメージできていますか?
家族がついやってしまう「尋問のような会話」を反面教師にすることで、「なぜ発話を引き出す必要があるのか」が腑に落ちるはずです。実践的なコラムで理解を深めましょう。
👉 家族の会話から「双方向コミュニケーション」を学ぶ
問題5
次の記述のうち,介護福祉職のキャリアパスに関するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 介護計画を作成するときのポイントを明確にする。
- 2 介護福祉職の業務マニュアルを具体化する。
- 3 利用サービスに応じて求められる関係書類を検討する。
- 4 介護施設に必要な設備基準について確認する。
- 5 介護福祉職として必要な能力や経験を明確にする。
答え:5
解説:
キャリアパスとは、職務における経歴や、昇進・昇格に至るまでの道筋・順序を指します。介護福祉職のキャリアパスを構築するには、例えば「一般職」「リーダー」「主任」といった各段階(職位)において、どのような能力(知識・技術・倫理観)や経験が必要とされるのかを明確にし、体系化することが不可欠です。よって、選択肢5が正解です。
1、2、3は具体的な「業務内容」の整備であり、4は「設備基準」であり、いずれも人材育成の道筋であるキャリアパスそのものを指すものではありません。
【受験生の皆さんへ】「キャリアパス」をただの制度だと思っていませんか?
言葉の定義を覚えるだけでは、本当の理解とは言えません。「なぜキャリアパスが必要なのか?」それは、利用者が安心して暮らすため、そして家族が施設を信頼するための「品質保証」だからです。
利用者側の視点を知ることで、無機質な制度論が「生きた知識」に変わります。
👉 家族の視点で「キャリアパス」の重要性を読む
問題6
B介護老人福祉施設に,学校を卒業したばかりの元気なC介護福祉職が加わった。2か月後,ユニットリーダーが,「最近,C介護福祉職に笑顔が少ない。いつもとちがう様子だ」と,フォロワーであるD介護福祉職に話した。D介護福祉職はチームの一員として何ができるのかを考えた。D介護福祉職が最初に行うフォロワーシップとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 C介護福祉職に対して,元気を出すように励ます。
- 2 ユニットリーダーが気になっていることを詳しく聞く。
- 3 C介護福祉職の状況をユニット内のほかのメンバーと速やかに共有する。
- 4 施設長に対して,何か指示を出すようにお願いする。
- 5 C介護福祉職に対して,介助方法について教える。
答え:2
解説:
フォロワーシップとは、チームの目標達成のために、リーダーを補佐し、主体的に貢献することです。リーダーがCさんについて懸念を抱いている状況で、フォロワーであるD介護福祉職がまず行うべきことは、リーダーの懸念(Cさんのどのような様子を、どの程度気にかけているのか)を「詳しく聞く」ことです。これにより、リーダーと現状認識を共有し、チームとして次に行うべき適切な行動(Cさんへの声かけ、業務の調整など)を判断できます。
状況把握が不十分なまま、1のように励ましたり、3のように共有したり、5のように指導したりすることは適切ではありません。4のようにいきなり上位者に指示を仰ぐのも、チーム内の問題解決プロセスを逸脱しています。
【受験生の皆さんへ】「フォロワーシップ」を抽象的に捉えていませんか?
「リーダーを補佐する」といっても、具体的に何をすることなのか。ただのイエスマンになることではありません。
家族間のやり取りに置き換えて考えることで、「なぜ最初にリーダーの話を聞く必要があるのか(=状況把握)」という本質が見えてきます。
👉 家族の会話から「フォロワーシップ」の本質を学ぶ
社会の理解
問題7
社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち,適切なものを 1つ選びなさい。
- 1 収益事業は禁止されている。
- 2 所轄庁は内閣府である。
- 3 設立時に所轄庁の認可は不要である。
- 4 評議員会を置く必要がある。
- 5 解散は禁止されている。
答え:4
解説:
2016年の社会福祉法改正により、社会福祉法人のガバナンス(組織統治)強化のため、議決機関として評議員会を必ず設置することが義務付けられました。したがって、4が正解です。
1の収益事業は、定款で定め、収益を社会福祉事業に充てることを条件に実施可能です。2の所轄庁は、原則として主たる事務所がある都道府県知事または市長(指定都市・中核市の場合)です。3の設立には所轄庁の「認可」が必要です。5の解散は、評議員会の議決や破産など、法に定められた事由により可能です。
【受験生の皆さんへ】「評議員会」の設置義務、丸暗記で終わらせていませんか?
なぜわざわざ「評議員」が必要なのか。それは、利用者の生活を守るために「独断専行を防ぐストッパー」が不可欠だからです。
「家族が安心して預けられる理由」という視点から法人の仕組みを見ると、無味乾燥な法律知識に体温が宿ります。
👉 家族の視点で「法人のガバナンス」を理解する
問題8
次の記述のうち,定期巡回・随時対応型訪問介護看護の説明として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 利用定員は,9人以下と定められている。
- 2 日中・夜間を通じて,提供するサービスである。
- 3 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居する利用者に対して,機能訓練を行うサービスである。
- 4 通い,泊まり,看護の3種類の組合せによるサービスである。
- 5 都道府県が事業者の指定,指導,監督を行うサービスである。
答え:2
解説:
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、地域密着型サービスの一つです。その最大の特徴は、日中・夜間を問わず24時間体制で、定期的な巡回訪問と利用者からの通報(コール)による随時の対応(介護・看護)を行う点にあります。よって、2が正解です。
1の利用定員は小規模多機能型居宅介護等の規定で、本サービスにはありません。3は認知症対応型共同生活介護の説明です。4は(看護)小規模多機能型居宅介護の説明です。5は地域密着型サービスのため、指定・監督は「市町村」が行います。
【受験生の皆さんへ】漢字の羅列を丸暗記しようとしていませんか?
「定期巡回・随時対応型…」と呪文のように覚えるよりも、「夜中に親が転倒したらどうする?」という家族の切実な悩みを想像してください。
「なぜ日中・夜間を通じて対応が必要なのか」がストンと腹に落ち、迷わず正解を選べるようになります。
👉 家族の視点で「24時間訪問サービス」の必要性を読む
問題9
Aさん(48歳,会社員)は,うつ症状から体調不良が続き,仕事を休むことが増えたため,自主的に退職した。その後,体調は回復したが,再就職先がなかなか見つからなかった。しばらく貯金で生活していたが,数か月後,生活を営むことができなくなってしまった。頼れる親族はなく,生活保護を受給することにした。
この事例において,日本国憲法に基づいてAさんに保障された権利として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 団体交渉権
- 2 平等権
- 3 財産権
- 4 思想の自由
- 5 生存権
答え:5
解説:
生活保護制度の根拠となるのは、日本国憲法第25条の「生存権」です。この条文は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めており、Aさんが生活困窮により生活保護を受給するのは、この生存権の保障に基づいています。
1は労働基本権の一つ、2は法の下の平等を定めた第14条、3は第29条、4は第19条で保障される権利であり、いずれも生活保護の直接的な根拠ではありません。
【受験生の皆さんへ】憲法25条、条文の暗記だけで満足していませんか?
「生存権」という言葉の裏には、病気や失業で追い詰められた人々の切実な生活があります。
Aさんのような事例を通して「なぜこの権利が必要なのか」を想像することで、無機質な法律の知識が、現場で利用者さんを守るための武器に変わります。
👉 生活者の視点で「生存権」の重みを理解する
問題10
次の記述のうち,保健所に関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 保健師助産師看護師法に基づいて設置されている。
- 2 すべての市町村に設置の義務がある。
- 3 業務には精神保健に関する事項が含まれている。
- 4 歯科衛生士を置かなくてはならない。
- 5 児童の一時保護を行う。
答え:3
解説:
保健所の業務は地域保健法に定められており、公衆衛生や疾病予防、健康増進など多岐にわたります。その業務内容には「精神保健に関する事項」(相談、普及啓発など)も含まれています。よって、3が正解です。
1の設置根拠は「地域保健法」です。2は都道府県、指定都市、中核市などが設置主体であり、すべての市町村に設置義務はありません。4は必置職種ではありません。5の児童の一時保護は主に「児童相談所」の業務です。
【受験生の皆さんへ】「地域保健法」などの法律名、丸暗記は辛くないですか?
法律の条文を覚えるよりも、「親がうつ病になったらどこに行く?」という具体的なエピソードとセットで覚える方が、記憶に定着します。
保健所のリアルな役割を知ることで、試験問題が「ただの文字」から「現場の知識」に変わります。
👉 実生活での「保健所活用法」を読んで理解を深める
問題11
地域包括支援センターの業務に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 地域ケア会議の開催
- 2 施設サービスのケアプランの作成
- 3 成年後見制度の申請
- 4 介護認定審査会の設置
- 5 地域密着型サービスの事業者の指導・監督
答え:1
解説:
地域包括支援センターの業務には「包括的・継続的ケアマネジメント支援」があります。その一環として、地域の関係機関や専門職が集まり、個別事例の検討や地域課題の把握を行う「地域ケア会議」を開催することが定められています。
2は施設(介護老人福祉施設など)の介護支援専門員の業務です。3の申請は本人・家族・市町村長などが「家庭裁判所」に対して行います(センターは相談・支援を行います)。4の設置と5の指導・監督は「市町村」の業務です。
【受験生の皆さんへ】「個別課題の地域課題化」の意味、説明できますか?
教科書に出てくるこのフレーズ、暗記するだけでは意味がわかりにくいですよね。
「ゴミ出しに困っているおばあちゃん」の事例を通して考えると、「なぜ個人の悩みを会議にかける必要があるのか」がスッと理解できます。現場に出た時に役立つ視点を養いましょう。
👉 現場視点で「地域ケア会議」の意義を読む
問題12
Bさん(85歳,男性,要支援1)は,自宅で一人暮らしをしている。最近,物忘れが多くなり,1か月前から地域支援事業の訪問型サービスを利用するようになった。ある日,Bさんが,「これからも自宅で生活したいが,日中,話し相手がいなくて寂しい」と介護福祉職に話した。
次のうち,Bさんに介護福祉職が勧めるサービスとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 2 介護老人福祉施設
- 3 第一号通所事業(通所型サービス)
- 4 夜間対応型訪問介護
- 5 居宅療養管理指導
答え:3
解説:
Bさんは要支援1で、「自宅で生活したい」「日中、話し相手がいなくて寂しい」というニーズを持っています。このニーズに応えるサービスとして、介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)の「第一号通所事業(通所型サービス)」が最も適切です。これにより、日中に通いの場で他者と交流し、孤立感を解消しながら介護予防に取り組むことができます。
1や2は施設入所サービスであり、Bさんの「自宅で生活したい」という希望に反します。4は夜間のサービス、5は医師などによる医学的管理のサービスであり、Bさんの現在のニーズとは異なります。
【受験生の皆さんへ】「第一号通所事業」…名前が硬すぎませんか?
制度の名称を丸暗記するのは大変ですが、「要支援のおじいちゃんが、寂しさを埋めるために通う場所」とイメージすれば、その役割が一発で理解できます。
利用者の「生活の願い」と「制度」を結びつける、現場視点の解説を読んでみませんか?
👉 現場のエピソードで「通所型サービス」を理解する
問題13
介護保険制度に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 第1号被保険者の保険料は,都道府県が徴収する。
- 2 第1号被保険者の保険料は,全国一律である。
- 3 第2号被保険者の保険料は,年金保険の保険料と合わせて徴収される。
- 4 財源には,第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。
- 5 介護保険サービスの利用者負担割合は,一律,1割である。
答え:4
解説:
介護保険の財源は、約半分が公費(国・都道府県・市町村)で、残り半分が保険料です。この保険料は、「第1号被保険者(65歳以上)」の保険料と「第2号被保険者(40~64歳)」の保険料によって賄われています。したがって、4が正解です。
1の徴収は「市町村」が行います。2の保険料は、市町村ごとに必要な介護費用を見込んで算出されるため、一律ではありません。3は「医療保険」の保険料と合わせて徴収されます。5は所得に応じて1割、2割、3割のいずれかの負担割合が適用されます。
【受験生の皆さんへ】「公費50%・保険料50%」の数字、丸暗記で苦戦していませんか?
数字を覚える前に、「給与明細から引かれる保険料」と「親が使うサービス」をイメージしてください。
「なぜ現役世代からも徴収するのか?」という支え合いの仕組みを理解すれば、複雑な財源構成図も自然と頭に入ってきます。
👉 「自分事」として介護保険の財源を理解する
問題14
障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 2024 年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は,2.5%である。
- 2 精神障害者は,法定雇用率の対象から除外されている。
- 3 2024 年度(令和6年度)に,障害者の雇用義務が生じるのは,従業員101人以上の事業主である。
- 4 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。
- 5 2024 年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は,2023年度(令和5年度)以前と同じである。
答え:1
解説:
障害者雇用促進法に基づく民間企業の法定雇用率は、段階的に引き上げられています。2024年(令和6年)4月1日からは、従来の2.3%から2.5%に引き上げられました。したがって、1が正しい記述です。
2の精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の所持者であれば算定対象に含まれます。3の雇用義務が生じる事業主は、法定雇用率2.5%に基づき、従業員40.0人以上の事業主となります。4は2024年4月から、週10時間以上20時間未満の重度身体・知的障害者、精神障害者も「0.5人」として算定対象に加わりました。5の助成金なども法改正に伴い見直しされています。
【受験生の皆さんへ】「2.5%」の数字、ただの暗記で終わらせていませんか?
この数字の向こう側には、「働きたいけれど勇気が出ない」と迷っている高齢者や障害者の姿があります。
「なぜ国は雇用率を引き上げたのか?」その社会的背景を理解することで、無機質な数字が「希望の数字」に見えてくるはずです。
👉 家族の視点で「障害者雇用」の現在地を読む
問題15
「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。
- 1 介護給付費の支給を受けるときに,障害支援区分の認定は不要である。
- 2 短期入所は介護給付の1つである。
- 3 地域生活支援事業は,国が実施主体である。
- 4 自立支援給付は応益負担である。
- 5 行動援護は訓練等給付の1つである。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
答え:2
解説:
障害者総合支援法の自立支援給付は、「介護給付」と「訓練等給付」などに大別されます。「短期入所(ショートステイ)」は、居宅介護や重度訪問介護などと並び、「介護給付」に位置付けられています。よって、2が正解です。
1は間違いで、介護給付の多くは障害支援区分の認定が必要です。3の実施主体は「市町村」が基本です(都道府県も一部実施)。4は、利用したサービスの量に応じる「応益負担」ではなく、利用者の所得や資産に応じた「応能負担」が原則です。5の行動援護も「介護給付」の一つです。
【受験生の皆さんへ】「介護給付」の分類、機械的に暗記していませんか?
短期入所がなぜ「訓練」ではなく「介護」の給付に含まれるのか。
それは、在宅介護を支える家族のレスパイト(休息)が、利用者の生活維持に直結するからです。「家族の限界を防ぐ」という現場の視点を持つと、制度の分類が自然と頭に入ります。
👉 家族の視点で「ショートステイ」の重要性を読む
問題16
障害児支援に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 サービスを受けるには,療育手帳の取得が必要である。
- 2 放課後等デイサービスは,子ども・子育て支援法に基づく支援である。
- 3 障害児通所支援の利用には,障害児支援利用計画の作成は不要である。
- 4 障害児入所支援は,すべての市町村が実施主体である。
- 5 保育所等訪問支援は,保育所等を訪問し,障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。
答え:5
解説:
「保育所等訪問支援」は、障害のある児童が集団生活を営む施設(保育所、幼稚園、小学校など)を支援員が訪問し、その児童が施設で安定した集団生活を送れるように専門的な支援(本人への支援、訪問先スタッフへの助言など)を行うサービスです。選択肢5は、この内容を正しく説明しています。
1は、療育手帳がなくても、医師の意見書などで支援の必要性が認められれば利用可能です。2の放課後等デイサービスは「児童福祉法」に基づく支援です。3は、通所支援の利用にあたり「障害児支援利用計画」の作成が必要です。4の実施主体は「都道府県」です。
【受験生の皆さんへ】「保育所等訪問支援」のイメージ、湧いていますか?
字面だけ見ると難しそうですが、要は「プロが現場に出張して、本人と先生を助けるサービス」のことです。
「なぜ通所ではなく訪問なのか?」そのメリットを家族の視点から理解することで、制度の目的がストンと腑に落ちるはずです。
👉 家族の視点で「訪問支援」のメリットを読む
問題17
次の記述のうち,サービス付き高齢者向け住宅に関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 「高齢者住まい法」に基づく,高齢者のための住まいである。
- 2 65 歳以上の者が,市町村の措置によって入居する。
- 3 認知症高齢者を対象とした,共同生活の住居である。
- 4 食事サービスの提供が義務づけられている。
- 5 介護サービスの提供が義務づけられている。
(注) 「高齢者住まい法」とは,「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のことである。
答え:1
解説:
「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)に基づいて都道府県に登録される、バリアフリー構造等を備えた高齢者向けの賃貸住宅です。よって、1が正解です。
2は、市町村の措置ではなく、事業者との「賃貸借契約」により入居します。3は認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の説明です。4の食事サービスや5の介護サービスは、提供する住宅もありますが、義務ではありません。義務付けられているのは安否確認と生活相談サービスです。
【受験生の皆さんへ】「高齢者住まい法」…法律名だけでアレルギーが出ていませんか?
法律の名称よりも大切なのは、「なぜこの住宅が必要とされているのか」という利用者のニーズです。
「老人ホームは嫌だけど、一人は不安」という高齢者の揺れる心を知れば、制度の中身が自然と理解できるようになります。
👉 家族の視点で「サ高住」の魅力を読む
問題18
Cさん(60歳,男性)は,休日に自宅で趣味の家庭菜園の作業中に脳出血(cerebral hemorrhage)を起こして救急搬送された。特に麻まひ痺はなく,その後,リハビリテーション病院に転院した。現在は,高次脳機能障害(higher brain dysfunction)の治療とリハビリテーションに専念している。
医療費を支払うときにCさんが利用する制度として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 介護保険制度
- 2 労働者災害補償保険制度
- 3 雇用保険制度
- 4 医療保険制度
- 5 年金制度
答え:4
解説:
Cさんは脳出血という「疾病」の治療と、それに伴う高次脳機能障害のリハビリテーションを「病院」で受けています。このように病気やケガの治療・リハビリテーションにかかる費用は、原則として「医療保険制度」(健康保険や国民健康保険など)によって給付されます。
1の介護保険は、Cさんが60歳(第2号被保険者)のため脳出血が特定疾病に該当しますが、治療そのものではなく介護サービスが対象です。2の労災保険は業務中・通勤中の災害が対象ですが、今回は休日・趣味の作業中です。3は失業時、5は老齢・障害・遺族の場合に給付される制度です。
【受験生の皆さんへ】事例問題、迷わず解けていますか?
「60歳」「趣味の最中」「リハビリ中」。問題文に散りばめられたヒントから、瞬時に適切な制度を選び出す力は、現場での相談援助でも必須のスキルです。
「なぜ介護保険ではなく医療保険なのか」を、患者さんの生活背景から理解するコラムを読んでみましょう。
👉 家族の視点で「医療費と保険制度」を理解する
こころとからだのしくみ
問題19
次のうち,恐怖や不安,喜びなどの情動に関わる脳の機能局在の部位として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 扁桃体
- 2 小脳
- 3 下垂体
- 4 海馬
- 5 視床下部
答え:1
解説:
脳の大脳辺縁系にある扁桃体は、恐怖、不安、喜び、悲しみといった「情動(感情)」の発生や処理に中心的な役割を担う部位です。危険を察知したり、快・不快を判断したりする機能に関わっています。
2の小脳は主に運動の調節や平衡感覚、4の海馬は記憶の形成、5の視床下部は自律神経やホルモン分泌の調節、3の下垂体は視床下部の指令を受けてホルモンを分泌する器官であり、情動の中心的役割とは異なります。
【受験生の皆さんへ】「扁桃体=情動」と丸暗記していませんか?
アーモンドの形をしたこの小さな部位が、現場でよく見る「感情失禁」や「易怒性(怒りっぽさ)」の正体だと知ると、利用者の行動が違って見えてきます。
「なぜ高齢者はキレやすくなるのか?」そのメカニズムを生活の視点から理解するコラムを読んでみましょう。
👉 家族の視点で「脳と感情」の関係を読む
問題20
次のうち,顔の感覚に関与する脳神経として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 嗅神経
- 2 三叉神経
- 3 顔面神経
- 4 迷走神経
- 5 舌下神経
答え:2
解説:
三叉神経は、主に顔面(額、頬、あご)の皮膚感覚(触覚、圧覚、痛覚、温度覚)を脳に伝える役割と、咀嚼筋(噛む筋肉)を動かす運動の役割を担っています。したがって、顔の「感覚」に関与するのは2の三叉神経です。
1の嗅神経は嗅覚(におい)、3の顔面神経は主に顔の「表情筋を動かす」運動や味覚(舌の前方2/3)、4の迷走神経は内臓の感覚や運動、5の舌下神経は舌を動かす運動に関与します。
【受験生の皆さんへ】「三叉神経」と「顔面神経」、どっちが感覚?
丸暗記だと混同しやすいこの2つ。「三叉神経痛=痛い(感覚)」、「顔面麻痺=動かない(運動)」という具体的な症状とセットで覚えれば、もう迷うことはありません。
「なぜ食事介助で麻痺側の確認が必要なのか」という実践的な視点が身につくコラムを読んでみましょう。
👉 家族の視点で「顔の神経トラブル」を理解する
問題21
次の記述のうち,鼻の構造と機能として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 鼻腔は前鼻道・中鼻道・後鼻道に分かれる。
- 2 鼻毛は塵や埃を除去する。
- 3 鼻腔の奥は喉頭に直接つながっている。
- 4 鼻腔には毛細血管は少ない。
- 5 嗅細胞は外鼻孔にある。
答え:2
解説:
鼻腔の入り口にある鼻毛は、吸い込んだ空気に含まれる比較的大きな塵や埃、花粉などを物理的に除去するフィルターの役割を果たしています。よって、2が正解です。
1の鼻腔は、鼻甲介というヒダによって「上鼻道・中鼻道・下鼻道」に分かれます。3の鼻腔の奥は「咽頭」につながり、その下が喉頭になります。4の鼻腔粘膜には毛細血管が豊富にあり、吸気を温める役割を担っています。5の嗅細胞は鼻腔の天井部分(嗅上皮)にあります。
【受験生の皆さんへ】解剖学の図を見て溜息をついていませんか?
鼻腔の構造や機能、丸暗記は退屈ですよね。でも、「なぜ高齢者は肺炎になりやすいのか?」という視点を持つと、鼻毛や加湿機能の重要性がリアルに理解できます。
身近な生活の話題から、身体の仕組みを紐解くコラムを読んでみましょう。
👉 家族の視点で「鼻の機能」を理解する
問題22
次のうち,歯周病(periodontal disease)の症状として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 歯のくぼみの形成
- 2 歯の硬組織の軟化
- 3 歯髄の炎症・疼痛
- 4 歯のエナメル質の侵食
- 5 歯周ポケットの形成
答え:5
解説:
歯周病は、歯と歯肉(歯茎)の境目に付着したプラーク(歯垢)によって歯肉に炎症が起こる疾患です。進行すると、歯と歯肉の間の溝(歯周ポケット)が深くなっていきます。これが歯周病の典型的な症状の一つです。
1、2、3、4は、主にう蝕(虫歯)の症状や進行過程(歯が溶ける、神経が痛むなど)を示しています。
【受験生の皆さんへ】「歯周ポケット」をただの溝だと思っていませんか?
なぜこの溝ができることが「適切な症状」として選ばれるのか。それは、ここが細菌の温床となり、誤嚥性肺炎などの全身疾患につながるスタート地点だからです。
「口の中の菌が命を奪う」というリスクを知ることで、口腔ケアの重要性がより深く理解できます。
👉 家族の視点で「歯周病と肺炎」の関係を読む
問題23
Aさん(78歳,女性)は,友人から口臭を指摘されて悩んでいる。また,食事をするときに,「水分と一緒に食べないと飲み込みにくい」とも話している。Aさんに歯の欠損,麻痺はなく,ストレスの訴えもない。
次のうち,Aさんのからだの中で,機能低下が考えられるものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 咀嚼
- 2 蠕動運動
- 3 嗅覚
- 4 唾液分泌
- 5 胃液分泌
答え:4
解説:
唾液には、口腔内を浄化して口臭を防ぐ作用(自浄作用)や、食物と混ざり合って食塊(食べ物のまとまり)を形成し、飲み込みやすくする(嚥下を助ける)作用があります。Aさんの「口臭」と「水分がないと飲み込みにくい」という訴えは、どちらも唾液分泌の機能低下によって説明できます。高齢になると唾液の分泌量が減少することが多いため、4が最も適切です。
1の咀嚼は歯の欠損がないため、2の蠕動運動や5の胃液分泌は飲み込みにくさや口臭の直接的な原因とは考えにくいです。3の嗅覚低下は口臭を自覚しにくくする要因にはなりますが、訴えの直接の原因ではありません。
【受験生の皆さんへ】「唾液=消化作用」だけで満足していませんか?
唾液には抗菌、中和、潤滑など多くの役割があります。「Aさんはなぜ口臭を気にしているのか?」「なぜ水がないと食べにくいのか?」
症状から身体機能の低下を逆引きで推測するプロセスは、現場で最も使う思考回路です。コラムで実践的なイメージを掴みましょう。
👉 家族の視点で「ドライマウスのリスク」を読む
問題24
皮膚の構造に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 表皮の厚さは平均2.0mmである。
- 2 真皮には角質層がある。
- 3 外界と接する組織は表皮である。
- 4 皮脂腺は皮下組織にある。
- 5 表皮の最表面は基底層である。
答え:3
解説:
皮膚は外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」の3層構造になっています。そのうち、最も外側にあって外界と直接接しているのが表皮です。表皮は外部の刺激から体を守るバリア機能などを担っています。
1の表皮の厚さは平均約0.2mm(部位により異なる)であり、2.0mmは厚すぎます。2の角質層は表皮の最も外側の層です。4の皮脂腺は真皮に存在します。5の表皮の最表面(一番外側)は「角質層」であり、「基底層」は表皮の一番内側(真皮との境界)にあります。
【受験生の皆さんへ】「表皮・真皮・皮下組織」の順序、丸暗記で終わっていませんか?
「なぜ高齢者には剥離トラブルが多いのか?」「なぜ保湿が必要なのか?」
表皮が外界と接する「バリアの最前線」であるという役割を理解していれば、スキンケアの必要性や褥瘡(床ずれ)のリスク管理まで、知識が芋づる式につながります。
👉 家族の視点で「高齢者の皮膚の特徴」を読む
問題25
次のうち,高齢者が嗜好や温度覚の低下によって高温浴を希望した場合に,説明すべき高温浴の特徴として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 血圧の上昇
- 2 腸蠕動の促進
- 3 腎機能の促進
- 4 副交感神経の亢進
- 5 心機能の抑制
答え:1
解説:
高温浴(熱いお湯、目安として42℃以上)に入ると、交感神経が刺激され、血管が収縮しやすくなるため、血圧が上昇します。また、心臓の拍動も速くなり、心臓への負担が大きくなります。高齢者は温度覚が低下し熱い湯を好みやすい一方で、血圧変動のリスクも高いため、この特徴を説明する必要があります。
2の腸蠕動の促進、4の副交感神経の亢進は、主にぬるめのお湯(微温浴)によるリラックス効果です。3の腎機能や5の心機能は、高温浴によって促進・抑制されるのではなく、負担がかかる状態となります。
【受験生の皆さんへ】自律神経の働き、丸暗記で混乱していませんか?
「交感神経=興奮=血圧上昇」。言葉で覚えるよりも、「熱湯風呂に入ったおじいちゃんの体の中で何が起きているか」をイメージする方が、記憶に深く定着します。
現場で役立つリスク管理の視点を、コラムで養いましょう。
👉 家族の視点で「入浴と血圧」の関係を読む
問題26
次のうち,食物の栄養素の大部分を吸収する部位として,正しいものを1 つ選びなさい。
- 1 胃
- 2 小腸
- 3 直腸
- 4 横行結腸
- 5 S状結腸
答え:2
解説:
食物の消化・吸収の過程において、栄養素(糖質、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなど)の大部分は、小腸(十二指腸、空腸、回腸)の広い表面積(絨毛)から吸収されます。よって、2が正解です。
1の胃は主に食物を消化(たんぱく質の分解)する場所で、アルコールなどを除き、栄養素の吸収はほとんど行いません。3、4、5の大腸(直腸、横行結腸、S状結腸を含む)は、主に水分と一部のミネラル(電解質)を吸収する場所です。
【受験生の皆さんへ】解剖生理学、図を見るだけで眠くなっていませんか?
小腸や大腸の機能を丸暗記するのは退屈ですが、「なぜ高齢者は食べているのに痩せるのか?」という疑問と結びつければ、臓器の役割がリアルに見えてきます。
現場で役立つ栄養ケアの視点を、コラムで養いましょう。
👉 家族の視点で「小腸の働き」を理解する
問題27
次の記述のうち,レム睡眠に関するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 記憶を整理し,定着させる。
- 2 脳を休息させる。
- 3 入眠初期に出現する。
- 4 成長ホルモンの分泌を促す。
- 5 深い眠りの状態である。
答え:1
解説:
睡眠には、深い眠りの「ノンレム睡眠」と、浅い眠りの「レム睡眠」があります。レム睡眠中は、体は休息していますが脳は活動しており、この間に日中の体験や学習した内容が整理され、記憶として定着させられると考えられています。よって、1が正解です。
2の「脳を休息させる」、4の「成長ホルモンの分泌」、5の「深い眠り」は、いずれもノンレム睡眠(特に深い段階)の特徴です。3の入眠初期には、まずノンレム睡眠が出現します。
【受験生の皆さんへ】「レム睡眠=急速眼球運動」と丸暗記していませんか?
言葉の意味を覚えるだけでなく、「なぜ高齢者は夢の話をよくするのか?」「なぜ睡眠が認知症予防に大事なのか?」と結びつけることで、知識が現場で使える知恵に変わります。
👉 家族の視点で「睡眠と記憶」の関係を読む
問題28
Bさん(76歳,男性)は,この数週間,日中に,「眠い」と訴えている。Bさんは毎日15時にコーヒー1杯を飲み,たばこを1本吸い,21時に就寝する。夜間の睡眠状態を数日間観察すると,睡眠中にぴくぴくと下肢が動いていることがたびたびあった。起床後,手足に異常を感じるかをBさんに確認したが,「特にない」とのことだった。
次のうち,Bさんの睡眠障害の原因として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 ニコチン摂取
- 2 レム睡眠行動障害
- 3 レストレスレッグス症候群
- 4 カフェイン摂取
- 5 周期性四肢運動障害
答え:5
解説:
周期性四肢運動障害は、睡眠中に本人の意思とは関係なく、足(時には腕も)がぴくぴくと周期的に動くことを繰り返す睡眠障害です。この動きによって睡眠が妨げられ、脳が覚醒してしまうため、夜間の睡眠の質が低下し、日中の強い眠気を引き起こします。Bさんの「睡眠中の下肢の動き」と「日中の眠気」という症状から、5が最も疑われます。
3のレストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)は、覚醒時(特に夕方から夜)に脚の不快感があり、動かしたくなる症状が特徴ですが、Bさんは起床後の異常を否定しています。2のレム睡眠行動障害は、夢の内容に反応して大声を出すなどの異常行動がみられます。1や4も睡眠に影響しますが、15時の摂取が21時以降の睡眠に強く影響するとは考えにくく、特徴的な下肢の動きの説明にはなりません。
【受験生の皆さんへ】「自覚症状がない」というヒントを見逃していませんか?
似たような睡眠障害の選択肢が並ぶ中で、決め手になるのはBさんの「起床後、異常を感じない」という発言です。
「本人は気づかないけれど、体は動いている」という病態の特徴を、家族の観察視点から深く理解しましょう。
👉 家族の視点で「足ピク睡眠障害」の特徴を読む
問題29
次のうち,呼吸中枢がある部位として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 大脳
- 2 中脳
- 3 小脳
- 4 延髄
- 5 脊髄
答え:4
解説:
呼吸や心拍、血圧、嚥下など、生命維持に不可欠な中枢機能は、脳幹の一部である「延髄」にあります。呼吸中枢は延髄にあり、血液中の二酸化炭素濃度などを感知して、無意識下でも呼吸運動を自動的に調節しています。
1の大脳は思考や意識、2の中脳は眼球運動や姿勢反射、3の小脳は運動調節、5の脊髄は脳と末梢神経の中継や反射に関わります。
【受験生の皆さんへ】「延髄=生命維持」と丸暗記していませんか?
延髄がダメージを受けるとどうなるか。呼吸が止まり、飲み込めなくなる。
「なぜ誤嚥性肺炎が命取りになるのか」という現場の恐怖感とセットで覚えることで、脳の機能局在がリアルな知識として定着します。
👉 家族の視点で「延髄の役割」を理解する
問題30
次のうち,脳の機能停止を示す徴候に該当するものとして,適切なものを 1つ選びなさい。
- 1 呼吸不全
- 2 溢流性尿失禁
- 3 心停止
- 4 蠕動運動の減弱
- 5 瞳孔散大・対光反射消失
答え:5
解説:
脳の機能が停止(脳死)すると、脳幹が担っていた機能も失われます。対光反射(目に光を当てると瞳孔が小さくなる反射)の中枢は脳幹(中脳)にあるため、脳機能が停止するとこの反射が消失し、瞳孔は開いたまま(散大)の状態になります。これは脳幹機能の停止を示す重要な徴候の一つです。
1の呼吸不全や3の心停止は脳機能停止の結果として起こり得ますが、原因は他にもあり、脳機能停止の直接的な徴候とは限りません。2や4は脳機能停止の直接的な徴候ではありません。
【受験生の皆さんへ】「脳死判定5項目」を丸暗記しようとしていませんか?
なぜ瞳孔を見るのか、なぜ呼吸を確認するのか。一つ一つの検査には「脳のどこの機能が止まったか」を確認する意味があります。
「看取りの現場で何が起きるか」を知ることで、無機質な検査項目が、命の終わりのストーリーとして理解できるようになります。
👉 家族の視点で「最期のサイン」の意味を読む
発達と老化の理解
問題31
次の記述のうち,子どもの標準的な成長として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 1 歳半から2歳ごろに,ハイハイをして移動できるようになる。
- 2 生後9か月から1歳ごろに,指をさして自分の関心や欲求を他者に伝えられるようになる。
- 3 子どもが使う言葉が急に増える語彙爆発は,5歳を過ぎたころに生じる。
- 4 人見知りの反応は,2歳を過ぎたころに生じる。
- 5 イヤイヤをしてすぐに泣く行動は,第二反抗期に生じる。
答え:2
解説:
生後9か月から1歳ごろになると、子どもは興味を持ったものや欲しいものを指さし(指向の指さし)、他者の注意を引こうとする行動(共同注意)が見られるようになります。これは、言語発達の前段階として重要なコミュニケーション手段です。
1のハイハイは、生後7か月から10か月ごろに見られるのが標準的です。3の語彙爆発は、1歳半から2歳ごろに生じます。4の人見知りは、生後6か月から始まり、1歳前後にピークを迎えることが多いです。5のイヤイヤする行動は、自我が芽生える2歳前後の「第一次反抗期」の特徴です(第二反抗期は思春期)。
【受験生の皆さんへ】「指差し=9ヶ月〜1歳」と数字だけで覚えていませんか?
指差しは「共同注意」と呼ばれる、他者とのコミュニケーションの原点です。
赤ちゃんの成長プロセスを知ることは、逆に「言葉を失っていく高齢者との非言語コミュニケーション」を理解するヒントにもなります。発達の不思議をコラムで感じてみましょう。
👉 家族の視点で「指差しの意味」を読む
問題32
次の記述のうち,神経性無食欲症(anorexia nervosa)に関するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 活動性が高まる。
- 2 学童期に最も生じやすい。
- 3 太ることへの恐怖はみられない。
- 4 低体重の深刻さを理解している。
- 5 多くが男性である。
答え:1
解説:
神経性無食欲症は、極端な食事制限や痩せ願望を特徴としますが、栄養不足にもかかわらず、かえって活動性が亢進し、過度な運動を続けるといった行動がみられることが特徴の一つです。
2は学童期ではなく、思春期の女性に最も生じやすいです。3は間違いで、「太ることへの極度な恐怖」が中核的な症状です。4は間違いで、多くの場合、自分の低体重の深刻さを認識できない(病識の欠如)という特徴があります。5は間違いで、患者の多くは女性です。
【受験生の皆さんへ】「神経性無食欲症=活動性亢進」で引っかかっていませんか?
「エネルギーがないはずなのに、なぜ動く?」
その背景にある「痩せ願望による強迫的な行動」や「ボディイメージの歪み」という病理を理解すれば、選択肢に迷うことはなくなります。
👉 家族の視点で「拒食症のパラドックス」を読む
問題33
Aさん(73歳,男性)は,会社の役員として勤めていたが,3年前に退職した。地域の老人クラブへの入会を勧められたが拒否している。毎年,敬老の日に記念品が配布されても,不快感を示して受け取らない。退職後も会社の状況を気にしていて,後輩とときどき連絡をとっている。Aさんは,身体が衰えることに強い不安を感じて,筋力トレーニングを毎日行っている。会社の後輩から,「いつも若々しいですね」と言われることに喜びを感じている。
ライチャード(Reichard, S.)による,引退後の男性の5つの適応タイプのうち,Aさんに相当するものとして,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 外罰(憤慨)型
- 2 内罰(自責)型
- 3 円熟(成熟)型
- 4 自己防衛(装甲)型
- 5 ロッキングチェアー(安楽椅子)型
答え:4
解説:
ライチャードの適応タイプのうち、「自己防衛(装甲)型」は、老いによる不安や無力感を受け入れられず、それに抵抗するために活動的であり続けようとするタイプです。Aさんが老人クラブを拒否し、「若々しい」と言われることを喜び、身体の衰えに不安を感じてトレーニングに励む姿は、老いを認めない「自己防衛」のメカニズムが働いていると考えられます。
1は他者や環境を非難するタイプ、2は自分を責めるタイプ、3は老いを受け入れ穏やかに過ごすタイプ、5は他者に依存し受動的に過ごすタイプであり、Aさんには当てはまりません。
【受験生の皆さんへ】ライチャードの5分類、丸暗記で苦戦していませんか?
「円熟型」「ロッキングチェア型」「装甲型」「憤慨型」「自責型」。
それぞれのタイプを「近所の頑固オヤジ」や「愚痴っぽいお婆ちゃん」など、身近な高齢者に当てはめてイメージすることで、特徴がスッと頭に入ります。
👉 家族の視点で「高齢男性の心理」を読む
問題34
次の記述のうち,結晶性知能に関する説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 感覚や運動に基づく知能である。
- 2 過去に得た知識を活用して問題を解決する能力である。
- 3 40~50歳で急激に低下する。
- 4 知識や文化の影響よりも,生理的な老化の影響を受けやすい。
- 5 その場で新しい問題を解決する能力である。
答え:2
解説:
結晶性知能とは、教育や学習、経験などから獲得した知識や判断力を活用する能力のことです。過去の知識を応用して問題を解決する能力であり、2が正しい説明です。
3、4のように急激に低下したり、生理的老化の影響を受けやすかったりするのは「流動性知能」の特徴です。結晶性知能は、高齢になっても維持されやすいとされています。5の「新しい問題を解決する能力」も流動性知能の説明です。
【受験生の皆さんへ】「流動性」と「結晶性」、どっちがどっち?
迷ったときは漢字のイメージで覚えましょう。
「流動」=水のように流れて消えていく(加齢で低下)。
「結晶」=時間とともに固まって輝く(加齢で維持)。
「おじいちゃんの知恵袋」のエピソードと結びつければ、もう忘れることはありません。
👉 家族の視点で「高齢者の知能」の特徴を読む
問題35
次の記述のうち,加齢に伴う感覚機能の変化として,最も適切なものを1 つ選びなさい。
- 1 皮膚感覚が敏感になる。
- 2 高音域の聴力が高まる。
- 3 暗順応の時間が延長する。
- 4 味覚が敏感になる。
- 5 嗅覚が敏感になる。
答え:3
解説:
暗順応とは、明るい場所から暗い場所に入ったときに、徐々に暗闇に目が慣れて見えるようになる機能です。加齢に伴い、瞳孔の反応が遅くなったり、網膜の機能が低下したりするため、この暗順応にかかる時間が長く(延長)なります。
1の皮膚感覚(触覚・痛覚・温度覚など)、2の聴力(特に高音域)、4の味覚(特に塩味や甘味)、5の嗅覚は、いずれも加齢に伴って「鈍化(低下)」する傾向があります。
【受験生の皆さんへ】「暗順応の延長」を文字だけで記憶していませんか?
この知識の裏には、「夜中のトイレで転倒し、骨折してしまう高齢者」のリスクが隠されています。
「なぜ高齢者住宅には足元灯が必要なのか?」という根拠を体の仕組みから理解することで、丸暗記ではない生きた知識が身につきます。
👉 家族の視点で「目の老化と転倒」の関係を読む
問題36
Bさん(74歳,女性)は,地方で一人暮らしをしている。持病はなく,認知機能の異常もない。ダンスサークルに通い,近所との付き合いも良好で,今の暮らしに満足している。最近,白髪が増え,友人との死別もあり,年をとったと感じている。ある日,一人息子(50歳,未婚)から,東京で一緒に住むことを提案された。Bさんは,「ここには知り合いがいるが,東京には誰もいない。ここが一番いい」と言った。すると息子は,Bさんに,「年をとると頑固になる。あと数年したら認知症(dementia)になるかもしれないので,自分と一緒に暮らすべきだ」と言った。
次のうち,Bさんに関する記述として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 Bさんには,老性自覚はみられない。
- 2 Bさんには,友人との死別による悲嘆がみられる。
- 3 Bさんは,今,住んでいる環境や生活に適応できていない。
- 4 Bさんには,エイジズム(ageism)の考え方がみられる。
- 5 Bさんには,住み慣れた環境や仲間を喪失することへの不安がみられる。
答え:5
解説:
Bさんは、息子の同居の提案に対し、「ここには知り合いがいるが、東京には誰もいない」と述べています。これは、現在の良好な人間関係や住み慣れた環境を離れること、つまりそれらを「喪失」することへの不安や抵抗感を示していると解釈できます。
1は間違いです。「白髪が増え、友人との死別もあり、年をとったと感じている」という記述から、Bさんには老性自覚(自分が年をとったという自覚)がみられます。2は「暮らしに満足している」とあり、悲嘆に暮れている様子はありません。3は「満足している」「付き合いも良好」とあり、十分に適応できています。4のエイジズム(年齢による偏見)は、「年をとると頑固になる」「認知症になる」と決めつけている「息子」の側にみられる考え方です。
【受験生の皆さんへ】「喪失体験」という言葉、暗記だけで済ませていませんか?
住み慣れた家を離れることが、高齢者にとってどれほど大きなストレスか。Bさんの事例を通して想像することで、「環境移行時の支援」の重要性が深く理解できます。
教科書の知識を、生きた人間ドラマとして捉え直すコラムを読んでみましょう。
👉 家族の視点で「同居拒否の心理」を読む
問題37
次の記述のうち,サクセスフル・エイジング(successful aging)として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 長生きすることが,最大の目的である。
- 2 一人暮らしで,周囲の人と交流をしないようにしている。
- 3 膝に痛みがあるので,一日中ベッド上で過ごすようにしている。
- 4 難聴があるので,補聴器をつけてパソコン教室に通い始めた。
- 5 歌を上手に歌えなくなったので,カラオケに誘われても行かないようにしている。
答え:4
解説:
サクセスフル・エイジングとは、加齢による変化や困難(病気や機能低下)を受け入れつつも、それにうまく適応し、能動的に社会参加を続けるなどして、質の高い老後を送ることを指します。4は、「難聴」という機能低下に対し「補聴器」という手段で適応し、「パソコン教室に通う」という新たな社会参加・学習に能動的に取り組んでおり、サクセスフル・エイジングの典型例です。
1は長寿(量)のみを目的としており、生活の質(サクセスフル)とは異なります。2、3、5は、社会との交流を避けたり、機能低下を理由に活動をやめてしまったりする「非活動的な」状態であり、不適応な例です。
【受験生の皆さんへ】「サクセスフル・エイジング」をただのカタカナ語にしていませんか?
「成功した加齢」と直訳するだけでは、現場での意味を見失います。
身体機能が低下しても、補聴器などの道具を使って社会参加し続けること。その「適応する姿」こそが答えなのだと、具体的なイメージで理解を深めましょう。
👉 家族の視点で「幸せな老後」の具体例を読む
問題38
次のうち,老年症候群に直接関わる疾患として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 高血圧症(hypertension)
- 2 糖尿病(diabetes mellitus)
- 3 骨粗鬆症(osteoporosis)
- 4 心筋梗塞(myocardial infarction)
- 5 脂質異常症(dyslipidemia)
答え:3
解説:
老年症候群とは、高齢期に多くみられ、日常生活機能の低下や生活の質の低下をきたす症候群(例:転倒、骨折、失禁、低栄養、認知機能低下、フレイルなど)の総称です。骨粗鬆症は、骨がもろくなる疾患であり、転倒による骨折(特に大腿骨頸部骨折など)の直接的な原因となります。骨折は、寝たきりやフレイル(虚弱)といった老年症候群の主要な状態に直結するため、3が最も適切です。
1、2、4、5は生活習慣病であり、老年症候群のリスク因子(間接的な原因)とはなりますが、骨粗鬆症ほど直接的に転倒・骨折・寝たきりという症候群に関わるものではありません。
【受験生の皆さんへ】「老年症候群」を丸暗記しようとしていませんか?
高血圧や糖尿病といった「生活習慣病」との違いは何か。
それは、骨粗鬆症による骨折が「生活機能(ADL)の低下に直結する」という点です。「なぜこれが老年症候群に含まれるのか?」という理由を、生活の視点から理解しましょう。
👉 家族の視点で「骨粗鬆症のリスク」を読む
認知症の理解
問題39
次の記述のうち,2019年(令和元年)の認知症施策推進大綱に関する説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していく。
- 2 「予防」とは,「認知症(dementia)にならない」という意味である。
- 3 「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」を推進する7つの柱が示された。
- 4 「普及啓発・本人発信支援」として,家族が積極的に本人の意思を代弁することが示された。
- 5 策定後は,毎年施策の進捗を確認することが示された。
答え:1
解説:
認知症施策推進大綱では、認知症の人が尊厳と希望を持って暮らせる社会(共生)を目指すとともに、認知症の発症を遅らせる取り組み(予防)を進めることを基本理念としており、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進することが示されています。
2の「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味で用いられています。3は5つの柱(普及啓発・本人発信支援、予防、医療・ケア・介護サービス・介護者支援、認知症バリアフリー・住まい・生活環境、研究開発・産業促進・国際展開)が示されました。4は家族の代弁ではなく「本人」が自ら発信することを支援します。5は毎年ではなく、定期的に(おおむね3年ごと)施策の進捗を確認し、見直すこととされています。
【受験生の皆さんへ】「施策推進大綱」なんて漢字ばかりで嫌になりますよね。
でも、この法律の裏には「認知症になっても絶望しないでほしい」という国からのメッセージが込められています。
「なぜ予防だけでなく共生が必要なのか?」を家族の視点から理解することで、無機質な制度論が温かい知識に変わります。
👉 家族の視点で「共生と予防」の真意を読む
問題40
Aさん(84歳,女性,要介護3)は,アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)で,介護老人福祉施設に入所している。赤ちゃんの人形を持っていて,「はなちゃん」と呼んで話しかけている。昼食のため,介護福祉職が居室を訪問すると,Aさんは不安そうな顔で,「はなちゃんがいなくなった。どこへ連れて行ったの?返して」と大声を出した。人形はAさんのロッカーの上に置かれていた。
Aさんに対する介護福祉職の最初の声かけとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 「私を疑っているんですか」
- 2 「置いた場所を忘れたんですか」
- 3 「心配ですね,一緒に探しませんか」
- 4 「ご飯を食べてから探してはどうですか」
- 5 「ロッカーの上にあるのが見えないんですか」
答え:3
解説:
Aさんは、大切にしている人形(はなちゃん)が見当たらず、「いなくなった」と強い不安を感じています。このような「物盗られ(探し物)」の訴えに対しては、まず「心配ですね」とAさんの不安な気持ちに寄り添い、受容・共感することが最も重要です。その上で「一緒に探しませんか」と共同で問題解決にあたる姿勢を見せることで、Aさんの不安を和らげ、信頼関係を築くことができます。
1、2、5は、Aさんの訴えを否定したり、問い詰めたり、能力の低下を指摘したりする不適切な対応であり、Aさんの不安や混乱を強めてしまいます。4はAさんの現在の強い訴えを後回しにしており、食事どころではなくなってしまう可能性があります。
【受験生の皆さんへ】「事実を指摘する」のは、なぜ不正解なのでしょうか?
Aさんの事例では、人形はロッカーの上に見えています。それでも「そこにあるでしょ」と言ってはいけない理由。
それは、利用者が求めているのが「人形の場所」ではなく「喪失感への共感」だからです。家族心理の視点から解説を読み、深い理解につなげましょう。
👉 家族の視点で「物盗られ妄想への対応」を読む
問題41
認知症(dementia)の高齢者にみられる,せん妄に関する記述として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 覚醒レベルが重度に低下した状態である。
- 2 症状の変動が少ないことが特徴である。
- 3 夜間よりも日中に生じやすいことが特徴である。
- 4 認知機能障害がみられることはまれである。
- 5 関与する因子を特定することが重要である。
答え:5
解説:
せん妄は、急性に発症する意識障害(意識混濁)であり、幻覚、妄想、興奮などの症状を伴います。その背景には、身体疾患(感染症、脱水、低酸素など)、薬剤の影響、環境の変化(入院など)といった様々な「関与する因子」が存在することがほとんどです。そのため、せん妄に対応する際は、これらの原因となっている因子を特定し、それを取り除くことが最も重要となります。
1は覚醒レベルの低下(意識混濁)はみられますが、傾眠から興奮まで幅があり「重度」とは限りません。2は症状が1日の中でも変動しやすい(日内変動)のが特徴です。3は「夜間」に生じやすい(夜間せん妄)のが特徴です。4は注意障害や見当識障害といった認知機能障害を伴います。
【受験生の皆さんへ】「せん妄=意識障害」と丸暗記していませんか?
教科書の定義だけでなく、「なぜ原因(因子)の特定が重要なのか?」という視点を持つことが大切です。
「脱水ケアをしたら治った!」という現場の成功体験と結びつけることで、無機質な選択肢が生きた知識として定着します。
👉 家族の視点で「せん妄の原因探し」を読む
問題42
次の記述のうち,アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)の特徴として,適切なものを1つ選びなさい。
- 1 近時記憶(新しい記憶)の障害は,初期から始まる。
- 2 特徴的な症状として幻視がある。
- 3 脳にアミロイドβが沈着し始めると,すぐに発症する。
- 4 歩行障害が多く現れるのは,初期の段階である。
- 5 嚥下障害が多く現れるのは,初期の段階である。
答え:1
解説:
アルツハイマー型認知症は、脳の海馬(記憶を司る部位)の萎縮が早期から始まるため、「さっきの出来事を忘れる」「同じことを何度も聞く」といった近時記憶(新しい記憶)の障害が、初期段階から顕著にみられることが特徴です。
2の幻視(特に具体的でリアルな幻視)は、レビー小体型認知症の特徴的な症状です。3のアミロイドβの沈着は、発症の10~20年も前から始まるとされており、沈着が始まってもすぐには発症しません。4の歩行障害や5の嚥下障害は、主に中期から末期にかけて現れる症状です。
【受験生の皆さんへ】「幻視=レビー小体型」「近時記憶=アルツハイマー型」。
この病気ごとの特徴的な症状(中核症状)を区別できていますか?
丸暗記するのではなく、「海馬が萎縮するから新しいことが覚えられない」という脳のメカニズムとセットで理解することで、現場で使える確かな知識になります。
👉 家族の視点で「アルツハイマーの初期症状」を読む
問題43
次のうち,認知症(dementia)のリスクを高める要因として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 身体活動
- 2 不飽和脂肪酸の摂取
- 3 歯がなくなることによる咀嚼機能の低下
- 4 難聴による補聴器の使用
- 5 ボランティア活動
答え:3
解説:
歯が失われ、咀嚼機能(噛む力)が低下すると、脳への血流や刺激が減少したり、食事内容が偏り低栄養になったりすることが、認知症の発症リスクを高める要因になると指摘されています。
1の身体活動(運動)、2の不飽和脂肪酸(魚油など)の摂取、4の補聴器の使用(難聴はリスク要因だが、補聴器の使用はリスクを低減させる)、5のボランティア活動(社会参加)は、いずれも認知症のリスクを「低下させる(予防に寄与する)」要因と考えられています。
【受験生の皆さんへ】「咀嚼機能の低下」を選択肢から選べましたか?
認知症のリスク要因には、運動不足や難聴など様々なものがありますが、「口の中の健康」も見逃せないポイントです。
「なぜ噛むことが脳に良いのか?」というメカニズムを知ることで、口腔ケアの重要性がより深く理解できます。
👉 家族の視点で「噛むことと脳」の関係を読む
問題44
次のうち,全般的な認知機能を評価する尺度であり,30点満点で20点以下を認知症の目安とするものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 バーセルインデックス(Barthel Index)
- 2 改訂長谷川式認知症スケール(HDS-R)
- 3 FAST(Functional Assessment Staging)
- 4 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
- 5 臨床的認知症尺度(CDR:Clinical Dementia Rating)
答え:2
解説:
改訂長谷川式認知症スケール(HDS-R)は、見当識、記憶、計算、言語機能などを評価するための9項目の質問で構成される、全般的な認知機能の評価尺度です。30点満点であり、20点以下の場合に認知症の疑いが強いと判定する目安として広く用いられています。
1のバーセルインデックスはADL(日常生活動作)の評価尺度です。3のFASTと5のCDRは、認知症の重症度(病期)を評価するための尺度です。4の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準は、認知症の状態像や介護の手間を評価する尺度です。
【受験生の皆さんへ】「HDS-R=20点」の丸暗記で終わっていませんか?
大切なのは点数だけでなく、「何(記憶・計算・見当識)を評価しているのか」を理解することです。
「100引く7」がなぜ認知症の検査になるのか。その理由を家族の視点から知ることで、アセスメント(評価)の意味が深く理解できます。
👉 家族の視点で「認知症検査」の中身を読む
問題45
次の記述のうち,「認知症(dementia)の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年(平成30年)(厚生労働省))で示されている,意思決定支援として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 認知症(dementia)の人の家族の意思を支援することである。
- 2 意思決定支援者は特定の職種に限定される。
- 3 一度,意思決定したら,最後まで同じ内容で支援する。
- 4 看取りの場面になってから支援を開始する。
- 5 身振りや表情の変化も意思表示として読み取る努力を最大限に行う。
答え:5
解説:
このガイドラインでは、認知症の人の意思決定支援において、本人が言葉でうまく意思を伝えられない場合でも、支援者はその人の身振り、手振り、表情の変化、視線、声の調子などを「本人の意思表示のサイン」として最大限読み取り、その意思を尊重する努力を求めています。
1は家族ではなく、あくまで「本人」の意思決定を支援します。2は特定の職種に限定されず、本人に関わる全ての人が支援者となります。3は本人の意思は状況や体調によって変化しうるため、繰り返し確認し支援することが重要です。4は看取りだけでなく、日常生活のあらゆる場面(今日の服装、食事のメニューなど)で支援が必要です。
【受験生の皆さんへ】「意思決定支援」を難しく考えすぎていませんか?
ガイドラインの条文を覚えるよりも大切なのは、「言葉を失った人がどうやってNoを伝えているか」に気づく感性です。
家族が日々実践している「察するケア」をヒントに、選択肢5が正解になる理由を深く理解しましょう。
👉 家族の視点で「意思の読み取り方」を学ぶ
問題46
次の記述のうち,回想法として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 肩や背中から優しくゆっくりと触れる。
- 2 共感を通して,認知症(dementia)の人が体験している現実を受け入れる。
- 3 見当識を高めるために,時間や場所,現在の状況を説明する。
- 4 昔の写真や音楽を活用して,記憶を活性化する。
- 5 残存能力を活用し,共同作業を通して仲間をつくる。
答え:4
解説:
回想法は、昔の写真、使い慣れた道具、懐かしい音楽など、過去の記憶を呼び起こすきっかけ(手がかり)を用いて、その人の人生の出来事や思い出を語ってもらう心理療法の一つです。これにより、比較的保たれている昔の記憶を活性化させ、自尊心を高めたり、情緒を安定させたりする効果が期待されます。
1はタクティールケアなどの手法の説明です。2はバリデーション(共感的理解)の基本的な態度の説明です。3はリアリティ・オリエンテーション(現実見当識訓練)の説明です。5は作業療法やレクリエーション活動などの説明に近いものです。
【受験生の皆さんへ】「回想法」と「リアリティ・オリエンテーション」を混同していませんか?
回想法の目的は「人生の肯定的評価」であり、事実の正誤を問うものではありません。
家族がアルバムを開いて「おばあちゃん、いい笑顔だね」と語り合うシーンを想像すれば、選択肢に迷うことはなくなります。
👉 家族の視点で「回想法」の実践例を読む
問題47
次の記述のうち,認知症疾患医療センターの説明として,適切なものを1 つ選びなさい。
- 1 事業の実施主体は,市町村である。
- 2 都道府県ごとに,1か所の設置が義務づけられている。
- 3 認知症(dementia)の鑑別診断を行う。
- 4 主に認知症(dementia)が進行した人の入院治療を行う。
- 5 介護保険法に定められている。
答え:3
解説:
認知症疾患医療センターは、認知症に関する専門医療機関として、保健所、市町村、かかりつけ医などと連携し、専門医療相談や「鑑別診断」(認知症の原因疾患(アルツハイマー型、レビー小体型など)を特定する診断)を行う重要な役割を担っています。また、行動・心理症状(BPSD)への対応なども行います。
1の実施主体(指定を行う者)は、都道府県または指定都市です。2は1か所の義務ではなく、都道府県が医療圏域ごとに指定・整備を進めています。4は急性期治療やBPSDの対応も行いますが、進行した人の長期入院が主目的ではありません。5は介護保険法ではなく、主に医療法や認知症施策推進大綱に基づいて整備されています。
【受験生の皆さんへ】「鑑別診断」という言葉、具体的にイメージできますか?
なぜ普通の病院ではなくセンターに行く必要があるのか。それは、認知症の種類によってケアの方法が全く違うからです。
「最初の診断を間違えないための砦」という視点で理解すると、施設の役割がより鮮明になります。
👉 家族の視点で「専門医療センター」の役割を読む
問題48
Bさん(87歳,男性)は,一人暮らしである。玄関前で,脱水で倒れているところを発見され,救急搬送された。入院中,認知症(dementia)の疑いがある行動が見られた。Bさんは,「自宅で暮らしたい」と強く希望していた。退院後,Bさんは外出して自宅に戻れなくなることがあった。近所の人たちが,Bさんの生活を心配して,地域包括支援センターに相談した結果,認知症初期集中支援チームが編成された。
次の記述のうち,Bさんに対して認知症初期集中支援チームが行う支援として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 金銭管理を行う。
- 2 支援方針を検討する。
- 3 居宅サービス計画書を作成する。
- 4 介護保険サービスを契約する。
- 5 法定後見を行う。
答え:2
解説:
認知症初期集中支援チームは、認知症が疑われるが医療や介護につながっていない人(Bさんのようなケース)やその家族を訪問し、アセスメント(評価)を行います。その上で、本人の状態やニーズに基づき、医療機関への受診や必要な介護サービスの利用につなげるための「支援方針」を検討・作成することが、チームの主な役割です。支援期間はおおむね6か月が目安です。
1、3、4、5(金銭管理、ケアプラン作成、サービス契約、後見)は、支援チームが直接行う業務ではなく、検討された支援方針に基づき、適切な関係機関(日常生活自立支援事業、居宅介護支援事業所、成年後見センターなど)につなげるための調整を行います。
【受験生の皆さんへ】「初期集中支援チーム=金銭管理」で×を選べましたか?
このチームの役割は、あくまで「初期の導入支援(レールに乗せること)」です。成年後見制度のような権利擁護とは役割が異なります。
「拒否があるBさんをどうやってケアにつなげるか?」という現場の困りごとから発想すれば、自然と「支援方針の検討」という正解が見えてきます。
👉 家族の視点で「チームの役割」を理解する
障害の理解
問題49
次のうち,ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health:国際生活機能分類)の社会(人生)レベルに該当するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 心身機能・身体構造
- 2 活動
- 3 参加
- 4 機能障害
- 5 活動制限
答え:3
解説:
ICF(国際生活機能分類)は、人の生活機能を「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つの次元で捉えます。このうち「参加」は、家庭や社会生活、余暇活動など、実生活の場面(人生)に関わることを指し、社会(人生)レベルに該当します。
1は生命レベル、2は個人レベルの次元です。4の機能障害は「心身機能・身体構造」のマイナス面、5の活動制限は「活動」のマイナス面を指す言葉です。
【受験生の皆さんへ】「活動」と「参加」の違い、ごっちゃになっていませんか?
「トイレに行く」は活動、「トイレを使って旅行に行く」は参加。
「それが人生の楽しみにつながるか?」という視点で分類すれば、もう迷うことはありません。現場での目標設定にも役立つ考え方をコラムで学びましょう。
👉 家族の視点で「ICFの参加」を理解する
問題50
次の記述のうち,障害者のエンパワメントに関するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 障害のある人が障害のない人と同等に生活し,活動する社会を目指す。
- 2 専門職が主導し,障害がある人は受動的に支援を受ける。
- 3 障害のある人が自らの能力や長所に気づき,課題に対応する。
- 4 障害のある人が,主体性や人権が守られないことに耐える。
- 5 障害のある人が,医学的リハビリテーションを受ける。
答え:3
解説:
エンパワメントとは、障害のある人自身が、自分の持っている能力(ストレングス)や長所、可能性に気づき、主体的に意思決定し、自らの力で課題を解決・対応していけるように支援する考え方やプロセスを指します。
1はノーマライゼーションやインクルージョンの考え方です。2は専門職主導(パターナリズム)であり、エンパワメントの対極にある考え方です。4は権利を侵害されている状態であり不適切です。5は医療的アプローチの一つであり、エンパワメントそのものではありません。
【受験生の皆さんへ】「エンパワメント」をただのカタカナ語として暗記していませんか?
なぜ「受動的に支援を受ける」ことが不正解なのか。
それは、エンパワメントの本質が「主体性の回復」にあるからです。「私なんて」と自信を失った親御さんが、再び顔を上げる瞬間。そのドラマを想像すれば、この概念が忘れられないものになります。
👉 家族の視点で「エンパワメントの魔法」を読む
問題51
次のうち,クローン病(Crohn disease)にみられる特徴的な症状として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 視力低下
- 2 栄養障害
- 3 咳嗽
- 4 運動失調
- 5 関節痛
答え:2
解説:
クローン病は、口腔から肛門までの消化管のあらゆる部位に炎症や潰瘍が起こりうる原因不明の炎症性腸疾患です。小腸や大腸の粘膜が広範囲に障害されるため、食物の消化・吸収が妨げられ、その結果として低栄養や体重減少といった「栄養障害」が特徴的な症状として現れます。
5の関節痛も合併症として見られることはありますが、消化器症状として最も中心的な問題となるのは2の栄養障害です。1、3、4はクローン病の典型的な症状ではありません。
【受験生の皆さんへ】「クローン病」の症状、丸暗記していませんか?
「消化管全体に炎症が起きる」→「栄養が吸収できない」→「栄養障害になる」。
この因果関係(プロセス)で理解すれば、数ある選択肢の中から迷わず正解を選べるようになります。
👉 家族の視点で「消化器疾患と栄養」の関係を読む
問題52
次の記述のうち,遂行機能障害の特徴として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 些細なことですぐに興奮して怒鳴る。
- 2 新しい知識を覚えることが困難である。
- 3 ぼんやりして周囲に注意を向け続けることが困難である。
- 4 行動を計画して実行することが困難である。
- 5 言葉の表出や理解が困難である。
答え:4
解説:
遂行機能障害は、高次脳機能障害の一つで、目的を持った一連の行動を最後までやり遂げることが困難になる状態を指します。具体的には、行動の「計画を立てる(段取り)」、それを「実行する」、途中で「間違いを修正する」といったことが難しくなります。
1は感情コントロールの障害、2は記憶障害、3は注意障害、5は失語症(言語障害)の説明です。これらも高次脳機能障害に含まれますが、遂行機能障害の定義とは異なります。
【受験生の皆さんへ】「遂行機能障害」という言葉、難しそうに感じていませんか?
要するに「段取りが悪くなること」です。料理や旅行の計画など、日常生活の具体的なエピソードと結びつければ、もう忘れることはありません。
家族の視点から症状を理解し、アセスメント能力を高めましょう。
👉 家族の視点で「段取り障害」の具体例を読む
問題53
視覚障害の特徴と視覚障害者の生活支援に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 ロービジョンは,視覚情報をまったく得られない状態である。
- 2 中途視覚障害者は,先天性の障害に比べて障害を受容しやすい。
- 3 白杖には,視覚に障害があることを周囲に知らせる役目がある。
- 4 視覚障害を補うために,ペットの犬と一緒に外出する。
- 5 視覚障害者は,ガイドヘルパーの利用はできない。
答え:3
解説:
白杖(はくじょう)は、視覚障害のある人が歩行時に路面の状況や障害物を察知する「安全確保(センサー)」の役割と同時に、周囲の人に「視覚に障害があること(シンボル)」を知らせ、配慮を促すという重要な役目を持っています。
1のロービジョンは、視力は低いものの視覚情報をある程度は得られる状態(弱視)を指します。全く得られない状態は「全盲」です。2は逆で、人生の途中で視力を失う中途視覚障害者は、障害受容が困難な場合が多いです。4はペットではなく、専門的な訓練を受けた「盲導犬」です。5はガイドヘルパー(同行援護)は視覚障害者の外出を支援する重要なサービスです。
【受験生の皆さんへ】「ロービジョン」の意味、正しく理解していますか?
「視覚情報が全く得られない」わけではありません。残された視力を使って生活している人もたくさんいます。
「見え方は人それぞれ」という視点を持つことで、白杖やガイドヘルパーの必要性がより深く理解できるようになります。
👉 家族の視点で「白杖の役割」を読む
問題54
Aさん(76歳,女性)は,パーキンソン病(Parkinson disease)と診断され,日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL)は,車いすやベッド上で全介助である。最近,食事に時間がかかって嫌がるようになり,かすれ声が目立つようになった。
次のうち,現在のAさんに対して介護福祉職が留意すべきこととして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 安静時振戦
- 2 筋固縮
- 3 仮面様顔貌
- 4 誤嚥
- 5 便秘
答え:4
解説:
Aさんの「食事に時間がかかって嫌がる」「かすれ声が目立つ」という症状は、パーキンソン病の進行に伴う嚥下(飲み込み)機能の低下を示唆しています。飲み込む力が弱くなると、食べ物や水分が気管に入ってしまう「誤嚥」のリスクが非常に高くなります。誤嚥は窒息や誤嚥性肺炎につながるため、食事介助の際に最も留意すべき点です。
1、2、3、5(振戦、筋固縮、無表情、便秘)もパーキンソン病の代表的な症状ですが、事例の食事場面の状況から最も注意すべきなのは誤嚥です。
【受験生の皆さんへ】「誤嚥」という単語を、リアルな生活場面で想像できますか?
試験問題にある「食事を嫌がる」「かすれ声が目立つ」という情報が、なぜ「誤嚥」という解答につながるのか。
単なる症状の暗記ではなく、高齢者の生活の中でどのようなサインとして現れるかを、家族の視点で深く理解しましょう。
👉 家族の視点で「飲み込みにくさのサイン」を読む
問題55
聴覚障害者の特徴や支援の方法に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 要約筆記によって意思疎通を補う。
- 2 軽度の聴覚障害を「ろう」という。
- 3 フラッシュベルは周囲の音を増幅させて伝える。
- 4 手話は意思の伝達に役立たない。
- 5 両耳の聴力レベルが40dBで身体障害者手帳が交付される。
答え:1
解説:
要約筆記は、話されている内容をその場で要約し、文字にして伝える筆談の一形態です。主に中途失聴者や難聴者など、手話よりも文字による情報を必要とする人にとって、会議や講演会などで意思疎通を補う有効な支援方法です。
2の「ろう」は、聴力が非常に低い(一般に90dB以上)か、全く聞こえない状態(最重度の聴覚障害)を指します。3のフラッシュベルは、音を「光の点滅」に変換して知らせる機器です(音を増幅するのは補聴器)。4の手話は、ろう者にとって重要な意思伝達手段です。5の手帳交付は、両耳70dB以上、または片耳90dBかつ他耳50dB以上が基準です(40dBでは原則交付されません)。
【受験生の皆さんへ】「フラッシュベル=音の増幅」で×を選べましたか?
「光」で知らせるのか、「音」を大きくするのか。道具の役割を正確に理解することは、利用者の生活課題(ニーズ)に合った提案をするために不可欠です。
「チャイムが聞こえない親の悩み」を想像しながら、各ツールの特徴を整理しましょう。
👉 家族の視点で「聴覚支援ツール」を理解する
問題56
Bさん(24歳,男性)は,母親と二人暮らしで,小学生のときに注意欠陥多動性障害と疑われていた。Bさんは,最近になって昼夜を問わずゲームを続け,朝起きられずにアルバイトを無断で休むことが増えた。
次のうち,Bさんの母親が相談する機関として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 ハローワーク(公共職業安定所)
- 2 難病情報センター
- 3 認知症カフェ
- 4 放課後等デイサービス
- 5 発達障害者支援センター
答え:5
解説:
Bさんは、子どもの頃に発達障害(注意欠陥多動性障害)の疑いがあり、現在もゲーム依存や無断欠勤など、社会生活への適応に課題を抱えている状況です。発達障害者支援センターは、年齢に関わらず、発達障害のある人やその家族からの相談に応じ、必要な助言や関係機関との調整を行う専門機関です。
1は職業紹介、2は難病、3は認知症、4は障害のある児童(学齢期)が対象のサービスであり、Bさんのケースには不適切です。
【受験生の皆さんへ】「発達障害者支援センター」の役割、あやふやではありませんか?
なぜ選択肢の「ハローワーク」や「難病情報センター」ではダメなのか。
Bさんのような「未診断だが疑いがある」「生活リズムが崩れている」というケースに対して、「包括的な支援」ができる唯一の機関だからです。事例を通して機関の役割を明確にしましょう。
👉 家族の視点で「支援センターの役割」を読む
問題57
次の記述のうち,「障害者差別解消法」の合理的配慮に沿った対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 車いすの身体障害者から,陳列棚にある商品を見せてほしいと言われたが,口頭で商品を説明した。
- 2 聴覚障害者の手話による注文がわからなかったので,最も人気のあるメニューを出した。
- 3 盲導犬を連れた視覚障害者が来店したが,動物嫌いの客から苦情を言われると思い,犬は店の中に入れないように頼んだ。
- 4 役所に相談に来た精神障害者から,多くの人の中だと不安になると言われたため,帰宅してもらった。
- 5 知的障害者から申し出があったので,会議に参加するための資料をわかりやすい言葉に直して,事前に口頭で説明した。
(注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
答え:5
解説:
合理的配慮とは、障害のある人から意思表明があった場合に、過度な負担にならない範囲で、社会的障壁(利用しにくいルールや設備、慣行など)を取り除くための個別の調整や変更を行うことです。5は、知的障害のある人の「わかりにくい」という障壁に対し、「わかりやすい言葉に直す」「事前に説明する」という申し出に基づいた調整を行っており、合理的配慮の適切な例です。
1、2、3、4は、いずれも本人の意思やニーズを無視・拒否しており、合理的配慮の不提供、あるいは不当な差別的取扱いに該当します。
【受験生の皆さんへ】「合理的配慮」を難しく考えすぎていませんか?
正解の選択肢は、常に「相手の障害特性に合わせて、手段を変更・調整しているもの」です。
「聞こえないなら筆談」「見えないなら読み上げ」「わからないなら噛み砕く」。生活の中にある当たり前の優しさが、そのまま答えになります。
👉 家族の視点で「合理的配慮の具体例」を読む
問題58
レスパイトケアの望ましいあり方に関する記述として,最も適切なものを 1つ選びなさい。
- 1 障害者はサービスを利用せずに生活するべきである。
- 2 利用中,家族は自宅で休まなくてはならない。
- 3 家族が障害者を預けて旅行に行くことは認められない。
- 4 家族の休息が目的なので,障害者の施設利用は宿泊に限定される。
- 5 家族が休息している間も,障害者が自分らしく過ごせるようにする。
答え:5
解説:
レスパイトケアは、介護を担う家族に一時的な休息(レスパイト)を提供し、心身のリフレッシュを図ってもらうことを主な目的としています。しかし、それは単に家族が休むためだけに本人が我慢するのではなく、サービスを利用する障害者本人も、その人らしく安心して楽しく過ごせるような支援が提供されることが望ましいあり方です。
1はレスパイトケアの否定です。2や3は、休息の方法(場所や目的)を不当に制限するものであり不適切です。4は、宿泊(ショートステイ)だけでなく、日中一時支援など様々な形態があります。
【受験生の皆さんへ】レスパイトを「家族のためだけのもの」と思っていませんか?
正解の選択肢にある「障害者が自分らしく過ごせるようにする」。ここがポイントです。
単なる「預かり」ではなく、「利用者にとっても有意義な時間にする」という視点が、質の高いケアにつながります。
👉 家族の視点で「レスパイトの理想形」を読む
医療的ケア
問題59
次の記述のうち,成人に対する救急蘇生法での胸骨圧迫の方法として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 呼吸が確認できない場合は,すぐに圧迫を始める。
- 2 圧迫する部位は,胸骨の左側である。
- 3 実施者の両手を重ねて,指先で圧迫する。
- 4 圧迫の深さは,胸が10cm沈むようにする。
- 5 1 分間に60回を目安に圧迫する。
答え:1
解説:
成人の一次救命処置(BLS)ガイドラインでは、傷病者に反応がなく、正常な呼吸(普段通りの呼吸)が確認できない場合、または呼吸があるか不明な場合は、ただちに胸骨圧迫を開始するとされています。よって1が正解です。
2の圧迫部位は、胸骨の左側ではなく「胸の真ん中(胸骨の下半分)」です。3は指先ではなく「手の付け根(掌基部)」で圧迫します。4の深さは約5cm(6cmを超えない)が推奨されています(10cmは深すぎます)。5の速さは1分間に100回~120回のテンポです(60回は少なすぎます)。
【受験生の皆さんへ】「カーラーの救命曲線」をただのグラフとして見ていませんか?
「3分で50%死亡」という数字の裏には、一刻を争う現場の緊張感があります。
なぜ「すぐに始める」ことが正解になるのか。その根拠となる時間の重みを理解すれば、迷うことなく選択肢を選べるようになります。
👉 家族の視点で「最初の3分の重み」を読む
問題60
次の記述のうち,痰を喀出する仕組みに関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 呼吸器官の内部は乾燥した状態になっている。
- 2 気管の内部の表面には絨毛があり,分泌物の侵入を防いでいる。
- 3 分泌物は,咽頭で吸収される。
- 4 痰は,咳や咳払いによって排出される。
- 5 咳は,下垂体にある咳中枢によっておこる反射運動である。
答え:4
解説:
気道から分泌された痰は、気道粘膜にある線毛(絨毛)運動によって咽頭部まで運ばれます。そして最終的に「咳」や「咳払い」といった反射的な運動によって口腔外へ排出されます。よって4が正解です。
1の呼吸器官内部は、粘液によって湿潤な状態に保たれています。2の線毛(絨毛)は、分泌物(痰)を体外へ「運び出す」役割を担っています。3の分泌物は咽頭で吸収されません(飲み込まれるか喀出されます)。5の咳中枢は、下垂体ではなく脳幹の「延髄」にあります。
【受験生の皆さんへ】「呼吸器=乾燥している」で×を選べましたか?
呼吸器は常に湿っていなければ機能しません。なぜなら、乾燥すると線毛が動けなくなり、防御機能が失われるからです。
「なぜ加湿ケアが必要なのか?」という現場の実践と結びつければ、身体の構造がリアルにイメージできるようになります。
👉 家族の視点で「痰出しのメカニズム」を読む
問題61
次の記述のうち,介護福祉士が行う口腔内の喀痰吸引の方法として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 吸引圧は,利用者の体調によって介護福祉士が決める。
- 2 吸引圧をかけた状態で,吸引チューブを挿入する。
- 3 口蓋垂まで吸引チューブを挿入する。
- 4 吸引チューブを回転させながら痰を吸引する。
- 5 吸引後は洗浄水を吸引し,清浄綿でチューブを拭く。
答え:4
解説:
吸引チューブを引き抜く際に、チューブを回転させながら操作することで、気道粘膜への刺激や損傷を最小限に抑えつつ、効率よく痰を吸引することができます。これは安全な吸引のための重要な手技です。
1の吸引圧は、介護福祉士が判断せず、医師や看護師の指示に従います。2は粘膜を損傷するため、吸引圧をかけずに挿入します。3は不適切です。挿入の深さは痰が溜まっている位置までであり、口蓋垂(のどひこ)まで深く挿入すると嘔吐反射を誘発する危険があります。5は吸引後の処置としては正しいですが、吸引「中」の最も適切な方法(手技)としては4が最適です。
【受験生の皆さんへ】「カテーテルを回す」=「粘膜保護」。このリンクができていますか?
手順を丸暗記するのではなく、「掃除機がカーテンに吸い付くのを防ぐ動き」とイメージすれば、現場でも自然と手が動くようになります。
利用者さんの痛みを想像しながら、安全な手技の根拠を学びましょう。
👉 家族の視点で「吸引の優しさ」を理解する
問題62
次の記述のうち,消化器症状の説明として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1 腹部膨満感は,腹部が張る感覚のことである。
- 2 しゃっくり(吃逆)は,胸膜の刺激で起こる現象である。
- 3 胸やけは,飲食物による食道の熱傷のことである。
- 4 げっぷ(噯気)は,咽頭にたまった空気が排出されることである。
- 5 嘔気は,胃や腸の内容物が,食道を逆流して口外に吐き出されることである。
答え:1
解説:
腹部膨満感は、消化管内にガスや便が溜まることなどにより、お腹が張る、苦しいと感じる自覚症状のことです。1は正しく説明しています。
2のしゃっくりは、主に横隔膜のけいれんによって起こります。3の胸やけは、胃酸が食道に逆流することによって生じる灼熱感(焼けるような感覚)です。4のげっぷは、胃に溜まった空気が食道を経て口外に出ることです。5は「嘔吐」の説明であり、「嘔気」は吐き気(むかつき)という感覚(吐きたい感じ)を指します。
【受験生の皆さんへ】「胸やけ」や「げっぷ」の定義、あやふやではありませんか?
日常語だからこそ、医学的な定義を問われると迷いやすいものです。
「腹部膨満感」がなぜ苦しいのか、経管栄養の方になぜ注意が必要なのか。「ガスが溜まったお腹の苦しさ」を想像しながら学習すれば、知識が現場で使えるものになります。
👉 家族の視点で「お腹の張り」の辛さを理解する
問題63
Aさん(80歳,女性)は,脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症で左片麻痺があり,介護老人保健施設に入所して在宅復帰に向けた訓練をしている。嚥下障害もあるため,経鼻経管栄養による栄養摂取をしているが,経口摂取できないことでイライラしてチューブを抜去したことがある。医師からは一時的な治療であると説明を受けて同意していた。
経管栄養中に介護福祉士が訪室すると,チューブを触りながら,「自分の口から食べたいから,このチューブを抜いてほしい。見た目も良くない」と訴えがあった。看護師に連絡し,チューブが抜けていないことを確認してもらった。
このときのAさんへの介護福祉士の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1 チューブを抜かないようにAさんの右手を固定する。
- 2 経管栄養が早く終わるように滴下速度を調節する。
- 3 医師や看護師にAさんの思いを伝える。
- 4 Aさんに胃ろうの造設を提案する。
- 5 Aさんに経口摂取を提案する。
答え:3
解説:
Aさんは経管栄養に対し「口から食べたい」「見た目が良くない」という強い思い(苦痛や希望)を訴えています。介護福祉職はまず、その訴えを受け止め、Aさんの代弁者(アドボカシー)として、その思いを医師や看護師などの医療職に正確に伝えることが最も重要です。これにより、チーム全体でAさんのQOL(生活の質)向上や意欲の維持に向けた支援(リハビリの進め方や今後の見通しの再説明など)を検討できます。
1の身体拘束は不適切です。2の滴下速度の調整は医療行為であり、介護福祉職は行えません。4(胃ろうの提案)や5(経口摂取の提案)は、嚥下障害のあるAさんに対する医学的な治療方針の変更提案であり、介護福祉職の役割を逸脱しています。
【受験生の皆さんへ】「医療職への伝達」がなぜ正解になるのか?
Aさんの「食べたい」という訴えは、単なる不満ではなく「QOL向上のための重要なニーズ」です。
介護職だけで抱え込まず、医師や看護師と連携する「チームアプローチ」の重要性を、具体的なエピソードを通して理解しましょう。
👉 家族の視点で「思いをつなぐケア」を読む
過去の問題はこちら
(令和6年度午前)介護福祉士国家試験 問題・解答・解説 (当ページ)